山寺香 『誰もボクを見ていない なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか』 ― 2018/11/01

祖父母や親を殺す少年犯罪が頻繁に起こるので驚くことがなくなり、またかとしか思わなくなってきています。
この事件は2014年埼玉県川口市で発生しましたが、残念ながら覚えていません。
殺した少年のことを当時のマスコミは詳しく報道していたのかしら?
祖父母を殺したと報道された時は、ただ単にお金が欲しいから祖父母を殺したと思ったと思います。
しかし、この本を読むと、少年の置かれていた家庭が普通ではないのがわかります。
悲惨な成育環境です。
彼が母親から引き離されていれば、このような事件は起こっていなかったでしょうに。
誰か彼の本音を引き出せる大人がいたら・・・と思います。
でも、そういう人ってなかなかいませんよね。
自分の周りに彼のような子がいるかどうか、残念ながら私には気付けませんもの。
一体どうすればいいのか・・・。
難しいことです。
自分の力の至らなさを感じつつ、出所してからの彼の人生が少しでも良くなることを心から望みます。
内田洋子 『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』 ― 2018/09/30

著者の内田さんは住んでいるヴェネツィアで見つけた古書店に何度か通ううちに店主と話をするようになりました。
話の中で、彼の先祖がトスカーナの山奥の村、モンテレッジォ出身で、本を籠に入れて売り歩いていたというのを聞き、モンテレッジォに興味を持ちます。
古書で村のことを調べようとすると、店主が実際に行ってみるとよいと言います。
有志が立ち上げた村を紹介するサイトを見て問い合わせをすると、ミラノまで迎えに来てくれ、一緒に村に行くことになります。
未知の村への旅のはじまりです。
モンテレッジォは人口が32人という村で、イタリアの文学賞の一つ、「露天商(バンカレッラ)賞」の発祥の地です。
ちなみに第一回の受賞者はヘミングウェイで、村の入り口で彼が迎えてくれます。
特産物は石と栗。
<夏のない年>、生き残るために本を売り歩くことにしました。
次々と明らかになっていく事実に、ミステリーを読んでいるような感じになります。
何と言っても写真が美しいです。
夏には各地に散った行商人の子孫や親戚縁者が村に帰って来て、祭があるそうです。
一度、行ってみたいですね。
「モンテレッジォは、本の魂が生まれた村なのだ」
この言葉が全てを表しています。
石井光太 『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』 ― 2018/09/23
本屋さんたちも考えること。
「本屋大賞」で主に小説を選んでいましたが、今度はノンフィクション部門ができました。
「本屋大賞 ノンフィクション本大賞」だそうです。
ノミネート作品が決まり、二次選考をして11月に大賞作品が発表されるそうです。
「本屋大賞」ほど売れるかどうか・・・。
私は図書館で借りれたり、kindleで読めるなら出来る限り読んでみようと思います。
では、ノミネート作品のひとつ、『43回の殺意』を紹介しましょう。

2015年2月、神奈川県川崎市の多摩川河川敷で13歳の少年の全裸遺体が発見された。
少年の体にはカッターで傷つけられた43か所の傷跡が見つかった。
一週間後、逮捕されたのが17歳と18歳の未成年3人。
殺害に至るまでの状況を裁判の証言に基づいて再現し、事件後起こったインターネットによる「犯人捜し」や河川敷を訪れた1万人にも及ぶ人々の「善意」、被害者と加害者たちの生い立ち、そして、同じグループだった友人たちと殺された遼大の父親の証言などが書かれています。
読んでいて残念だったのは、被害者の母親からの証言は取れなかったようで、父親からの見方だけということです。
不思議だったのは、河川敷に1万人近くの人々が訪れたのは何故なのかということです。
「河川敷に集まる人々の間で、遼太は宗教のように偶像化されていったのかもしれない」と著者は書いていますが、ニュースで報道されたのを見ましたが、何とも奇妙な光景でした。
そして、著者も疑問を呈していましたが、加害者の一人が保護観察中だったというけれど、保護観察制度は実際に機能しているのでしょうか。
心が切なくなる事件です。
家庭とか周りの環境が悪かったとか、運が悪かったとか言ってすっぱり切り捨てられるような事件ではありません。
こういう事件が起こらないように、何ができるのか。
何か事件が起こるたびにこの答えのない問いを繰り返すしかないのでしょうねぇ。
水野敬也 『顔ニモマケズ どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語』 ― 2018/09/21

相当前に雑誌で紹介されていた本です。
その時は図書館の予約数が多かったので、読むのを諦めていました。
どんな人でもコンプレックスを持っているもんじゃないですか?
例えば醜形恐怖症にまではいかないけれど、でも自分の顔のここが嫌、もっと綺麗に、恰好よく生まれてくればと思っていない人っていないと思います。
でも、結局はどうしようもなく、悩みつつも折り合いをつけて生きていますよね。
この本は病気で「見た目に傷や痣などの症状を持つ「見た目問題」当事者の方たち」と著者が「会話を重ね、外見から生まれる仕事や恋愛の問題をどのように乗り超えていったか」をインタビューして書いていった本です。
見かけのコンプレックスのある人以外にも、人間関係に悩んでいる人や就職や仕事のことで悩んでいる人、コニュニケーションが苦手な人など様々なことで悩んでいる人が読むと、「生きるヒント」がもらえるかもしれません。
どの人も素敵です。
著者が後書きで書いています。
「乗り越えた悩みが大きければ大きいほど、人は魅力的になれる」と。
その通りだと思いますが、自分のことを振り返ると・・・(苦笑)。
花田菜々子 『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』 ― 2018/09/12
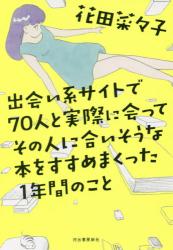
夫と別居し、一人暮らしを始めた書店員の菜々子さんは、出会い系サイト「X」に登録し、そこで出会った人にぴったりの本をお勧めすることを思い立つ。
「X」のコンセプトは「知らない人と30分だけ会って、話してみる」
初めの2人はできればセックスをやりたいという人でしたが、それ以降は「X」の使い方がわかったからか、それなりの人と出会えています。
しかし、なんで出会い系?
勇気あると思います。
私なんか、知らない人と会うのが大嫌いですから。
でも、その人に合った本を紹介するというのはおもしろいですね。
私も本を紹介してもらいたいものです。
それにしても、会って本をすすめた人たちの何割がその本を読んだんでしょうね。
気になります。
後ろに紹介した本のリストがありますが、実は花田さんの紹介した本のほとんどを読んでいません。
彼女と私の好みが全く違います。
まあ、それもおもしろいのですがね。
気になった本をこれから読んでみますわ。
題名に惑わされて、間違って買わない様にね。
まじめな自分探しと本紹介の本ですから。
川名壮志 『謝るなら、いつでもおいで 佐世保小六女児同級生殺害事件』 ― 2018/09/10
暗い報道が多い中、大坂なおみさんの全米制覇の話題は嬉しいものですね。
グラフの頃からテニスの試合を見ていた私にとって、日本人が取ったというのが驚きです(彼女のことを日本人じゃないと言う人もいるようですが、お母様が日本人ですから、OKじゃないですか?)。
セリーナさんの行動が残念でしたが、あれは考えてやっていたのでしょうね。
まともに戦うと負けるのがわかっていたので、精神的に弱いなおみさんを揺さぶる意味もあったのでしょう(と思いたいけど、そうじゃなかったら、怖いわぁ。)
とにかく、おめでとう!
と書きながら、紹介する本は重いものです。

1997年に酒鬼薔薇聖斗事件が起こり、少年犯罪の凶悪化がマスコミで取り上げられるようになり、この小学校6年生の女の子が、同級生を殺したという事件は2004年に起こりました。
本を書いたのは、被害者の少女の父親の直属の部下で毎日新聞記者の方です。
加害者と被害者の両方を知っている、事件当時から関わってきた人です。
当時の学校の混乱した様子や佐世保支局内のこと、被害者家族のこと、加害者と被害者の関係、加害者の父との会話、被害者の父と兄の話などが克明に書かれています。
勉強不足で、この本で知ったのですが、14歳以下の子どもには少年法ではなく「児童福祉法」が適用されるそうです。
「児童福祉法」では非行少年の「保護」をうたっており、犯した犯罪の軽重は問わず、「加害者」であっても「社会の網の目からこぼれ落ちた被害者」とみなし、子どもの福祉を一番の目的としています。(p.53)
そのため刑も罰も科せられず、加害者の少女は児童自立支援施設に収容されました。
少年たちは「可塑性」に富んでいるから、大人と同じ刑を科すことができないとは言うけれど、どうなんでしょうか。
この事件とは関係ないのですが、足立区で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」で逮捕された4人の少年たちは出所後、また犯罪を犯していると聞きました。
彼らは特別なんでしょうか?
少年であっても罪の重さに応じて刑を科す方がいいのではないでしょうか?
被害者の家庭は母親が癌で亡くなっていました。
被害者の女の子はその寂しさや友達とのことを父親には言えなかったようです。
父親は加害者の少女に関してこう書いています。
「あの子とあの子の家族はやり直しができるんですよね。でも、僕のところはやり直しができない。失ったまま。それはわかってくれど。もちろんね、相手も平穏な生活が崩れたことは承知している」
「それでもやり直しができるということは、向こうにとっての「救い」だよね」
「被害者なんてものは、救いがあるなんて思っていないんだよ」
「あの子には生きて抱えてもらいたいと思っている」
この本を読んで一番の被害者は殺された少女の兄ではないかと思いました。
彼は被害者家族でありながら、必要な援助がなされていなかったのです。
警察からも教師からも誰からも事件について聞かれず、父は悲嘆に沈み、精神的におかしくなりそうな状態だし、周りは何を彼に言ったらいいのかわからず、声をかけられず、学校にいたスクールカウンセラーさえも話しかけてこなかったそうです。
彼は話したかったのです。
怒りをぶつけたかったのです。
中1だった彼は高校を卒業するような年齢になっています。
彼は加害者の少女に対して、「普通に生きてほしい」、「一度きちんと謝る。謝ってもらった後は、お互い自分の生活に戻る」などと言っています。
自分の妹を殺した相手にこんなことを言えるなんて・・・。
彼こそ、一番ケアが必要だったのに。
彼の言葉は彼女に届いているでしょうか。
山本雅也 『キッチハイク!突撃!世界の晩ごはん』 ― 2018/09/03

450日をかけて世界一周をし、見知らぬ地元の人に家庭料理をおごってもらおうという調子のいい本。
全く知らない人とどうやって知り合って、どういう声掛けをしたのか知りたかったのですが、これは書いてありません。
家に行って、料理を作ってもらい、食べるまでしか書いていません。
全く知らない人に声をかけて食べさせてもらうよりも、知り合いの紹介の方が多いです。
まあ、そうでしょうねぇ。
日本のテレビ番組でも「あなたのご飯をみせてください」などという図々しいものがありますが、よくみなさん、見せてくれるなと思います。
もう少し、写真が欲しかった。
料理を作っているところ、料理の写真、食べている写真等がふんだんにのっているとよかったのに。
個人的には各国の家庭料理を御馳走になるというコンセプトはいいけれど、著者の性格があまり好きではないです。

谷中に用事があったので、行ってきました。
鰻を食べたのですが、前日の残りをまた焼いたのかと思えるほど皮が焼き過ぎで堅く、タレも甘辛く、残念な鰻でした。
もう行きませんわ。
谷中に新しくカフェがオープンしていました。
「CIBI」という本店がメルボルンにあるカフェです。
時間がなくて入れなかったのですが、見た感じ、流行っているようです。
鰻よりもここに入ればよかったわ(笑)。
村中璃子 『10万個の子宮 あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか』 ― 2018/08/06

何年か前に子宮頸がんワクチンを女子高校生全員が接種することになったと聞きましたが、しばらくすると中止になりました。
ワクチンを接種した子の中に激しい副反応に悩まされている子がいると報道されたからです。
しかし、この本を読むと、副反応はワクチンのせいではなかったことになっています。
WHOは繰り返し声明を出し、日本では「(ワクチン接種を止めた)せいで子宮頸がんの死亡率が上昇している」と名指しで批判しているそうです。
何故日本ではけいれんや記憶低下などの神経の異常を思わせる症状が、ワクチン接種と関係があるのか、ないのかということを科学的に検証し、報道されないのでしょうか。
本書によると、「日本だけで毎年、3000の命と一万の子宮がうしなわれている」と言います。国賠訴訟が終わるまでの10年間、この状態が続くと、10万個の子宮が失われてしまいます。
ワクチン接種をすることにより子宮頸がんに罹らなければ、無駄に子宮を取らなくてもよかったし、命を失うこともなかったはずなのです。
なんでこんなことになってしまったのでしょうか。
現役の医師でジャーナリストの村中さんが名誉棄損で訴えられながらも、真実を訴えたいと書いた本です。
娘さんのいる親に是非とも読んでもらいたい本です。
堀川恵子 『教誨師』 ― 2018/08/03

「教誨師」とは「受刑者に面会し、教誨(教えさとす)や教戒(教え戒める)を行う人」で、主に僧侶や神職、牧師、神父などがなっています。
この本では50年もの長きにおいて死刑囚の教誨師をしていた渡邉普相のことが書かれています。
堀川さんは死んでから世に出すとの約束で、彼から話を聞きました。
彼の生い立ちや教誨師になったきっかけ、心に残る死刑囚や死刑執行立ち会いのことなどの他に知らされていない死刑執行の実態が描かれています。
先日、オウム真理教の人たちの死刑執行が行われたので、もしいたのなら彼らの教誨師はどの宗教の人だったのか、執行の前に何を言ったのかを知りたいと思いました。
死刑制度については賛否両論があります。
賛成か反対かは、それぞれの人が考えるべきことですが、この本を読むと死刑が必要なのかと疑問に思うようになります。
死刑は人が人を殺す、「人殺し」(渡邉曰く)ですから。
例えば、仕事であるからと言っても死刑を執行した刑務官(でいいのかな?)の心に何も影響を与えないということはないでしょう。
教誨師の立場からしても、今まで関係を持っていた人が自分の目の前で亡くなるのですから。
渡邉でさえアルコール依存症で苦しみます。
罪は贖うべきですが、死刑にしてまで贖うべきでしょうか。
死刑制度について深く考えさせられる本です。
鈴木大介 『されど愛しきお妻様 「大人の発達障害の」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間」 ― 2018/03/21

トリミングしたての犬たちです。
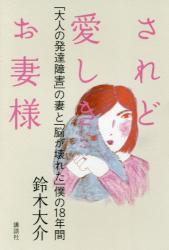
子どもの発達障害についてはそれなりに知っていますが、彼らが大人になったらどうなるのかはあまり知りませんでした。
仕事仲間の中にこの人なんでこうなんだろうと不思議に思う人が結構いました。
たぶんその人は大人の発達障害だったのかもしれませんね。
そう思うと、納得できることもあります。
(もちろん、すべてがそうだとはいいませんが。)
この本のことを簡単に言うと、発達障害の妻が何故そうするのか、またはできないのかが理解できずに、心無い言葉を投げかけていた著者が41歳の時に脳梗塞で高次脳機能障害になり、妻のことを少なからず理解でき、それからの二人は互いの出来ない所を補いつつ暮すようになっていっているというお話です(簡単すぎw)。
実は私の義理の姉が高次脳機能障害です。
くも膜下出血で3回手術をしています。
たまに会うと、兄が姉にかける言葉にびっくりします。
日常的に接していると、障害のことをわかっていてもイライラすることがあるのだろうと思いますが、聞いてる方は嫌になります。
なかなか高次脳機能障害ってわかりずらいのです。
なにせ見えないのですから。
発達障害や高次脳機能障害のある大人に対する援助ってどうなっているのでしょうか。
手術後、姉はしばらく老人用のデイサービスに通っていましたが、今は通っていません。
一緒に暮らしていた母が亡くなったので、日常的に話す人がいなくなってしまい、どうなるのか心配していますが、彼女の実家が近いので、どうにかなるでしょう。
なかなか社会全体でみるという仕組みができていないですから、家族で抱え込むしかないですね。
鈴木さんはルポライターという習性からか、障害を持った後の自分のことを本に書いています。
書いていただくことで世間の認識が変わるといいですね。
最近のコメント