朝吹真理子 『きことわ』 ― 2011/03/02

芥川賞を受賞した『きことわ』を読んでみました。
母親が管理人をしていた葉山の別荘に、永遠子は母親の代わりに25年ぶりに訪れることになります。別荘が売られることになり、片づけをしなければならなかったからです。
別荘の持ち主の家族には貴子という、永遠子と七つ違いの女の子がいました。二人は仲良しで、別荘では一緒に過ごしていました。
貴子の心臓の弱い母親が死んでから、永遠子は別荘に行くことがなくなりました。
25年ぶりに別荘で貴子と再会します。
夢かうつつか、二人の過去と現在が交差していきます。
この本が好きかと言われると、残念ながらあまりというしかありません。これといった出来事もなく、あれこれと止めどなく流れていく意識の流れに退屈さを感じたのです。
私は文を味わう人ではないからなのかもしれません。
「恋するベーカリー」を見る ― 2011/03/03
ひょっとしたらメリル・ストリープの地に近い役なのかもしれません。
「プラダ…」の怖い上司ではなく、「ジュリー&ジュリア」の飛んだおばさんではなく、どっちかというと「恋に落ちたら」の女性が年を取ったら・・・と思わせられました。
「プラダ…」の怖い上司ではなく、「ジュリー&ジュリア」の飛んだおばさんではなく、どっちかというと「恋に落ちたら」の女性が年を取ったら・・・と思わせられました。

10年前に離婚し、今はベーカリーを経営して成功しているジェーンは50歳を過ぎ、一抹の寂しさを感じるこの頃。
家を増改築して理想のキッチンを作ろうと思っています。
三人目の子供のルークが大学を卒業するため、家族がNYに集まります。
子どもたちが出かけてしまったため、一人ホテルで食事をしようと思っていたところに、元夫のジェイクが現れ、二人は一緒に飲むことになってしまいます。
そして、いつしか意気投合してしまい、ベッドインへと・・・。
家を増改築して理想のキッチンを作ろうと思っています。
三人目の子供のルークが大学を卒業するため、家族がNYに集まります。
子どもたちが出かけてしまったため、一人ホテルで食事をしようと思っていたところに、元夫のジェイクが現れ、二人は一緒に飲むことになってしまいます。
そして、いつしか意気投合してしまい、ベッドインへと・・・。
なんで私が元夫と不倫をしなけりゃならないのと悩むジェーンですが、ジェイクは若い妻と子に飽き飽きしていたこともあり、ジェーンに夢中になってしまいます。
ジェイクの一人よがりのところが笑えます。(アレック・ボールドウィン、太ったわねぇ・・)
ジェーンにはジェイク以外にも気になる男性がいます。建築家のアダムです。
ジェーンにはジェイク以外にも気になる男性がいます。建築家のアダムです。
彼は2年前に離婚し、まだ離婚の痛手から立ち直っていません。
ジェーンに好意を寄せるアダムの言葉がいいです。
「年齢も君の魅力だよ」
一度でもいいから、誰かに言ってもらいたいわ。あ、私の場合は
「体重も君の魅力だよ」かしら・・・。
後半のアダムの大人~な言動が素敵です。
母親と父親が復縁するのではと、戸惑う子供たち。
彼らは親の離婚で傷ついていたのです。
そうそう、長女ローレンの婚約者のハーレイ君(↓)、いいキャラです。婚約者の家族のことを真剣に心配しています。義理の父母がホテルで密会するのを見ちゃって、その後のフォローがナイスです。
「年齢も君の魅力だよ」
一度でもいいから、誰かに言ってもらいたいわ。あ、私の場合は
「体重も君の魅力だよ」かしら・・・。
後半のアダムの大人~な言動が素敵です。
母親と父親が復縁するのではと、戸惑う子供たち。
彼らは親の離婚で傷ついていたのです。
そうそう、長女ローレンの婚約者のハーレイ君(↓)、いいキャラです。婚約者の家族のことを真剣に心配しています。義理の父母がホテルで密会するのを見ちゃって、その後のフォローがナイスです。

二人の男性と子供たちの間で複雑な心境のジェーン。
さて、彼女の出した答えは・・・。
良質な(・・・ちょっとお下品という場面もありますが)大人のラブコメディです。
メリルの自然な表情がとっても魅力的です。彼女のしわもいいと私は思いますが、男性はどうなんでしょうね。
メリルを見ていると、年をとるのが怖くなくなります。
邦題は『恋するベーカリー』ですが、特にベーカリーとは関係ない話です。最初と中間のアダムと一緒にチョコレートクロワッサンを作る時に出てくるぐらいです。
そうそう、一番美味しそうだったのが、チョコレートクロワッサン。夜中にベーカリーで一緒に作るチョコレートクロワッサンって美味しそうです。
「英国王のスピーチ」を観る ― 2011/03/05
アカデミー賞の「作品賞」、「主演男優賞」、「監督賞」、「脚本賞」の四冠を取った映画です。私としては「助演男優賞」も取って欲しかったです。
そうそうヒュー・グラントがコリンの役を断って後悔しているそうです。彼が演じたらどうなったのかしら?アカデミー賞は…無理だったかもね。
そうそうヒュー・グラントがコリンの役を断って後悔しているそうです。彼が演じたらどうなったのかしら?アカデミー賞は…無理だったかもね。

現エリザベス女王の父親、ジョージ6世は、兄がアメリカ人女性で離婚経験があるシンプソン夫人と結婚するために王様になった人。その彼が吃音だったなんて、知りませんでした。
父親のジョージ5世は厳格な人だというのがよくわかりました。映画で息子が吃音でスピーチを苦手としているのを知りながらも博覧会の閉会式でスピーチをやらせるところが出てきます。王族というもの、それぐらいできなくてどうするんだというスパルタ教育ですかね。
ジョージ6世が吃音になったのは、彼自身の性格や父親からの心理的圧迫、幼少期の乳母からの肉体的虐待、家庭教師の厳格な指導、左利きやX脚の矯正、兄との軋轢など色々な要因が関係していたようです。
ジョージは2人の子供にも恵まれ、結婚は幸せなものでした。王にならなかったら、のんびりと暮らせたのでしょうね。
夫思いの妻のエリザベス(エリザベス女王のお母様)は吃音を治してくれる治療者を探しまわっていました。
医師の治療の失敗に終わった後、オーストラリア人のスピーチ矯正専門家ライオネル・ローグのところにジョージを連れて行きます。
彼は今までの治療者とは違い、吃音になるには心が関わっているのだという考えでした。
ライオネルのユニークな治療方法に反発しながらも、いつしか彼のことを頼るようになっていくジョージ。
兄がシンプソン夫人と結婚するために王位を退いたため、思ってもいなかった王位につくことになってしまいます。
自分は王になるべき人間ではないという思いに苛まれるジョージにライオネルは、あなたは王様に相応しい人であると励まし続けます。
王様であれ、誰であれ、幼いころにお前はクズだ。お前はダメな奴だ。お前は・・・、と言い続けられていると、ジョージのように吃音にならなかったとしても、自分に自信がない人間になってしまいますよね。
ジョージ6世のような社会的責任のある人ならなおのこと、どうにかならない方がおかしいです。
そういう王様の人間らしさを赤裸々に描いたのが、この映画。
真に英国らしい映画です。
日本の皇室の映画って・・・できないでしょうねぇ。
コリン・ファースはポスターで見ると恰幅がいいように見えたのですが(頭が西洋人にしては大きいのかしら?)、映画では全然太っていませんでした。失礼。
父親のジョージ5世は厳格な人だというのがよくわかりました。映画で息子が吃音でスピーチを苦手としているのを知りながらも博覧会の閉会式でスピーチをやらせるところが出てきます。王族というもの、それぐらいできなくてどうするんだというスパルタ教育ですかね。
ジョージ6世が吃音になったのは、彼自身の性格や父親からの心理的圧迫、幼少期の乳母からの肉体的虐待、家庭教師の厳格な指導、左利きやX脚の矯正、兄との軋轢など色々な要因が関係していたようです。
ジョージは2人の子供にも恵まれ、結婚は幸せなものでした。王にならなかったら、のんびりと暮らせたのでしょうね。
夫思いの妻のエリザベス(エリザベス女王のお母様)は吃音を治してくれる治療者を探しまわっていました。
医師の治療の失敗に終わった後、オーストラリア人のスピーチ矯正専門家ライオネル・ローグのところにジョージを連れて行きます。
彼は今までの治療者とは違い、吃音になるには心が関わっているのだという考えでした。
ライオネルのユニークな治療方法に反発しながらも、いつしか彼のことを頼るようになっていくジョージ。
兄がシンプソン夫人と結婚するために王位を退いたため、思ってもいなかった王位につくことになってしまいます。
自分は王になるべき人間ではないという思いに苛まれるジョージにライオネルは、あなたは王様に相応しい人であると励まし続けます。
王様であれ、誰であれ、幼いころにお前はクズだ。お前はダメな奴だ。お前は・・・、と言い続けられていると、ジョージのように吃音にならなかったとしても、自分に自信がない人間になってしまいますよね。
ジョージ6世のような社会的責任のある人ならなおのこと、どうにかならない方がおかしいです。
そういう王様の人間らしさを赤裸々に描いたのが、この映画。
真に英国らしい映画です。
日本の皇室の映画って・・・できないでしょうねぇ。
コリン・ファースはポスターで見ると恰幅がいいように見えたのですが(頭が西洋人にしては大きいのかしら?)、映画では全然太っていませんでした。失礼。
若い頃の彼(↓格好良すぎる!)と「マンマ・ミーア」の年を取った彼とのギャップが大きすぎて、私の中ではまだ消化しきれていないようです。

ヘレナが王族に見えたかというと、何とも言えません。彼女って変な役ばかりしているので、真っ当な姿を見ると見慣れないので不思議に思ってしまいます。
ヘレナの着ている衣装が地味でしたが、エリザベス女王のお母様って地味好みだったっけ?
最後のスピーチの場面では、ライオネルと一緒にジョージに頑張れっていっている自分がいました。
コリン、上手いわね~。
ライオネルの御鼻、妙に気に入りました(笑)。
ライオネルの御鼻、妙に気に入りました(笑)。
「フェルメール≪地理学者≫とオランダ・フランドル絵画展」@ザ・ミュージアム ― 2011/03/06
オランダ・フランドル絵画展というので、絵画がオランダの美術館からだと思ったら違っていました。ドイツのフランクフルトのシュテーデル美術館の所蔵でした。
オランダと言えばブリューゲル。
ブリューゲルと言っても、ピーテル・ブリューゲル親子とこの展覧会に展示されているヤン・ブリューゲル親子がいて、ややこしいです。
ピーテル・ブリューゲル父は「農民の画家ブリューゲル」で、有名な「イカロスの墜落のある風景」や「バベルの塔」、「雪の中の狩人」などを描いた人です。
ピーテル・ブリューゲル子は「地獄のブリューゲル」と呼ばれています。変なキャラクターの絵は彼のかな?お父さんのにも奇怪な動物が描かれているような。
ヤン・ブリューゲルはピーテル・ブリューゲル父の息子です。ということは、ピーテル・ブリューゲル子の弟ということです。彼には2人子供がいて、長男もヤン・ブリューゲルといい画家です。ヤン・ブリューゲル父は「花のブリューゲル」と言われているそうです。
今回はヤン・ブリューゲル親子の絵が展示されています。
子の絵は「楽園でのエヴァの創造」1630年代後半(↓)。
オランダと言えばブリューゲル。
ブリューゲルと言っても、ピーテル・ブリューゲル親子とこの展覧会に展示されているヤン・ブリューゲル親子がいて、ややこしいです。
ピーテル・ブリューゲル父は「農民の画家ブリューゲル」で、有名な「イカロスの墜落のある風景」や「バベルの塔」、「雪の中の狩人」などを描いた人です。
ピーテル・ブリューゲル子は「地獄のブリューゲル」と呼ばれています。変なキャラクターの絵は彼のかな?お父さんのにも奇怪な動物が描かれているような。
ヤン・ブリューゲルはピーテル・ブリューゲル父の息子です。ということは、ピーテル・ブリューゲル子の弟ということです。彼には2人子供がいて、長男もヤン・ブリューゲルといい画家です。ヤン・ブリューゲル父は「花のブリューゲル」と言われているそうです。
今回はヤン・ブリューゲル親子の絵が展示されています。
子の絵は「楽園でのエヴァの創造」1630年代後半(↓)。

父の絵は3点。「嘲笑されるラトナ」1601年と「人物のいる森の風景」1605-10年、工房の「ガラスの花瓶に生けた花」1610-25年頃(↓)。

描かれている花は季節外れのものがあったりするそうで、頭の中で想像して描いたのでしょうね。
ピーテル親子の絵に比べるとスケールが小さいようです。
展覧会は5つに分かれています。
<歴史画と寓意画>
<肖像画>
<風俗画と室内画>
<静物画>
<地誌と風景画>
特に風俗画はおもしろかったです。
酒とたばこを嗜む男性たちの姿や足や背中の手術で痛がっている男たちとか。
たばことか酒はこの頃からも嗜好品として人気があるのですね。
静物画では花の絵が一枚欲しいですわ。
花を描いた女性の画家のラッヘル・ルイスの絵が気に入りました。他にも描いていないのでしょうか?
「死んだ野兎と鳥のある静物」や「死んだ家禽のある静物」、「調理台の上の魚」とかは、どこに飾ってあったのでしょうね。
台所ならいいのですが、居間なら、趣味悪いですわ。
この展覧会の一番の見どころは、やっぱりフェルメールの「地理学者」1669年。
ピーテル親子の絵に比べるとスケールが小さいようです。
展覧会は5つに分かれています。
<歴史画と寓意画>
<肖像画>
<風俗画と室内画>
<静物画>
<地誌と風景画>
特に風俗画はおもしろかったです。
酒とたばこを嗜む男性たちの姿や足や背中の手術で痛がっている男たちとか。
たばことか酒はこの頃からも嗜好品として人気があるのですね。
静物画では花の絵が一枚欲しいですわ。
花を描いた女性の画家のラッヘル・ルイスの絵が気に入りました。他にも描いていないのでしょうか?
「死んだ野兎と鳥のある静物」や「死んだ家禽のある静物」、「調理台の上の魚」とかは、どこに飾ってあったのでしょうね。
台所ならいいのですが、居間なら、趣味悪いですわ。
この展覧会の一番の見どころは、やっぱりフェルメールの「地理学者」1669年。

この絵に描かれている時代の地球儀や地図、コンパスなどが会場に飾られています。男性の来ている衣服やコブラン織(でいいのかな?)はなかったですが。
この衣装、なにやらかいまき風ですね。女性の服装は絵に描かれているのでわかるのですが、男性はどうでしたっけ?
それにしても日本にいるということは幸せですね。
フェルメールの絵をわざわざ外国まで見に行かなくても見られるのですから。
近藤 史恵―キリコ&大介・シリーズ ― 2011/03/08

オペレータールーム勤務になった梶本大介がロビーで見かけたのが、ビルの清掃をしているキリコという女の子。
彼女は普通の清掃員ではなく、ピアスを三つも四つもつけている、渋谷や原宿を歩いているようなお洒落なタイプ。
彼女が歩いた後に、1ミクロンの塵も落ちていないっていう掃除の天才。
キリコのすごいところは、何よりも掃除が大好きだっていうこと。
そんなある日、大輔の机の上の書類がなくなるということが続き、無くなった書類を見つけてくれたのがキリコでした。
キリコは見つけた書類を渡してくれず、不思議なことを言うのでした。
ひょんなことをきっかけにして、大介はキリコと仲良くなり、キリコの力を借りて、会社の中の不思議を解決していきます。
表紙の印象から、明るいスッキリしたミステリーだと思っていたら・・・。
人が生きていくうちに色々と遭遇する、人間の暗い面が浮き彫りになっていきます。
大介ってちょっと根暗かな・・・?
このシリーズ、四作目まで出ていますが、二作目と三作目は売り切れらしく、古本屋か図書館で探すしかなさそうです。
四作目は『モップの精と二匹のアルマジロ』という長編物。

結婚したキリコと大介。
キリコが大介の勤務する会社のあるオフィスビルの清掃をすることに。
オフィスビルの中にあるシステムキッチンの会社に夫が務めているという女性から、キリコは夫の浮気調査を依頼されます。
調べ始めてからしばらくして、その夫は轢き逃げされ、三年間の記憶を無くしてしまいます。
彼は本当に浮気をしていたのでしょうか。
夫婦とは何か?
ちょっぴり切なく、悲しい物語です。
「ヤマアラシのジレンマ」とは哲学用語ですが、「アルマジロ」とは・・・?
近藤さんによる、おもしろい比喩ですね。
NHK「無縁社会プロジェクト」取材班 『無縁社会~”無縁死”三万二千人の衝撃~」 ― 2011/03/09
NHKスペシャルで放送していた番組は見ていません。
本が出たというので、読んでみました。
本が出たというので、読んでみました。

「行旅死亡人」という言葉があるのを知りませんでした。「住所、居住、もしくは氏名が知れず、遺体の引き取り者なき死亡人」のことを言うそうです。
今、「行旅死亡人」や「引き取り拒否の遺体」、縁者の見つからない遺体などが増えているそうです。
この理由として高齢化、雇用の悪化、家族の崩壊、血縁の気薄さ、地域のつながりの喪失、生涯未婚の急増などが関係しているそうです。
取材班はいろいろな人にインタビューしています。
いろいろと思うところはあったのですが、その中で一番印象に残ったのが、元銀行員の男性です。
彼は銀行退職後、小平市の老人ホームに入居しました。
彼は叔父に紹介された女性と結婚したのですが、仕事優先の生活を送ったため、妻と子から愛想を尽かされ、別居。その後離婚し、子どもにも会っていないし、親戚とも疎遠になっています。
銀行に勤めていたためお金はあるのですが、結局一人暮らしはせず、老人ホームに入るという決断をしたのです。
銀行生活で得られたことは、「経済的には問題のない生活」と彼は言っています。お金があるだけまだましなのでしょうが、彼の生活は寂しそうです。
「家族より会社を優先して生きてきた人たち。家族のつながりを失くし、会社のつながりを失った時、無縁化してしまう」
家族のためと仕事優先に働いている人には身につまされるでしょうね。
私なんかは、ある程度の人とのつながりは欲しいけれど、昔の血縁関係や地域社会のような濃い関係は避けたいという気持ちが強いです。私のように思う人は多いんじゃないでしょうか。こういう時代にどういう人間関係の構築がふさわしいのか、考えてみる価値はありそうです。
私は子もなく、夫だけ。どちらかが死ねば無縁かな。
夫よりも早く死ななくては、などと不謹慎なことを考えてます。
あ、葬式しなくていいから直葬で、遺灰は海に撒いてほしいな。
こう思うのも、まだ死が遠くにあるからなのかもしれませんね。
いろいろと考えるところはありますが、疲れているので、頭がまわっていません。
TV番組はどうだったのでしょう?
タナ・フレンチ 『道化の館』 ― 2011/03/10
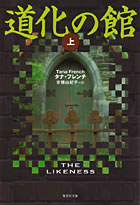
アイルランドを舞台にしたミステリーです。
『悪意の森』で刑事ロブの相棒として出てきたキャシー(カサンドラ)・マドックスが今回の主役です。
彼女はその後、殺人課から潜入捜査課へ移り、そこでレクシー(アレクサンドラ)・マディソンとなり、麻薬捜査のために潜入捜査をしました。しかし、潜入捜査は失敗。今はアイルランド警察DV対策課で働いています。
ダブリン郊外にあるグレンスキー村の廃屋でレクシー・マディソンという女性が死んでいました。
彼女は何者かに刺されており、妊娠初期でした。
彼女は「ホワイトソーン館」に同じ大学に通っている4人の友人たちと暮らしていました。
4人の友人の一人、ダニエルはグレンスキー一帯を支配してきたマーチ家の末裔で、「ホワイトソーン館」の持ち主。ジャスティンは弁護士の息子。レイフは投資銀行家の息子。アビーは孤児院育ちの女性。
5人は他の学生たちとは違う、5人の世界を形作り、その中で暮らしていました。
潜入捜査のためにでっちあげた人格のレクシーが生きていたということで、キャシーはこの事件を自分の手で解決したいと思います。
そのため、潜入捜査課時代の上司フランクが、ふたたびレクシーとなり、「ホワイトソーン館」に潜入することを提案すると、キャシーは恋人の殺人課刑事サムの反対を知りながらも、引き受けてしまったのです。
上手くレクシーを装い、「ホワイトソーン館」に潜入しますが、やがてキャシーは5人の生活に不思議なほど馴染んでいく自分を感じていきます。
本の大部分がレクシーになることを躊躇しながらも受け入れていくキャシーの心模様と、「ホワイトソーン館」でレクシーになり、だんだんと仲間と一体感を持つようになるキャシーの様子で費やされています。
5人の生活を語る場面が美しくせつないです。
人とコミュニケーションが上手く取れない人たちが仲間になり、その中で自分らしく生きていこうとする。そして、その絆をいつまでも持続させようとする。
誰でも居場所は欲しいものね。
でも、人との関係は時とともに移ろいゆくもの。
ミステリーとしてよりも、若者の自分探しの話として読むといいかもしれませんね。
広瀬 隆 『東京に原発を!』 ― 2011/03/13

大学時代に友人に勧められ、この本を読みました。
読んだ後、いつ原発事故が起こっても不思議はないことを知り、しばらく眠れませんでした。
スリーマイル島、チェルノブイリ、そして日本では東海村臨界事故などが起こったのですが、いつしか私たちの中の原発に対する危機感が薄れていました。
そして、今、恐れていたことが起こっています。
読んだ後、いつ原発事故が起こっても不思議はないことを知り、しばらく眠れませんでした。
スリーマイル島、チェルノブイリ、そして日本では東海村臨界事故などが起こったのですが、いつしか私たちの中の原発に対する危機感が薄れていました。
そして、今、恐れていたことが起こっています。
佐藤 正午 『Y』 ― 2011/03/15
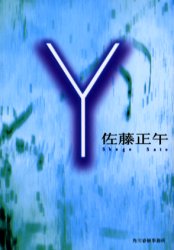
「再び訪れる一九九八年の夏。
アイリス・アウトで視界が黒く塗りつぶされる瞬間。アイリス・インで過去へと引き戻される瞬間。それを待って、僕は三たび生き直し、きみたちをこの手に取り戻すことができるかもしれない。」
知らない男からの電話。
彼は自分は高校時代の同級生で親友だったと言う。
彼が託したフロッピーには奇妙な物語が書かれていた。
彼はもう一度時間を戻り、あの瞬間を変えたいと言う。
人は誰でも、あの時というものを持っている。
あの時、あの瞬間をもう一度生き、変えられたら、と思う。
私たちにとって、その時は・・・。
未来への言葉 ― 2011/03/16

しばらく前に読んだ『失われた物語を求めて』を書いたレイチェルさんのことを思い出しました。
レイチェルさんは十五歳の時に、医師にクローン病で四十歳まで生きられないと言われました。彼女は医師の言葉に絶望しました。
「あのとき、たった一人の医師であってもいい。生きようという意志があれば、アスファルトを突き破って芽吹いた草の葉のように、クローン病という障害を打ち砕くことができるかもしれない、と励ましてくれたら、と今でも残念に思います・しかも、そうした力は自分自身の中に見つけられる、と言ってくれていたなら・・・」
私たちの未来は、今は暗く感じるかもしれない。けれど、彼女が十四歳の時にマンハッタンで見た「アスファルトを突き破って芽吹いた草の葉」のように、私たちの中に「アスファルトを突き破る」力があると信じて生きていけたら、未来は変わると思います。
レイチェルさんは十五歳の時に、医師にクローン病で四十歳まで生きられないと言われました。彼女は医師の言葉に絶望しました。
「あのとき、たった一人の医師であってもいい。生きようという意志があれば、アスファルトを突き破って芽吹いた草の葉のように、クローン病という障害を打ち砕くことができるかもしれない、と励ましてくれたら、と今でも残念に思います・しかも、そうした力は自分自身の中に見つけられる、と言ってくれていたなら・・・」
私たちの未来は、今は暗く感じるかもしれない。けれど、彼女が十四歳の時にマンハッタンで見た「アスファルトを突き破って芽吹いた草の葉」のように、私たちの中に「アスファルトを突き破る」力があると信じて生きていけたら、未来は変わると思います。
最近のコメント