近藤史恵 『山の上の家事学校』 ― 2024/04/22
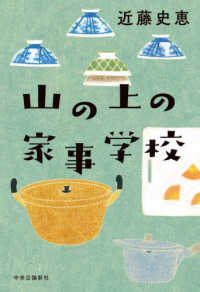
四十三歳、新聞記者の仲上幸彦は一年前に離婚してから荒んだ一人暮らしをしている。
妻は同業者だったが、娘が産まれてからはライターをしていた。
ある日、家に帰ると妻と子の荷物がなくなっていて、テーブルの上に離婚届とここ一年間の幸彦の行動レポートが置かれていた。
離婚してからできるだけ娘の側にいたいがために、幸彦は大阪支所に異動願いを出し、ほぼ本決まりとなっている。
異動のことを話しに幸彦が母親に会いに行くと、妹が家族を連れてやって来た。
彼女は幸彦にリフレッシュ休暇を利用して、大阪にある男性のための「山之上家事学校」に通ってはどうかと勧めてきた。
三月のはじめ、幸彦は大阪に行き、不動産会社で物件を探し、山之上家事学校の説明会に行った。
猿渡という青年と一緒に花村校長からの説明を聞き、きていた生徒に紹介された。
幸彦は山之上家事学校の寮に入り、とりあえず二週間、授業を受けることにする。
カリキュラムは洗濯と調理実習などの必修の授業の他に自由選択として編み物や育児研修、消火活動、子供のヘアアレンジなどがあり、意外に幅が広い。
家事学校で家事を学んでいくうちに、幸彦は日々の暮らしについて考えさせられると共に離婚前の自分がどうしようもなくダメな奴だったことに気づかされる。
調理実習でポテトサラダを作る場面があり、そういえばポテサラ論争があったなぁと思い出しました。
何も家事をしてこなかった高齢男性にとって、料理を作ることなんかたいしたことじゃないと思っていたり、女性ならそれぐらい作るのが当たり前と思っているのでしょうね。
幸彦もそうでした。
花村校長はこう言っています。
「家事とは、やらなければ生活の質が下がったり、健康状態や社会生活に少しずつ問題が出たりするのに、賃金が発生しない仕事、すべてのことを言います。多くが自分自身や、家族が快適で健康に生きるための手助けをすることで、しかし、賃金の発生する労働と比べて、軽視されやすい傾向があります」
気づいた幸彦はこう思います。
「ぼくたちは、家事と愛情を結びつけたくなるし、ケアをしてもらえることが愛情だと思ってしまいがちだけど、それはもしかしたら違うんじゃないかなって」
「ケアと愛情を結びつけるなら、自分もちゃんと相手をケアするべきなのだ」
覚醒した幸彦でしたが、それでも彼は元妻の苦しみを理解できませんでした。
花村校長はこう言います。
「わたしは、家事をやることに男性も女性も関係ないと思っています。それでも社会から押しつけられる圧力は全然違う。そこは認めないと公正ではありませんね」
まだまだジェンダー平等までには遠い道のりです。
でも、少しでも幸彦のように覚醒する人が増えていくと、少しは生きやすい世の中になっていくかもしれません。
是非、男性の方に読んでいただきたい本です。
読んだ文庫本 ― 2024/04/19

次々と花が咲いてきました。藤の花が美しいです。

サマーカットにしたので、日焼けがしないか心配です。
特に弟は背中の皮膚が透けて見えるです。
夏用のタンクトップを着せて散歩しようかしら。

「ママ、変な洋服着せないで下さいね」というように、ママの顔を見る兄です。
文庫本が溜まってきたので、三冊一篇に紹介します。

小路幸也 『花咲小路二丁目の寫眞館』
桂樹里は三代続いている写真館、<久坂寫眞館>で働くことになる。
社長は身長180センチを超える、細マッチョな久坂重。あとは彼の母親の聖子がいるだけだ。
一週間前に父親が亡くなったので、急遽重が北海道から戻り、写真館を継ぐことになったらしいが、重は自分では人間の写真を撮らない。幽霊のようなものが写ってしまうからだという。
試しに樹里の写真を撮ってみると、歩いて移動している男性が写っていた。
今度は動画を撮ってみようとすると、急に停電になる。
気づくと二人は三十年前にタイムトラベルをしていた。
困った二人はドネィタス・ウィリアム・スティブンソンこと矢車聖人、すなわちセイさんに助けを求めることにする。
写真館を出ようとすると、重の父親宛への手紙が置いてあった。
手紙の書き手は菅野好美で、樹里の母親だった。
それは別れの手紙で、二人は何があったのか確かめるために好美のところに行こうとすると、運よく駅の発売機のところに好美がいた。
早速彼女に理由を聞くと、騙されて、<久坂寫眞館>の土地と権利書を取られたという。
これはセイさんに頼むしかない。
二人は手紙を書いて、セイさんを公園に呼び出すことにする。
花咲小路シリーズの七作目です。
花咲小路は何丁目まであるのか知りませんが、これまでの題名から四丁目まであるのはわかりました。
今回とうとうタイムトラベルしちゃいましたwww。
内山純 『魔女たちのアフタヌーンティー』
前屋敷真希は都内大手の不動産会社の開発部に勤めているが、先月、とんでもない失態をやらかしてしまった。このままでいると左遷されるので、白金七丁目の”プラチナの魔女”が住むという屋敷の土地を手に入れ、汚名返上しようと目論む。
運が味方したのか、ひょんなことから出会った少女みのりに魔女の屋敷のお茶会に誘われる。
美味しいお茶と手作りのお菓子に癒やされる真希。
それからお茶会に来る様々な年代の人と交わるうちに、いつしか真希はお茶会が楽しみになっていく。
アフタヌーンティーという題名につられて読んでしまいました。
忙しい日常にホッと一息できるお茶の時間を持つといいかもしれませんね。
スーさんのような女主人が催すお茶会ならもっといいです。招かれてみたいです。
午鳥志季 『君は医者になれない2 膠原病内科医・漆腹光莉と鳥かごの少女』
戸島光一郎は波場都大学医学部三年生になったが、血を見ると、相変わらず気持ちが悪くなる。
指導医は変わらず、コーヒーとジャンクフード好きで、身の周りの整理のできない社会不適合な膠原病内科医の漆原光莉だ。
「第一章 去りゆく人・高木セツの追憶」
誤嚥性肺炎で救急外来に運ばれてきた八十歳、全身性強皮症の高木セツは戸島の採血の練習台となってくれ、「逃げちゃダメよ」と励ましてくれた。
彼女のために戸島、走ります。
「第二章 新人看護師・幹元華の秘密」
漆原先生が珍しく飲み会に参加するが、ジャージを着てくる。その上、鞄から取り出したのが、カップラーメンと魔法瓶の水筒。やっぱり変人だぁ、笑。
幹元が何気なく、心因性で月に一回微熱が出て、体がだるくて、動きたくなくて、急に仕事を休み、前の病院を首になったことを話すと、漆腹がポツリと「心因性かな?」と言葉を吐く。漆原は何に気づいたのか。
「第三章 膠原病患者の母・山波泉の悔い」
十七歳の『抗リン脂質抗体症候群』の女の子、山波瑞羽が他の大学病院からの紹介でやって来る。
母親の泉は単刀直入に漆原に「治せるか」と聞く。もちろん漆原は「治せない」と答える。どうも母親は娘の病気を受け入れられていないようだ。
ある日、戸島は困っていた瑞羽を助け、それから話すようになり、本まで借りるようになる。
しばらく瑞羽は漆原のところに来ていたが、泉が埼玉の病院への紹介状を書いてくれと言い出す。
仕方ないという漆原だったが、瑞羽の採血を確認すると…。
「第四章 車椅子の少女・山波瑞羽の願い」
山波瑞羽は「劇症型・抗リン脂質抗体症候群」の可能性があり緊急入院する。
しかし、瑞羽は死にたいといい、治療を拒否する。
漆原は治療を望まないなら、その意思を尊重すると言う。
「……逃げるな」
戸島、瑞羽を救うために立ち上がる。
戸島君がだんだんとたくましく医師として成長していく姿が頼もしいです。
血が怖くたって、内科医になれば問題ないしね。
彼のような医師の方が患者の立場に立って考えてくれそうですよね。
膠原病ってあまり一般的ではないので、よくわかりませんが、この本を読むと少しわかってきました。
瑞羽ちゃんみたいになると、親も子も大変だなと思いますが、戸島君同様、どこまで気持ちが分かるか、自信がありませんわ。
イチオシは「君は医者になれない」シリーズです。
漆原先生の変人さが気に入りましたwww。
原田ひ香 『定食屋「雑」』 ― 2024/04/18

三上沙也加は突然夫の健太郎から離婚を言い渡された。
夫は仕事のストレスからか、仕事の帰りに公園で酒を飲み始め、そこが禁じられると、近所の定食屋「雑」で定食を食べ、酒を飲むようになって、家ではご飯を食べず、帰りが遅くなっていた。
沙也加は夫のために三食、健康的な手料理を作ってきた。
夫にはご飯はご飯として食べ、その後にナッツとかチーズとかで酒を飲んで欲しかったのだ。
夫は沙也加には俺の気持ちはわからないと言い、家から出て行った。
沙也加は夫が行っていた定食屋「雑」に行ってみた。
店主は七十代の背の低い、樽のような体形の、やる気のなさそうな女性だ。
出てきた生姜焼きは甘い、お菓子のように甘い。肉じゃがも甘い。
ただ、スパゲッティサラダが絶妙だった。
夫は本当にこの店が好きなのだろうか、それとも…。
そうこうしているうちに、お金が心配になる。
派遣会社に常勤で働きたいとお願いしたが、すぐに探せないと言われ、どうしようかと思っていたら、定食屋「雑」の店員急募の張り紙を見つける。
この店で夫が女と出会って浮気をしていたかどうか調べられるし、お金も稼げる。
一石二鳥と考えて、沙也加は働いてみることにする。
女店主・雑色みさえはぞうさんと呼ばれている。
ぞうさんの大雑把さには驚かされたが、やがて二人は信頼し合える仲になっていく。
頑なだった沙也加だったが、定食屋「雑」で働くうちにだんだんと心がほぐれていき、自分の行く末も考えられるようになる。
やがてコロナ禍になり、定食屋「雑」も形態を変えざる得なくなる。
ほとんどがすき焼きのタレの味付けという、おそろしい定食屋「雑」。
でもコロッケは美味しそう。
家庭で作るコロッケってジャガイモの味が濃くて、いいんですよね。
自分では作らないけど、食べたいわ。
から揚げも醤油だけで味付けしているけど、衣がカリカリで中がジューシー。
う~ん、食べたい。
どんなに美味しいフランス料理やイタリア料理を食べても、最後はこういう何の変哲もないお料理に戻りますよね。
原田さん、料理の描き方がホントに上手いです。
それにしても沙也加の旦那はクズ男です。
最初は沙也加のせいかとも思ったのですが、後で離婚の話をする時のことなど読むと、もともと大した男じゃなかったことがわかります。
沙也加も男を見る目がなかったのね。
離婚をいい肥やしとして、これから前向きに、ぞうさんと仲良く、生きていって欲しいです。
お腹が空いている時に読むと、お腹が鳴ってしまうかもしれないので、くれぐれも気をつけてくださいませ、笑。
<この頃のわんこ>

ヨーキーの弟の毛の色が変わりました。
シニア(9歳よ)なので、毛が白くなっていたのですが、見て下さい。
黒くなっています。
ヨーキーの毛の色はいくつまで変わっていくのでしょうかね。
彼は音の出るおもちゃを咥えるとなかなか離しません。
ほっておくと離しますが、片付けようとしておもちゃを拾おうとすると、すぐに咥えます。
遊びだと思っているのでしょうかね。
中島京子 『うらはぐさ風土記』 ― 2024/04/07

田ノ岡沙希は30年ぶりに日本に帰って来た。
カリフォルニア州の私立大学で日本語を教えていたが、日本語科が閉鎖されてしまった上に夫のバートの浮気がわかり、どうしようかと思っていた時に、母校の女子大から二年間の仕事のオファーが来たのだ。
とりあえず武蔵野の一角のうらはぐさ地区にある伯父の家に住ませてもらい、母校に通勤することにする。
そこで出会ったのが、伯父の家の庭の手入れを無料でしてくれている秋葉原さんとその妻の刺し子姫、不思議な敬語を使う、国際文化研究科一年生の亀田マサミことマーシーと彼女の友だちで人文科学研究科の水原鳩ことパティ、大学の同僚で日本近現代史専攻の非常勤講師、来栖先生とパートナーでリサーチ会社を経営している猿渡くん、あけび野第三小学校の校長、車谷武蔵など、多彩な人たちだ。
沙希はうらはぐさ地区に暮らすうちに、あけび野商店街のところに、道路拡張計画があることを知る。
商店街がなくなるのかと不安に思う沙希。
そこに元夫のバートが現れる。
コロナ禍を沙希がこう思っています。
「あんがい、コロナというのは、呼吸器官にはりついて肺炎を引き起こすばかりではなく、どこか人の弱い部分や無意識の部分に入り込んでその本質を露呈させるような、奇妙なウィルスだったりするのだろうか」
淡々とした日常が描かれ、これと言った出来事はないけれど、そこに生きる人たちがとても愛おしく思えるお話です。
武蔵野にある女子大と言うと、あそこかと思って中島さんの経歴を見ると、そうでした。商店街というとたぶん、あそこね。
そこがこのお話のようなところであるとは思いませんが、なんとなくそうあってもいいなぁと思えます。
武蔵野を知っていると、より面白く読むことができるでしょう。
別に知らなくてもいいんですけど、笑。
<今週のおやつ>

La nature Kのクッキー缶です。
胃の具合があまりよくないので、あまり食べられません。(食べるのかよ・笑)
無添加、白砂糖不使用と、材料を吟味しているらしいです。
チョコチップ、サブレココ、ガレット、ごまサブレの4種類です。
きび糖は意外と甘いんですね。
ここのプリンが美味しいというので、いつか食べに行きたいと思います。
読んだ文庫本&漫画 ― 2024/02/17

<読んだ文庫本>
中山裕次郎 『外科医、島へ 泣くな研修医6』
三十一歳になった雨野隆治は医者になってもうすぐ七年になる、駆け出し外科医。
四月から半年間の予定で神仙島へ派遣されることになる。
神仙診療所には医師は所長の瀬戸山と雨野の二人、看護師は半田志真と繁田秀子の二人がいる。
島では今までとは違い、あらゆる病気を診なければならず、技量のなさを思い知らされる毎日だが、雨野は瀬戸山や志真たちの助けを借り、なんとかやっていく。
三十年以上もこの診療所で働いている瀬戸山。
彼が人生をかけて築いてきた医療体制と守ってきた島民の命、そして、諦めてきたいくつもの命がある。
あらゆる診療科の、あらゆる疾患を診て、全ての責任を負う瀬戸山の姿は、雨野には本当の医者の姿に思えた。
雨野は瀬戸山みたいな医者になりたいと思う。
人として、医者として、一回り大きくなった雨野くんです。
Dr.コトーを思い出しますが、雨野くんは島に残らず帰ってしまったのが残念でした。
喜多みどり 『弁当屋さんのおもてなし 巡り逢う北の大地と爽やか子メロン』
第一話 氷雪の下の幸を揚げる
第一話 氷雪の下の幸を揚げる
札幌の弁当屋くま弁を夫婦で経営するユウと千春は、一泊二日でサロマ湖畔へ旅行に行く。宿泊した民宿はくま弁のお客だった華田将平が働くところだ。
宿で食事をしていると、将平が一人の女の子のことを気にしている様子がうかがえた。彼女は食事にあまり手をつけていないのだ。
次の日、将平と待ち合わせをしていたのに、将平が現れない。
将平はユウたちに食べさせる昼食の下見に出かけたらしいが…。
第二話 夕張小旅行とテッカメロン弁当
ドラマやバラエティで人気の有名人になった黒川茜がくま弁に現れる。一人の女性に後を付けられているという。その女性がくま弁の中にまで入ってきて、茜を探しているようだ。千春が声をかけると、店を出て行った。彼女は夕張市で開催されている映画祭のフライヤーを落としていく。
彼女のことに見覚えがあるような気がするという茜は、実際に夕張に行ってみると言い出す。
千春は明日はくま弁が休みの日なので、業務用バンで夕張まで行くことを提案する。
第三話 イカタコパーティーセット
お土産のイカとタコがあるので、ユウたちは休日に気心知れた友人たちを招いて食事会を開く。どんな料理がいいか訊くが、なかなか意見が合わない。ユウはあきれて厨房へ行ってしまう。
いつもユウに料理を作らせていると気づいたみんなはそれぞれタコとイカを使った料理を作ることにする。
第四話 冬の怪談と北海道巡り弁当
くま弁の近くのパティスリー・ミツで幽霊が出たという噂が…。
幽霊と間違えられたのはパティスリー・ミツのファンの梨之木という女性だった。
彼女は旅行に行けないので、道内で小旅行をした気分になれるお弁当を作って欲しいとユウに頼む。
ユウが作った弁当は…。
このシリーズは時が行ったり来たりします。
今回はユウと千春が籍をいれて数ヶ月の新婚の時のお話です。
お弁当で美味しいと思ったことはあまりありませんが、くま弁のなら食べてみたいです。
財政破綻した頃の夕張に行ったことがありますが、ゴーストタウンみたいでした。今はどうなんでしょう。メロンの食べ放題があるようですね。食べたいわぁ。
<読んだまんが>
大島弓子 『サバの秋の夜長』&『サバの夏が来た』
なんと猫が人間の姿で同じ大きさをしています。猫だけではなく、ノミやカラスなどの動物がみな人間の姿です。面白いですねぇ。
でも、このスタイルは続けず、猫は猫になりましたね。
漫画マキヒロチ 原案まろ(おひとりさま。)『おひとりさまホテル 1~3』
わたし、ホテルが大好きです。いろいろなホテルに泊まりに行きたいのですが、この頃ものすごく高くなっています。インバウンドのせいですね。
海外の旅行者価格と国内の旅行者価格の二つにしてくださいませんかね。
続々と新しいホテルができているようで、この漫画に出てくるホテルにいつか泊まりに行きたいと思っています。
柚月裕子 『風に立つ』 ― 2024/02/09
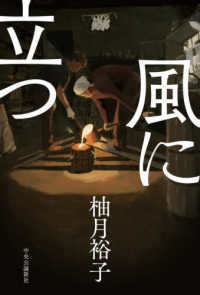
小原悟は困惑していた。
父の孝雄が補導委託を申し出たというのだ。
補導委託とは、「家庭裁判所が少年の最終的な処分を決める前に、民間のボランティアの方に非行のあった少年をしばらくの間預け、少年に仕事や通学をさせながら、生活指導を行い、更生への手助けを行う制度」。
孝雄は岩手県盛岡市にある南部鉄器工房『清嘉』の親方で、職人は悟と健司、研磨専門のアルバイトひとりだ。
悟は補導委託に反対だったが、健司と昨年結婚して家を出ている妹の由美は賛成していて、悟の話を聞こうともしない。
一ヶ月後、仙台家庭裁判所の調査官である飯島久子が預かる少年の庄司春斗と父親の達也、母親の緑を連れて来た。
春斗は16歳。彼の非行が始まったのは高校に入学してからで、万引きや自転車の窃盗などの問題行動が収まらなかったので、高校は退学処分となった。
父親は仙台市で弁護士事務所を構えており、母親は専業主婦だという。
悟は春斗にはできる限りかかわらないと決めていたが、彼の両親を見て、自分の先入観に気づく。
非行少年というだけで、親のネグレクトや貧困などの家庭環境が悪いのではないのだ。
それにしても何故孝雄は補導委託を申し出たのか。
自分の子供には手をかけなかったのに、どうして他人の子供の面倒を見る気になったのか。
孝雄は家族に対してはいつもぶっきらぼうで、態度も冷たかった。
それなのに、春斗には口調が穏やかで、態度も優しい。
いったいどうしたというのだ。
春斗と工房で働き、同じ屋根の下で暮らすうちに、悟の気持ちはだんだんと変化していくが…。
今回出てくる父親は二人とも不器用で、思いが子供に届いていません。
子供には親の気持ちが、近すぎて見えていなかったり、子供の気持ちを考えずに強制しようとするので、子供の負担になっていたり…。
最後は上手くいってよかったのですが、実際にはこんなに上手く行くことなんて、滅多にないだろうと思います。
親との関係に悩んでいる人は悟に共感できるかもしれません。
心暖まるお話を読みたい人にはピッタリの本でしょう。
でも、ゴメンナサイ。
柚月さんのファンの方には物足りないでしょうね。
わたし、何も意外性がなく、みんないい人というお話が読みたいとは思いません。
残念ながら、この本はわたしが望む柚月さんの本ではなかったです。
<今日のわんこ>

この頃、兄はよく寝ます。
今年で12歳。人間で64歳ですから、立派なシニア犬です。
食い意地だけは、ママと同じで、あります、笑。
砥上裕將 『一線の湖』 ― 2024/02/02
『線は、僕を描く』の続編。

両親が亡くなり、ひとりぼっちになった青山霜介は、叔父の助言により大学へ進学し、水墨画の巨匠、篠田湖山に出会い、水墨画の世界に魅了され、彼の内弟子となる。
湖山の孫、千瑛と湖山賞を競ったが、湖山賞を取ったのは千瑛だった。
それから二年が経ち大学三年となった霜介は未だ自分の進路を決められずにいた。
一方、千瑛は「水墨画界の若き至宝」と呼ばれ、もてはやされていた。
そんな時に、霜介は揮毫会で失敗してしまう。
湖山は霜介に少しの間、筆を置くようにいう。
そんなある日、兄弟子の西濱湖峰に呼び出される。
小学一年生に水墨画を教えるのを手伝って欲しいというのだ。
霜介が訪れた小学校は、亡き母が勤務していた学校で、担任の椎葉朋美は母と親しくしていたらしく、母の死後、彼女のクラスを引継いだという。
体調不良の西濱の代わりに霜介は児童たちに水墨画を教える羽目になる。
しかし、その授業が好評で、学校から引き続き霜介に水墨画を教えて貰いたいと請われる。
霜介は子どもたちに最善のものを伝えられればと思って引き受ける。
子どもたちと接するうちに霜介は思う。
「本当によい授業というのはこういうものかもしれない。彼らが自身で学ぶことに勝るものはない。教えたいという欲求を堪えることのほうが、教えることよりも難しい」
「彼らはありのままを生きているから、生きていることが描けるのだ。そのすべては線の中にあった。彼らが指先から生み出すものが、彼らの存在と違わない。
彼らは自然だった。心を遊ばせ、無限に変化し続けるゆらめきがそこにあった」
そして、霜介は母親の仕事を理解していく。
「母は自分が生きた一瞬や自分自身のために、力を尽くしていたのではない。人を育て、自分自身さえ見ることはないかもしれない遙かな未来に向けて、線を描いていたのだ」
「人は命よりも永く線を描くことができる」
小学校で一年生が描いた指墨画を展示し、その場で揮毫会を行うことになる。
その時の動画を誰かがアップし、話題となり、霜介は大学の理事長から大学学園祭で大揮毫会と展覧会を行うように頼まれる。
しかし、学園祭当日、子どもをかばった霜介は右手を骨折してしまう。
前から不調だった右手には感覚がなくなる。
湖山は霜介に自分の山荘に行くように勧める。
山荘に行った霜介は意外な人と再会する。
始めは二年前と同じように自分に自信がなく、同じ所をグルグル回っているだけのような霜助に、わたしはちょっと失望しました。
しかし、湖山先生は流石です。霜介の才能を惜しいと思っているのでしょう。
霜介を見捨てず、こう言います。
「描こうなんて思うな」「完璧なものに用はない」
「あと一歩だけだ。そこに線がある」
霜介は子どもたちから教えられ、そして、山荘に行き、自然と接するうちに、悟っていきます。
「生きるとは、やってみる、ことなんだ」
霜介はやっと一歩前に進むことが出来、自分の進むべき道を決められたのです。
時間がかかりましたが、回り道は彼にとって必要だったのでしょうね。
その道がどんなものであろうと、彼の家族である湖山会の人たちは受け入れてくれます。
わたしも彼の進む道が予想通りで、納得がいきました。
とにかく最後の湖山の引退式の揮毫会の場面が圧巻です。
絵が目の前で描かれているように、見えるのです。
どんな感じで水墨画を描くか、講談社が動画を載せていました。
ついでに前作の映画の予告編も載せておきます。
「線は、僕を描く」の予告編
映画は観ていませんが、予告編を見ると、登場人物たちがわたしがイメージしたのと違います。流星君は悪くないですが、これは観ないな。
本はとてもいいので、是非お読み下さい。
秋川滝美 『ひとり旅日和 幸来る!』 ― 2024/01/30
太田愛さんの『未明の砦』が大藪春彦賞を受賞したそうです。
おめでとうございます。
とてもいい作品だと思いますので、興味のある方は是非読んでみてください。

『ひとり旅日和』も五作目になり、梶倉日和(ひより)ちゃんは28歳になりました。
今回は日和ちゃんが行った観光地を載せておきます。
というのも、今まで載せていなかったので、後からどこに行ったのか調べられなかったからです。
本を見直せばいいのでしょうが、図書館で借りているので、思い立ったらすぐにみられないのです。
第一話:能登
本を開いてびっくりしました。
日和ちゃんが最初に行ったのが、能登だったのです。
読んで驚きました。
この本は昨年の11月発売ですから、秋川さんは何気なく書いたのでしょうが。
「新しく造られるものがある一方で、景勝地が天災に見舞われて美しさを失うこともあるだろう」
この言葉そのもののことが起ってしまいましたね…。
一日目。
のと里山空港→のとじま水族館→海づりセンター→輪島
『のとじま水族館』はジンベイザメを飼育している水族館で、日和は日本全国のジンベイザメを飼育している水族館を制覇。
ちなみにジンベイザメがいるのは大阪の『海遊館』と沖縄の『美ら海水族館』、鹿児島の『いおワールドかごしま水族館』だそうです。
水族館前の食堂街でランチの刺身定食を平らげ、『海づりセンター』に行くと、断れなくて拉致され、釣りをする羽目になるが、1回でギブアップ。自分には向いていないと、餌を子どもにあげてしまうのには笑ってしまいました。
輪島の被害状況はニュースなどで伝えられているので、ここには載せません。
二日目。
朝市(ノドグロのひものとえがらまんじゅうを購入)→重蔵神社→輪島キリコ会館→輪島塗会館→白米千枚田→イカの駅つくモール
輪島塗会館は当面の間臨時休館だそうです。輪島塗業界復興のための募金を受け付けています。こちらをご覧下さい。
第二話:妙高
日和、仕事でありえない失敗をする。申し訳なくて休日返上したいが、みんなに気分を切り替えるために行ってこいと言われ、東北新幹線に乗る。
一日目。
春日山駅→上越埋蔵文化財センター(春日山城跡の「御城印」をゲット)→(春日山城跡)→春日山神社→高田駅→高田城三重櫓→雁木通り
知らなかったのですが、刺身盛り合わせの食べ方があるそうです。
左前から右、淡泊な白身から食べるということです。
第三話:村上・新潟
第二話からの続きです。
二日目。
強風のため笹川流れは中止。そのためまっすぐ新潟駅に行く。
高田駅→新潟駅ぽんしゅ館→村上駅→町屋通り→おしゃぎり会館
三日目。
村上駅→笹川流れ遊覧船→新潟駅ぽんしゅ館
ぽんしゅ館では新潟の酒の利き酒ができるようです。酒好きなら外せませんね。
でも、お酒の飲めないわたしには豚に真珠ですわwww。
酒飲みの梶倉家なので、お菓子のお土産が少なくて、残念です。
第四話:山口
日和の思い人、蓮斗が九州に転勤になるという。
たまに連絡を取るのだが、蓮斗は日和に何も言わない。
わたしは蓮斗にとって、それぐらいの人なのね。
このまま連絡が途絶えるのかと落ち込む日和は傷心旅行で山口に行くことにする。
一日目。
秋吉台(秋芳洞)→別府弁天池→松蔭神社→萩
二日目:
『はい!からっと横丁』は名前からは想像できませんが、遊園地だったそうで、昨年の10月で営業終了してしまったそうです。
三日目。
唐戸市場で寿司を食べる→秋吉台(秋芳洞)再チャレンジ
秋吉台の秋芳洞には大学生の時に行きました。
その時はワンゲル部で隠岐の島に行った帰りに、友人と二人でリュックを担ぎ、鳥取砂丘や松江、出雲、萩、津和野、秋吉台、京都などを回って帰って来ました。
若くて体力があったのね。
日和ちゃんは秋芳洞が暗くて怖くなり、途中で引き返してしまいましたが、そんなに暗かったかしら?
わたしたちは雨水が溜まっていた所を知り合いになった大学生たちといっしょに通ろうとしましたが、頭まで水に浸かりそうだったので、途中で引き返したのは覚えています。
今はもっと観光地化して、歩きやすくなっていると思うのですが。
まあ、得手不得手は人それぞれですからね。
でも日和ちゃんにはいいことがあって、羨ましいです。
このシリーズ、これで終わりでもいいぐらいです。
どこに行ったかは書きましたが、書かれていないことがいっぱいありますから、日和ちゃんの行く末を知りたかったら、是非読んでみてください。
最後に、被災地が一日も早く復旧・復興して、再び多くの観光客が能登を訪れることを心より願っています。
人生、いろいろありますという本(文庫本) ― 2024/01/18
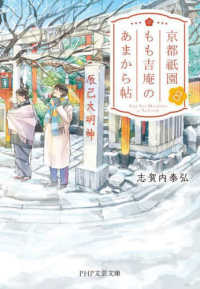
もも吉は京都祇園の元芸妓で一見さんお断りの甘味処「もも吉庵」を営んでいる。
メニューは四季おりおりの麩もちぜんざいだけ。
「もも吉庵」に今日も悩みを抱えた人たちが相談に来る。
「第一話 幸せの四つ葉探して京の春」
昼は個人タクシードライバー、夜は祇園甲部の芸妓という美都子が幼馴染みの建仁寺の塔頭・満福院副住職の隠善と甘いもんを食べにいった帰りに、駐車しておいた美都子のタクシーに無理矢理乗り込んできた女性とその旦那、そして幼いこども。
女性は切羽詰まった感じで、何か緊急事態かと思った美都子は彼らを乗せると、彼女は「前のタクシーを追ってください」という。どういうこと?
「第二話 空豆に商う心教えられ」
京大出身の皆川遙風は第一志望のメガバンクから内定をもらっていたが、銀行が経営破綻したため採用の取り消しになる。就活戦線は既に終盤を迎えており、ゼミの教授の勧めに応じて京都に本社のある京洛信用金庫に就職した。ゼミの同期は日本を代表する大手の銀行や保険会社に勤めているのに、自分はここで燻ったままで一生を終えるのかと思うと苛立ちを覚えてしまう。
そんな時にやっと融資の仕事ができるようになるが、遙風は最初の融資に失敗してしまう。支店長は案内係の朝倉に与信審査の方法を遙風に教えてやってくれと頼む。すると朝倉は遙風を京麩の半兵衛麩へと連れて行く。
「第三話 祇園会の会議は踊るおもてなし」
「風神堂」の斉藤朱音と若王子美紗は「祇園祭黒子会」の会議の幹事を任される。
「祇園祭黒子会」とは、祇園祭の裏側で、黒子のように見えないところで働く有志の集まりだ。第一回会議が開かれ、会議は紛糾し、議長を務めた明智夢遊は困ってしまう。というのも力になってくれると言っていた庭師の山科仁斎がことの発端になったのだ。朱音は夢遊のために、場を和ませようと策を巡らせる。
「第四話 おむすびに込めた愛あり萩ゆる」
渡辺真凜は困っていた。小学一年の娘、彩矢が遠足におむすびを持って行きたいと言い張るのだ。真凜にとっておむすびはトラウマで、作ることも食べることもできない。
そんな頃、父が昔いっしょに暮らしたことのある陶子に指輪を渡して欲しいと言って亡くなる。陶子こそトラウマを引き起こした張本人。ためらいながらも真凜は父のスマホに入っていたもも吉の電話番号に電話をし、陶子の居場所を訊くが…。
「第五話 京セリは雪解けを待ち耐えて生き」
元芸妓、もも雛こと陽向とゲーム会社、サンガエンペラーの社長をしている夫の内山爽馬は苦境に立たされていた。
常務の谷川が会社の金を私的流用し、無謀な投機をしたため、巨額な損失を被り、二度の不渡りを出していた。その上、内山が命令したという告発文のようなものを谷川がネット上にアップしたのだ。
自暴自棄になった内山にもも吉は自分の辛い過去を話す。
人の悩みは様々。そんな人たちにもも吉はそっと寄り添い、的確なアドバイスを施します。
第一話では自分の心次第で物事の見方が変わることを教えてくれます。
第二話には商いをする時に役立つ教えが書かれています。
第三話では朱音がまたまた活躍してくれます。わたしとしては夢遊さんの気持ちに応えて欲しいな。
第四話では陶子の隠された思いが明らかになります。
第五話は涙なくして読めません(たぶん)。
もも吉が世の中のままならぬことを、『出会いもん』として考え、生きてきたのです。そんな彼女だからこそ、沢山の人たちにいいアドバイスができるのでしょう。
最後に食いしん坊の隠源住職の言葉を書いておきます。
「まず自分が幸せにならんと、他人を幸せにでけへんさかいなぁ」
巻末に京都の美味しいお店が載っていますので、ご参考に。

日本橋二十一屋通称「牡丹堂」で働く小萩は、小萩庵でお客の依頼に基づいたお菓子を考え、作っている。
「鹿の子の思い」
ある日、小萩庵に紺屋(染物屋)の十歳の娘、茜がやって来る。
彼女の店で働いている職人の岩蔵に、自分の父親になってもらいたいという願いを込めたお菓子を作って欲しいという。
小萩は彼女の母が得意だという鹿の子絞りにかけた鹿の子と、一見無骨で内側に軽やかで繊細なものをもつ岩蔵を表す練り羊羹の二つを作り、茜の書いた文を添え、岩蔵に持っていくが…。
「黒茶、花茶に合うお菓子は?」
二十一屋は西国の大名、山野辺藩の御用を賜っている。このほど新しい留守居役が着任することになり、顔合わせの場を持つこととなる。
しかし、その日は札差の箔笛の別邸で茶会がある。その茶会では清国のお茶を三種類出すという。そのためお茶に合うお菓子を三種類考え、作らなければならない。
その上、葬式饅頭百個も頼まれる。
顔合わせの当日、二十一屋は総勢七人で山野辺番の髪屋敷に行くが、途中で三人が抜け出す。
しかし、それが見つかり、新しい留守居役から咎められる。絶体絶命の危機。
「とびきりかたい、かりんとう」
小萩庵に国学者・学而の妻、お香とその娘のお花がやって来る。学而が煙草を吸いすぎるので、控えてもらうためのお菓子をお願いしたいという。
話し合いの結果、お菓子の他に謎をかけた和歌を添えることになる。
小萩がお菓子を届に行くと、文治郎という男がいて、禁煙に失敗した学而をからかう。そのため学而はへそを曲げてしまう。せっかくの妻と娘の心遣いがダメになってしまうのか?
「吉原芸者の紅羊羹」
小萩庵に吉原芸者の千代菊がやって来る。このたび二挺鼓の打ち手としてのお許しをいただいたので、自前芸者になるお披露目のお菓子を頼みたいのだという。
別の日、見世で饅頭を買い、ここで食べたいという若い娘が現れる。母が病気で長くないという手紙を出しても返事がない姉をたずねて、はるばる越後から来たという。姉は竜泉の百川で働いていると言うので、お萩は簡単な地図を描いて渡す。
翌日、千代菊のところにお菓子の見本を持って行くと、昨日の娘が現れる。なんと千代菊が彼女の姉だった。娘は米といい、母に顔を見せてやってくれと言うが、千代菊はお披露目があるし、お座敷がかかっているので帰れないと断るが、米は納得しない。その翌日、千代菊が残りの半金をもって来る。
はたしてお披露目はされるのか…。
出てくる和菓子がとても美味しそうで、食べたいです。
初めは頼りなかった小萩がだんだんと一人前になり、人の心がわかるようになってきて、いいお菓子を提案できるようになっています。
茜の言う、「あたしが考える幸せっていうのはさ、にこにこ笑って今日もいい日だったねってご飯を食べることだよ」には驚きました。若いのにわかってらっしゃる。
どの人も他の人の幸せを思った行動をとるのですが、それがうまくいかないのは、人生の機微ってものでしょうか。
最後の「吉原芸者の紅羊羹」には泣かされました。
そうそう茶会に出されるお茶は、「緑茶 碧螺春」と「茉莉花茶 福州白龍珠」、「黒茶 正山頂普洱茶王」です。
「緑茶 碧螺春」は中国十大銘茶の一つで、江蘇省蘇州市の洞庭山で生産される非発酵茶。香りは非常に濃厚で、ほのかに花果の香りがして、淹れた湯の色は青く住んでいて、味は濃厚で後味もいいそうです。
「茉莉花茶 福州白龍珠」はジャスミン茶のことです。
「黒茶 正山頂普洱茶王」はプーラール茶かな?癖があって、好き好きですよね。
これからも小萩庵に次はどんな訳アリお客が来て、どんなお菓子を作るのか、楽しみです。
二冊ともシリーズ物ですが、シリーズが進むにつれて面白くなっていっています。
仕事で頑張る若い女性のお話(文庫本) ― 2024/01/13
原発性アルドステロン症の診察で内分泌科に行ってきました。
年末、食べ過ぎたため、1~2㎏太り、中性脂肪が増えてしまい、主治医がめちゃ怖かったですww。
12月に健康診断をしたのですが、腎臓の機能を表すeGFRの値が若干低く、軽度の腎機能障害があるかもと指摘されていたので、そのことを言うと、今飲んでいる薬でそういうことが起るのだそうです。
薬を減らすとeGFRの値は高くなるけど、それでは血圧が上がってしまうので、仕方ないそうです。
知りませんでしたわ。
原発性アルドステロン症の方で腎臓の機能低下がある方、そういうことだそうですので、ご参考までに。
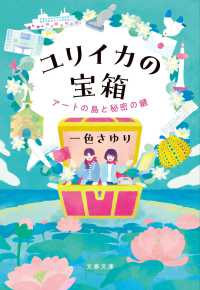
『ユリイカの宝箱 アートの島と秘密の鍵』 一色さゆり
桜野優彩は家の都合で高校を卒業してから画材店に就職した。しかし、画材店は半年前に店じまいをしてしまう。絶望感に襲われた優彩は、友人から仕事の誘いはあったが、その仕事は自分には無理なんじゃないか、本当に自分のやりたいことなのか考え始め、袋小路にはまってしまう。
そんな頃、梅村トラベルという見知らぬ旅行会社からアートの旅への招待状が届く。担当者の志比桐子に問い合わせてみると、新しくアートの旅行を企画する予定で、モニターとして参加し、サービスの感想や改善点についてのアンケートに答えるだけで、旅費のほとんどを負担してくれるのだとか。優彩は思い切って参加することにする。
行き先は「現代アートの聖地」、瀬戸内海に浮かぶ直島。
旅の終わりに優彩は桐子から一緒に働らかないかと誘われる。それだけでも驚きなのに、優彩と桐子は優彩が小学校の頃に会ったことがあるというのだ。
優彩は梅村トラベルで働くことにするが、桐子のことは思い出せない。
一方、桐子と巡るアートの旅は、人生に迷う人に寄り添い、前へ進もうと優しく誘ってくれるものだった。
一色さんは原田マハさんとは違った角度からアートを描いています。
この本では、アートは難しく考えることはない、自分自身と向き合うことだと教えてくれます。
アートは優彩に「自分の可能性を削っていたのは、他でもない自分自身」であり、「壁だと思い込んでいた境は、じつは、つぎの世界への入り口かもしれないのだ」と気づかせてくれました。
アートに関する印象に残った言葉をいくつか書いておきます。
「アート鑑賞って、基本的に誰にとっても、ユリイカの連続だと思うんです」
(注:「ユリイカ」とはギリシャ語の『わかった』)
「民藝では、美しいものは特別な人だけが生みだすものではなく、無名の職人の手仕事にも宿っているという考えがある」
「アートは決して、日常とかけ離れたものじゃない」
「アートって、自分の人生を見つめ直すきっかけをくれるから。道に迷ったときに光を照らしてくれる存在」
ちなみに彼女たちがお客様と訪ねた美術館は、直島の地中美術館、京都の河合寅次郎記念館、安曇野の碌山美術館、佐倉のDIC川村美術館です。
私は地中美術館とDIC川村美術館に行ったことがあります。どちらもお勧めです。
実はとても碌山美術館に行きたくなり、電車の時刻表を見たり、松本のホテルを探したりして、旅行日程を作ってしまいました。暖かくなったら、一泊二日の予定で行ってきますわ。
是非桐子たちとアートの旅へ行ってください。
『上毛化学工業メロン課』 奥乃桜子
瓜原はるのは上司、坂上の命を受け、『上毛高分子化学工業株式会社 赤城第二工場』に異動になる。工場は見渡す限り荒れた畑の中にある物置みたいな二つのプレハブ小屋で、入り口に『メロン課』と書いてある。まさかここ?なんとそこは問題社員を集めた「追い出し部屋」だったのだ。しかし、社長賞をとった、はるのの憧れの先輩で天才研究員と言われた南がいるはず。だが、南はパワハラ上司に逆らい左遷され、今や酒浸りだという。彼らは三年以内にメロンを収穫しないと首だと言い渡される。はるのはなんとかしてみんなをやる気にさせ、メロンを栽培しようとするが、前途多難。
なんとも情けない南と何があっても挫けない、前向きなはるのとの対比が面白かったです。パワハラ上司、室谷、最悪。会社の権力争いっていうものは…溜息。
できすぎ感はありますが、お仕事の本としては面白いですよ。
メロンは栽培がとっても難しいんですって。知りませんでした。
メロン農家さん、いつもありがとうございます。もう少し価格が下がれば、もっと食べますけどww。
『わたし定時で帰ります。3 仁義なき賃上げ闘争編』
定時帰りをモットーとする東山結衣は残業をしたがる若い部下、本間に悩まされていた。二週間前に仙台支店が炎上し、それを鎮めるために結衣の婚約者である種田晃太郎と甘露寺勝が仙台に行き、彼らの代わりとして仙台支社から来たのが平のディレクターの本間とサブマネージャの塩野。会社から残業削減指令が出ているにもかかわらず、本間と塩野谷は残業は仙台では当たり前だという。それでは収まらないのが結衣。本間から残業代がないと生活が苦しいという話を聞き、仙台支所の実態を探っていくと、思ってもいなかった事実が発覚する。定時帰りを死守するために、給料アップを目指し、結衣は人事評価制度の改革を提案するが…。
一方、結衣と晃太郎の結婚は仙台支社の炎上が収まらず、棚上げとなる。
はたして晃太郎との結婚はどうなるのか。
いろいろと問題山積のネットヒーローズ株式会社です。といってもこの会社だけの話ではないですよね。
生活残業や創業メンバーと中途採用の扱い、世代間の給与格差などの問題がわかりやすく書かれた作品です。
出世する気になった結衣がどこまでやるのか、楽しみです。
簡単に読める、面白い本ですので、お暇な時にどうぞ手に取ってみてください。
最近のコメント