今週読んだ本&まんがと映画 ― 2020/01/16

ユジク阿佐ヶ谷という小さな映画館で何回も上映をしている「人生フルーツ」というドキュメント映画を見てきました。
愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンの雑木林に囲まれた一軒屋に住む、建築家の津端修一さん(90歳)と妻の英子さん(87歳)の暮らしを描いた作品です。
修一さんは日本住宅公団で阿佐ヶ谷住宅や多摩平団地などの都市計画に携わってきました。
1960年代に高蔵寺ニュータウンを計画しましたが、経済優先の時代だったため、完成したものは理想とはかけ離れた無機質な大規模団地になってしまいました。
そのため修一さんは仕事から距離を置き、高蔵寺ニュータウンに土地を買い、家を建て、雑木林を育てることにします。
それから50年。
修一さんは90歳になりました。
(ちょっとネタバレあり)
庭で実のなる樹木を育て、畑で野菜を作り、自給自足に近い生活をしている彼らの姿をうらやましく思いました。
毎日身体と頭を使って暮らしているので、心身共に健康を維持していられるのでしょうね。
老いるに従い人生はフルーツのように実り豊かで美しいものであるといえることに羨望を感じます。
本来の人間の死は修一さんの死ようなものかも知れないですね。
でも、自分が彼らのような暮らしができるかというと・・・無理だよなぁ。
<読んだ本>
椹野道流 「鬼籍通覧」シリーズ
『暁天の星』、『無明の闇』、『壺中の天』、『隻手の声』、『禅定の弓』、『亡羊の嘆』、『池魚の殃』、『南柯の夢』の8作品が出版されています。
O医大の法医学教室に大学院生として伊月崇はやってきます。
一見ビジュアル系イケメンの伊月ですが、負けず嫌いだけど意外と素直で頑張り屋なため、人手不足の法医学教室ではかわいがられています。
物語は法医学教室に持ち込まれる遺体に関する謎を解いていくというもので、伊月と法医学教室のNO.2の伏野ミチルと伊月の幼馴染みの刑事・筧たちが活躍します。
林宏司 『トップナイフ』
人気脚本家の林さんが初めて書いた小説だとか。
ドラマにもなっているようですが、内容的に新しさを感じません。
そりゃあ医師にも色々な人がいて、全ての医師が患者のためを思って働いている訳ではないのですが、それでもなんかガッカリ。
脳外科だから?
澤村御影 『准教授・高槻彰良の推察 民俗学かく語りき』
『准教授・高槻彰良の推察2 怪異は狭間に宿る』
『准教授・高槻彰良の推察3 呪いと祝いの語りごと』
『准教授・高槻彰良の推察2 怪異は狭間に宿る』
『准教授・高槻彰良の推察3 呪いと祝いの語りごと』
幼い頃の出来事のため人の嘘がわかるようになった大学生・深町尚哉は人を遠ざけ、孤独に生きてきました。
ところが大学の民俗学2で書いたレポートがイケメン准教授・高槻に気に入られ、バイトと称して怪奇事件の解明に付き合わされることとなります。
軽いけど、都市伝説や幽霊などを扱って民俗学を説いているところが面白いですね。
怪奇事件の落ちがいつも”人”というのがさもありなんです。
いつか深町と高槻の謎が明らかになるのでしょうか。
<漫画>
桜井海 『おじさまと猫 4』
元天才ピアニストの神田冬樹に猫友ができた!
友は神田の才能を憎んでいた奴だったけど。
猫も可愛いけど、猫を愛するおじさんはもっと可愛い(かな?)。
新田章 『恋のツキ 1~7』
映画館に勤める平ワコ、31歳。
彼氏と同棲中でそろそろ結婚か・・・?
そういう時に映画を見に来た高校生を好きになってしまう。
現実的に高校生と31歳の女性って付き合うことあるかしらと思いますが、フランスの大統領のこともありますから、絶対にないとはいえないわね。
でも、なんかワコのことが好きになれないわ。
そう思いながら最後まで読みましたが、終わりがよければすべてよし。
これから年齢に囚われない生き方ができる世の中になるといいわね。
板垣巴留 『BEASTARS 17』
このシリーズも続いてますが、学園ものかと思ったらそうじゃなくなり、一体レゴシはどうなるのか。
最後はハルと異種族結婚でもして幸せになるのかな。
まだまだわかりませんわ。
「ハプスブルク展」@国立西洋美術館 ― 2020/01/17
そろそろ終わりに近づいたので、「ハプスブルク展」に行ってきました。
平日でも人が多く、じっくりは見られませんでした。
最初の部屋にあった甲冑が格好よかったです。
私が一番気にいったのが、このシンプルな甲冑。

他の甲冑は装飾が過多です。

この甲冑なんか服みたいです。
なんでウエストが絞ってあったり、スカートみたいになっているのかわかりません。
戦いに使用するというより、人に見せるためのものという感じです。
日本の鎧もそうですが、重そうです。
これを着て戦うことなんかできないでしょう。
一番最初の部屋だから混んでいるのだと思ったら、どの部屋も混んでいて、落ち着いて見ていられませんでした。
そんなわけでサッと見たので、お決まりのものだけ見てしまいました。

青い服が有名ですが、緑色の服のもあったのです。
何故か青い服に人が群がっていました。

マリア・テレジア、偉大なるお母様。
貫禄があります。

おバカな娘。
よくよく見ると、それほど美人ではないわね。
美人というと、こちら。

若い頃ですか、ウエストの細いこと。腕二本分より細いようです。
他にも絵やなんやらがありましたが、並んでまでも見ることはないとパスしてしまいました。
まだこの展覧会を見ていない方は金曜日の夕方から行かれた方が空いているかもしれません。
そうそうに美術館を引き上げ、ノーガホテル内のビストロでランチを食べました。
コース(3000円)。
アミューズがケーク・サレ(?)の上に生ハムとクリームチーズがのったもの。

前菜がサーモンとクリームチーズ(クリームチーズがかぶってしまい失敗)。
もっとあっさりしたものにすればよかった・・・。

メインにカモ肉を選びました。下にあるのはレンズ豆です。

柔らかくておいしかったです。
これにパン、デザートのバナナのブリュレとキャラメルのアイスクリームと紅茶。
前菜が失敗しましたが、思っていたよりもおいしく、お値段もお安い感じがしました。
上野に行ったらまた利用するかもしれません。
似鳥鶏 『目を見て話せない』 ― 2020/01/19

自称”コミュ障(コミュニケーション障害)”の藤村京は千葉の房総大学に入学しましたが、初めの自己紹介の時から友達作りに失敗。
みんなが連絡先を交換しているのに、誰とも話せず、寝てしまいます。
起きた時には教室には誰もいなくて、傘がポツンと置き去りになっていました。
ここで面白いのが、藤村君はわざわざ誰が置き忘れたのか推理を始めるのです。
普通の人なら「ア、傘の忘れ物かぁ。そのうち取りにくるだろう」と思って、そのままにしておくのにね。
もっと優しい人なら事務室にでも持っていくよね。
そういう場で色々と考えてしまうのが”コミュ障”なのか?
実は彼が”コミュ障”になったのには理由があったのです。
小学校での出来事と言っておきましょう。
彼の推理は当たっており、このことから色々な人と知り合いになっていき、様々な謎を解き明かしていくこととなります。
お話が5話ありますが、1話の妄想場面が読みずらかった。
でも、しばらく我慢して(飛ばして)読んでいると途中から慣れますので安心して読み進んで下さい。
自称”コミュ障”とか言う人は多かれ少なかれ自尊心が高く、ネガティブ思考で被害妄想気味かもしれませんね。
結局、誰もが”コミュ障”的なものを持っているんじゃないの、というのが結論です。(別に結論はいらないけど)
似鳥さんのあとがきがいつも面白いです。
私からのお願いは、この本の続きは書かなくていいから、動物園シリーズ、よろしく(笑)。
小路幸也 『花咲小路一丁目の髪結いの亭主』 ― 2020/01/20
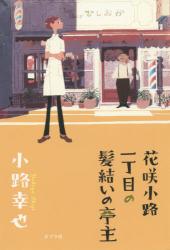
花咲小路シリーズの新刊。
今回はレトロな床屋さんがメインです。
この床屋さんは奥さんのミミ子さんがやっていて、旦那さんは新聞を読んだり、来るお客とお話したりしてのんびりしています。
この床屋に若い女の子、せいらちゃんが住み込みで働いています。
せいらちゃんは口が硬いので、「鋼鉄のセーラ」と言われているのだとか。
それにしても、床屋さん家族は口が軽いわぁ。
せいらちゃんに何でもしゃべっちゃうんだもの。
床屋に持ち込まれたヴィネグレット(気付け薬入れ)から旦那さんが西洋美術の裏の世界では有名な鑑定士だということがわかり、そのせいでセイさんの秘密がばれそうになります。
セイさん、どうなるのか・・・。
しかし、この狭い花咲小路にすごい人が集まっていますね。
次は二丁目。
どの店のどんな人が登場するのかしら。
詳しく花咲小路を知りたい人はポプラ社のHPへ。
「人生をしまう時間」@ユジク阿佐ヶ谷 ― 2020/01/21
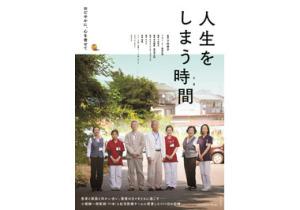
NHKBS1スペシャルの「在宅死”死に際の医療”200日の記録」というドキュメンタリーを映画にしたものです。
埼玉県新座市にある「堀ノ内病院」には在宅医が4人います。
そのうちの1人は80歳の森鴎外の孫で元外科医の小堀鴎一郎。
とても80歳にはみえない、ざっくばらんな人です。
67歳で退職した後に在宅医療に関わることにしたそうです。
もう一人は56歳の国際医療機関の医師だった堀越洋一。
堀越医師はマザー・テレサの「死を待つ人々の家」を訪ねたことがあり、その時のことがずっと心の中で気にかかっていたそうです。
優しい物静かな、丁寧な医師のように思います。
この2人の医師と看護師、ケアマネージャーたちが関わった人々のドキュメンタリーです。
寝たきりで部屋から一歩も出ない妻の面倒をみる夫。
便座に腰掛けられない妻を一本の紐でひょいと持ち上げた時の誇らしげな顔が印象的でした。
施設に入れるお金がないとは言いつつも、妻のことをよく世話していましたが、共倒れになってはいけないと、ケアマネージャーたちが介入した時、妻さんは不機嫌になってしまいます。
いつまでも夫に面倒を看てもらいたいのでしょうね。
103歳の母親を70代の夫婦が見るという老老介護もありました。
母親はなんとも品のいい女性で、膝小僧がきれいだと小堀医師に言われ、はにかんでいた姿が印象的でした。
しかし、だんだんと介護が難しくなり、施設に入り、癌が見つかり、病院で最期を迎えたようです。
77歳の母が癌の52歳の娘の最期をみるというのもありました。
どんな思いで娘を看ていたのでしょう。
映画の中で一番多く時間がさかれていたのが、47歳の盲目の娘のことが心配でと在宅医療を受けていた父親です。
娘可愛さに、手元に置いてずっと面倒を見てきたようです。
小堀医師と柿の話をよくしていました。
娘さんが父親が亡くなるということを理解していないようだと心配していた小堀医師。
最期が近づいていると知らずに、父親の言ったちょっとしたことで泣いてしまったことを後悔している娘さんを慰めながらも、彼女に父親の喉を触らせ、ここが動かなくなったら息をしなくなったということだと教えます。
残された娘さんは父親が亡くなった後どう生きていくのか、とても気にかかりました。
色々な人たちの最期をみて、自分はどういう最期を迎えるのか。
思いをはせてもどうにもなりませんが。
あなたがいい人だから周りにいい人がいるというようなことを小堀医師はある患者さんに言っていましたが、望むらくはいい人たちが最期の時にいますように。
そうは思いつつ、最期は「人生フルーツ」の夫さんみたいに、昼寝をしたら起きてこなかったがいいのですけど。
読んだ本&漫画 ― 2020/01/22

つばた英子・つばたしゅういち 『きのう、きょう、あした。』
「人生フルーツ」の英子さんが一人暮らしを始め、その暮らしを書いた本です。
英子さんが実際に書いたのかどうかはわかりませんが。
写真が主の本です。
しゅういちさんはお元気だと思っていたのですが、腎臓が悪かったようで、塩抜きの食事を作っていたそうです。
しゅういちさんが亡くなってからしばらく畑の手入れをしていなかったので野菜がなくなり、近所の野菜を買って食べたら蕁麻疹ができ、それから毎日1時間は畑仕事をしているそうです。
英子さんも89歳。
今でも手仕事は続けています。
いつまでもお元気で。
みお 『極彩色の食卓』
これもライトノベルかと思ったら、意外といい本でした。
画家になるという夢に挫折し、美大を休学し、顔がよかったため女の紐のような生活を始めた燕は、行き場がなくなり、どうしようかと思っていた時に、かつて天才女流画家とも言われ、今はひっそりと暮らしている律子に拾われる。
生活の面倒を見てもらうのと引き換えに、モデルとなることとご飯を作ることが条件で、燕と律子は一緒に暮らし始める。
燕の作るご飯が美しい。
画家ってこんなに色に執着するものなのですね。
二人が自らのトラウマを克服していく過程が美しいです。
竹岡葉月 『谷中びんづめカフェ 2 春と桜のエトセトラ』
谷中にある珍しいびんづめカフェのお話(題名通りだ)。
びんづめカフェを経営しているイギリス人のセドリックは妻の残した義理の息子と一緒に暮らしている。
彼らとひょんなことで知り合った谷中に住む女子大生・紬は彼の息子の家庭教師として雇ってもらっている。
今回は飼い猫がいなくなったお話や亡くなった奥さんの実家のお話など3話。
びんづめというとジャムとか野菜のピクルスを思い出しますが、結構なんでもびんづめになっちゃうんです。
花見のびんづめ、欲しいですわ。
小湊悠貴 『ホテルクラシカル猫番館 2』
パン職人の紗良はホテル猫番館で働き始めて三ヶ月。
様々な訳ありのお客様がやってくる。
猫連れ小説家は「パンを出すな」と言うし、困ったものです。
今回のパンのマロンクリームのコロネやさくらんぼデニッシュ、食べたいわ。
≪漫画≫
マキヒロチ 『いつかティファニーで朝食を1~14』
美味しい朝食の出てくる漫画です。
28歳、アパレル企業に勤める佐藤麻里子は仕事に悩殺される毎日。
同棲していた彼とも別れ、はまったのが美味しい朝食を食べにいくこと。
高校時代の友人を誘い、今日も美味しい朝食を食べ歩く。
仕事と恋愛。どっちもどっち。
もう結婚に期待する生活は止めようね。
出てくる人たちにあまり共感はできなかったのですが、どこで朝食を食べるのかという興味で最後まで読んでしまいました。
出てくる場所が朝行きたいとは思わない所なのが難点。
電車混んでそうなんだもの(笑)。
本の読み過ぎで、首こりが始まりそうな予感です。
少しペースを落としますわ。
『2人のローマ教皇』を観る ― 2020/01/23
「ローマ教皇」と「ローマ法王」の両方が使われていましたが、日本政府は「教皇」に統一したそうです。
ですからこの映画の題名が『2人のローマ教皇』なんです。

2005年にドイツ出身のラッツィンガーは教皇になる。
この時、彼と教皇の座を争ったのがアルゼンチンの枢機卿、ベルゴリオ。
彼はベネディクト16世(ラッツィンガー)が退位した後に教皇(フランシスコ)になる。
この2人がもし会っていたら、という発想から作られた映画です。
2012年、ベルゴリオは枢機卿を辞める許可をもらうため、ローマへと旅立つ。
教皇は別荘に行っており、そこで辞任の許しを得ようとするが、教皇は受入れてくれない。
当時、バチカンでは修道女や小児への性的虐待や不正を告発した内部文書のリークなどのスキャンダルが持ち上がっていた。
保守派対改革派の相対する2人だが、対話を通して理解し合っていく。
退位を決心するベネディクト16世よりもベルゴリオの過去に重きを置いて描かれています。
彼には結婚まで考えた女性がいたことやアルゼンチンの軍事政権下にイエズス会の神父たちを守るために奔走したのに、軍事政権に協力したと批判されていることなどが描かれています。(アルゼンチンのこと全く知りませんでした)
ベネディクト16世が「ナチ」と批判されているのもでてきますが、彼は第二次世界大戦時、義務とされているヒトラーユーゲントに加入していたからですかね。
難しい教義のことを話すのかと思っていたらそうでもなく、意外とユーモラスな話をしてたりします。
ベネディクト16世が運動量を計測するApplewatchみたいなものをつけていたり、ピアノが上手かったり、フランシスコ教皇がサッカー好きで、一緒にドイツ対アルゼンチンの試合を見たり、テイクアウトのピザを食べたり、別れの時にタンゴを踊ったりetc.。
笑いどころがいっぱいです。
ホント、二人は仲いいです。
おじいさんたち、可愛い(失礼)です。
教皇とはいえ人間なんですね。
夏川草介 『勿忘草の咲く町で~安曇野診療記~』 ― 2020/01/24

三年目の看護師の月岡三琴は松本市郊外にある梓川病院の内科病棟に勤めています。
内科へ研修期間を終えた研修医の桂正太郎がやってきます。
花の名前をよく知っている正太郎は生家が花屋、どこかひょうひょうとした不思議なキャラで、いつしか二人は付き合うようになります。
梓川病院、特に内科は高齢患者で溢れ、まるで介護施設のようです。
そのような状態でも患者のために真摯に取り組む二人がすがすがしいです。
昔なら亡くなっていた人が亡くならなくなり、地方の病院には高齢患者が溢れているといいます。
食べられなくなっても今は胃瘻があるから栄養が行き届いて、たとえ意識がなくても生き続けることになります。
「大量の高齢者たちをいかに生かすかではなく、いかに死なせるか」
これからの医療者はこのことを考えていかなければならないのです。
「死神の谷崎」のような存在も必要なのかも。
自分ならどうしてもらいたいか。自分の家族ならどうするか。
何かあったら考えるではなく、何かある前から考えておくことが大事ですね。
本の中にでてくる「花の美しさに気づかない者に、人の痛みはわからない」
痛烈な言葉です。
花だけではなく夕焼けでもいいし、何かの美しさを愛でる余裕がないのはいけないです。
『神様のカルテ』と同じようにシリーズになりそうです。
一止が現れるかと思ったら、ニアミスでした。残念。
「Girl」@UPLINK吉祥寺 ― 2020/01/25

ベルギー映画。
主演はアントワープの王立バレエ学校生の男の子、ビクトール・ポルスター。
彼はシスジェンダー(こういう言い方があるの、知りませんでした)なのでトウシューズを履いたことがなく、大変だったそうです。
映画の後、しばらくは前のように踊れなかったそうです。
映画のモデルは実際にトランスジェンダーであり、ダンサーであるノラ・モンスクールです。
15歳のララはバレリーナになるために、バレエ学校に編入しようとします。
8週間のトライアルの後、無事に編入を許されますが、他の子たちはララとは違いバレエの基礎ができていました。
追いつこうと必死に努力をするララ。
実はララはトランスジェンダーでした。
女の身体になるためにホルモン療法を始め、2年後には手術も考えられていました。
今を楽しむようにと父親もカウンセラーも言うのですが、ララはとにかく成長していく自分の身体に嫌悪感しかありませんでした。
バレエのレッスンがある日は股間をテープでとめて、水分をとらないようにし、レッスンが終わると急いでトイレに行き、テープを取り、トイレをすまし、水を飲みます。
父親はそんなララを心配して、「どうだ」と聞きますが、いつも答えは「大丈夫」。
本心を絶対に話しません。
学校の女の子たちはララを受入れているようですが、シャワーを何故使わないのかとか聞く子がいたり、ある友人の誕生会では無理矢理ララに身体を見せるようにと迫ったり・・・。
やがて追い詰められたララは・・・。
ララが痛々しかったです。
実際に自分の子がと思うと、お父さんの気持ちはいたたまれないでしょうね。
最後がショッキングですが、彼女はそれで解放されたのでしょうか。
トランスジェンダーの方の中にはこの映画に批判的な方もいるそうですが、どこに不満があるのかシスジェンダーの私にはわかりませんが。
とにかくララを演じたビクトール君、美しいです。
いつか日本にバレエ公演で来てくれたら、見に行きます(たぶん)。
リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー東京吉祥寺でランチをしました。
二階に行くと、女性ばかり。

豚肉のスープランチを食べました。
色からわかると思いますが、ゴボウのポタージュです。
野菜の下に豚肉があります。
これにパンとコーヒー。
1階でパンを買って帰りました。
読んだ本 ― 2020/01/26

下村幸子 『いのちの終いかた』
「人生をしまう時間」を撮ったディレクターの下村さんが書いた本です。
映画の中に出てきた方々と取材はしたけれど映画で紹介できなかった方々を載せています。
父親が亡くなった盲目の女性が元気に暮らしている姿が描かれていて、よかったなぁと思いました。
和田はつ子 『珍味脅かし 料理人季蔵捕物控』
一善飯屋「塩梅屋」は昼賄いの団子汁で評判になっていました。
そんな頃、不審な手紙が届きます。
父親の命が惜しければ、次の料理を作れというものです。
季蔵は元武士。訳あって主家出奔をしており、生家とは縁を切っていたのです。
一体何者がこの手紙を書いたのか。
父親のことが心配な季蔵は急遽家を継いだ弟と会います。
息子のことを思う父の心に泣きます。
矢崎在美 『ぶたぶたのシェアハウス』
ぶたぶたさんシリーズ。
色々な職業につくぶたぶたさんが楽しみでしたが、シェアハウスですか・・・想像もつきませんでした。
それもワケアリ女性のためのシェアハウス兼シェアキッチン。
だれでも来てご飯が食べられ、キッチンを使えるなんて、いいですね。
子ども食堂みたいに大人食堂もあるといいかも。
どの話も最後は明るい終わりなのでいいのですが、ちょっと上手く行き過ぎ感があります。
ぶたぶたさんですから、いいのですが。
椹野道流 『男ふたりで12ヶ月ごはん』
椹野さんの本には美味しそうなご飯が出てくるので、この本も読んでみました。
男ふたりとは、眼科医の遠峯朔と彼の高校の後輩で小説家の白石真生です。
遠峯のところに小説が書けずに悩んでいる白石が押しかけてきます。
日中は仕事の遠峯と夜中に仕事をする白石。
家のことは白石が主にやるということで、意外と気楽な二人暮らしになりました。
この二人の生活を四月から一月ずつ三月まで書いた本です。
ちょっと残念ですが、白石の作る料理がそれほど美味しそうではないのです。
椹野さんはあまり料理が得意ではないのかな?
出てくる中華屋とかケーキ屋の方が美味しそうです。
その点、期待外れでした。
おかざき登 『居酒屋がーる 1&2』
居酒屋「竜の泉」につどう女三人。
彼女たちの頼む料理と日本酒が美味しそう。
こんな居酒屋、近所にないかしらと思えるほどです。
一緒に「竜の泉」にいて、飲んでいるような感じがいいです。
木緒なち 『すべては装丁内』
学央館書房の新人編集者・甲府可能子は初めて本を出版することとなりました。
作家さんから頼まれたイラストレーターからOKをもらえたのに、装丁デザイナーが見つからない。
編集長から紹介されたデザイナーのところに行くと、即断られ、どうすればいいのか・・・。
編集者のお仕事本です。
編集者というと作家との交渉の話はよくあるのですが、今回は装丁デザイナーとのやりとりが書かれています。
おかざきさんは本物の装丁デザイナーだそうで、この本、ご自分で装丁なさっています。
≪漫画≫
竜山さゆり 『うちの犬が子ネコ拾いました。1&2』
大型犬ペリタスが子ネコを2匹拾ってきた。
ご主人様はネコ嫌い。
見つからないようにしなければ・・・。
しかし、見つかってしまい・・・。
2匹の子ネコに翻弄されるペリタスが可愛いです。
西原理恵子 『ダーリンは74歳』
バカップルは相変わらずラブラブです。
高須さんはツイッターやり過ぎです。
余計なお世話ですが、そんなことやるより西原さんともっと仲良くした方がいいと思いますけど。
台湾の高官に会えたりするのは何故?
ゆっくり観光でもやればいいのに、高官に会えないとなるとすぐに日本に帰ってくるあたり、せっかちなのね。
カレーを食べに自衛隊に行けるのも、高須さんなればこそなのね。
普通の人が行ったら相手にされないもの。
死ぬまで騒がせてくれそうなカップルです。
今週も軽いものばかり読んでいました。
じっくり読めるミステリ物求む。
最近のコメント