石持浅海 『扉は閉ざされたまま』 ― 2011/11/15

密室殺人物って好きですか?
大学の同窓会に7人の旧友たちが集まります。
場所は成城の高級ペンション。
完璧な密室を作ることができるはず。
密室殺人は上手くいったように思えたのですが・・・。
大学の同窓会に7人の旧友たちが集まります。
場所は成城の高級ペンション。
完璧な密室を作ることができるはず。
密室殺人は上手くいったように思えたのですが・・・。
始めから犯人がわかっており、もう一人の頭脳明晰な人が次々と謎を解いていくという形式です。
う~ん、本当にそんなにわかってしまうの?と思ったりして。
私のように殺人に付随するゴタゴタしたものを読むのが好きなものにとっては、あまりおもしろいもんじゃなかったです。
純粋に謎解きだけをしたい人向きです。
犯人の動機も、なんだかね。
『Rのつく月には気をつけよう』を読んで、浅海さんってグルメなのかしらと思っていたら、ただの酒好きっぽいですね。
この本にもお酒が出てきます。
ニッカウィスキーの余市でしか買えない限定品のカスクストレングスとシェリー樽十五年物、カリフォルニアワインのオーパス・ワン。
お酒に疎い私には猫に小判ですが。
ちなみに、ニッカウヰスキーを作った人は竹鶴と言う人だとか。
何故か相棒が知っていました。
変なことは知っている、変な人です。ただの酒好きおやじだからかしら?
宮部みゆき 『孤宿の人』 ― 2011/11/17
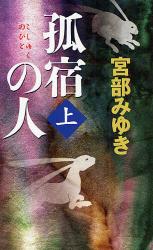
宮部みゆきの歴史小説です。
江戸の建具商「萬屋」の若旦那の私生児として生まれたほうは、母親がほうを産んだ後に死んでしまったため、金貸しの老夫婦にあずけられます。
躾もされずに育ち、九つになった時に「萬屋」に引き取られたのですが、それから「萬屋」に不幸が続きます。
修験者に加持祈祷をさせてご信託をいただくと、「萬屋」を恨んでいる死者の縁に繋がる者を寺社へ送って拝ませるといいとのこと。
ほうは女中と共に四国の讃岐の金毘羅さまを拝みに旅立ちます。
しかし、丸海湾に着いた時、船酔いで具合の悪いほうを置いて、女中は有り金全部を持っていなくなってしまいました。
ほうは代々藩医を勤める井上家にあずけられるのですが、井上家の娘でほうの面倒をみてくれていた琴江が毒殺されてしまいます。琴江の毒殺の事実を知っているほうはある事情から井上家にいられなくなります。
この頃、勘定奉行職にあったにもかかわらず妻子と部下を殺し流刑になった加賀殿が、丸海藩お預かりになります。
井上家から出され、引手見習いの宇佐と暮らしていたほうは、加賀殿を幽閉している涸滝の屋敷の住込み女中にされてしまいます。
丸海藩も丸海の町人も流行り病が起こったり、雷害が起こると、不幸を加賀殿が運んできたと言って恐れました。
妻子と部下を殺した加賀殿は鬼なのでしょうか?
阿呆の「ほう」だと言って人から疎んじられていたほうですが、人を恨まず、人を妬まず、彼女の純粋さが人の心を動かします。
お家が大事。だから真実を明かしてはいけない。
そういう武家社会の建前が人を不幸にしていきます。
ほうは知らないうちに利用されていたのですが・・・。
鬼は人の心に住むのです。
本の中で、心に残った言葉。
「半端な賢さは、愚よりも不幸じゃ。それを承知の上で、賢さを選ぶ覚悟がなければ、知恵からは遠ざかっていた方が、身のためなのじゃ」
「雨は誰の頭の上にも同じように降りかかる。しかし、降り止まぬ雨はない」
加賀殿・・・好みです。
武士の鏡。
こういう考えが脈々と日本社会の底に流れており、第二次世界大戦の時のようになるんだろうなぁと思いました。(詳しくは後の本の紹介で)
江戸の建具商「萬屋」の若旦那の私生児として生まれたほうは、母親がほうを産んだ後に死んでしまったため、金貸しの老夫婦にあずけられます。
躾もされずに育ち、九つになった時に「萬屋」に引き取られたのですが、それから「萬屋」に不幸が続きます。
修験者に加持祈祷をさせてご信託をいただくと、「萬屋」を恨んでいる死者の縁に繋がる者を寺社へ送って拝ませるといいとのこと。
ほうは女中と共に四国の讃岐の金毘羅さまを拝みに旅立ちます。
しかし、丸海湾に着いた時、船酔いで具合の悪いほうを置いて、女中は有り金全部を持っていなくなってしまいました。
ほうは代々藩医を勤める井上家にあずけられるのですが、井上家の娘でほうの面倒をみてくれていた琴江が毒殺されてしまいます。琴江の毒殺の事実を知っているほうはある事情から井上家にいられなくなります。
この頃、勘定奉行職にあったにもかかわらず妻子と部下を殺し流刑になった加賀殿が、丸海藩お預かりになります。
井上家から出され、引手見習いの宇佐と暮らしていたほうは、加賀殿を幽閉している涸滝の屋敷の住込み女中にされてしまいます。
丸海藩も丸海の町人も流行り病が起こったり、雷害が起こると、不幸を加賀殿が運んできたと言って恐れました。
妻子と部下を殺した加賀殿は鬼なのでしょうか?
阿呆の「ほう」だと言って人から疎んじられていたほうですが、人を恨まず、人を妬まず、彼女の純粋さが人の心を動かします。
お家が大事。だから真実を明かしてはいけない。
そういう武家社会の建前が人を不幸にしていきます。
ほうは知らないうちに利用されていたのですが・・・。
鬼は人の心に住むのです。
本の中で、心に残った言葉。
「半端な賢さは、愚よりも不幸じゃ。それを承知の上で、賢さを選ぶ覚悟がなければ、知恵からは遠ざかっていた方が、身のためなのじゃ」
「雨は誰の頭の上にも同じように降りかかる。しかし、降り止まぬ雨はない」
加賀殿・・・好みです。
武士の鏡。
こういう考えが脈々と日本社会の底に流れており、第二次世界大戦の時のようになるんだろうなぁと思いました。(詳しくは後の本の紹介で)
百田尚樹 『永遠のO』 ― 2011/11/19
今回読んだ本は、退職した元同僚の女性が勧めてくれた本です。
戦争物はあまり好きではなくて読まないのですが、読んでみました。
戦争物はあまり好きではなくて読まないのですが、読んでみました。

司法試験受験勉強をするためニート(懐かしい!)をやっている26歳のぼくは、姉でフリーライターの慶子からアルバイトを持ちかけられます。
彼らの母親が実の父親、彼らにとっては祖父である宮部久蔵のことを知りたいと言い出したのです。
宮部久蔵は彼らの祖母の初めの夫で、「大正八年東京生まれ、昭和九年、海軍に入隊。昭和二十年、南西諸島沖で戦死」していたのです。
旧海軍関係者の集まりである「水交会」に問い合わせ、いくつかの戦友会を教えてもらいました。その会に問い合わせ、祖父を知っている人が見つかると会いに行きます。
会った人はみな宮部はパイロットとして一流だったが臆病者で、「命が惜しくて惜しくてたまらない男」であったといいます。
祖父の宮部はみんなが言うように臆病者だったのでしょうか?
夫は証言①の段階でつまらなさうだったので、読むのを止めてしまったそうです。
実は私もそう思いました。
しかし、その後からミステリーを読み解くようなおもしろさが出てきました。
人の真実なんて、その人にしかわからないことです。
まわりの人は、その人の一面しか見ていないからです。
しかし、色々な人の証言を集めたら、真実の一面が見えるかもしれません。
ずっと前の職場で父親が戦死して、一度も顔を見たことがないという女性がいました。
彼女は新聞に戦争のことが書かれているとスクラップしていました。
戦友会の人とコンタクトを取り、父親と同じ部隊にいた人を探しては会いにいっていました。
一度も結婚をしたことはなく、結婚すると父親のことが調べられなくなるからと言っていました。
退職してもう10年以上経っていますが、どうしているのかと思うことがあります。
例え同僚に「給料泥棒」(こう言った人は今鬱病で仕事ができません。人のことを悪く言ってはいけませんね。何があって自分も仕事ができなくなるかわかりませんから・・・)と言われようが、困った人と思われようが、父親のことを知るということが彼女の一生の仕事になっていたのです。そのために周りの迷惑も何も考えられなかったのです。
彼女の一生は亡き父親を偲ぶことで費やされていたのです。
傍から見ていた私たちは、もっと違う風に生きればいいのにと思いました。
「私は天涯孤独なの」と言っていた彼女の淋しそうな姿が浮かびます。
『孤宿の人』の時も思ったのですが、日本社会は滅私奉公を強いる社会。
丸海藩存続のため、琴江が毒殺されたことを明らかにできませんでした。
御家存続のため、加賀殿は鬼になりました。
第二次世界大戦の時も同じ。
「ほとんどの戦場で兵と下士官たちは鉄砲の弾のように使い捨てられていた。(中略)だからこそ彼らに降伏することを禁じ、捕虜になることを禁じ、自決と玉砕を強要したのだろう。力を尽くして戦った末に敗れた者に「死ね」と命じたのだ」
「(アメリカの)「VTヒューズ」は言ってみれば防御兵器だ。敵の攻撃からいかに見方を守るかという兵器だ。日本軍にはまったくない発想だ。日本軍はいかに敵を攻撃するかばかりを考えて兵器を作っていた。その最たるものが戦闘機だ・・・」
海軍は、特攻や人間魚雷回天を考え、鉄砲弾のように兵士を使い捨てにしました。
特攻隊員の乗った戦闘機も回天も、そのほとんどが敵の艦体まで届くことがなかったということです。
ここから私の考えが飛びます。
フクシマのことを考えると、日本のこの体質は変わっていないのではないかと思うのです。
住民は使い捨て。子供が死ぬといっても全員ではない。
日本の繁栄のために少しの犠牲は許される。
文句を言うな。
考え過ぎでしょうか?
宮部少尉のように生きることは難しいです。
彼のように「わたくしはわたくしの戦いをするだけです」と言えるようになりたいです。
しかし、へたれの私にはそういう勇気も信念もありません。
それでも、大事な時に声をあげられる人になれるように頑張っていきたいと思っていますが。
20代でアメリカ旅行をした時に行ったスタジアムに、その土地で戦死した人の名前が彫られたプレートがありました。
そのプレートの横にあった説明文を読んだ時、日本との違いを感じました。
彼らは「freedom」のために闘った。
日本なら「お国」ですか。
ゼロ戦のことなど詳しく書かれていますので、戦闘機ファンにもおもしろい本ですし(あ、もう知っていることばかりかも・・・)、もちろん戦争のことを知らない世代が読んでもおもしろい本です。ミステリーを読むように読んでみてください。
彼らの母親が実の父親、彼らにとっては祖父である宮部久蔵のことを知りたいと言い出したのです。
宮部久蔵は彼らの祖母の初めの夫で、「大正八年東京生まれ、昭和九年、海軍に入隊。昭和二十年、南西諸島沖で戦死」していたのです。
旧海軍関係者の集まりである「水交会」に問い合わせ、いくつかの戦友会を教えてもらいました。その会に問い合わせ、祖父を知っている人が見つかると会いに行きます。
会った人はみな宮部はパイロットとして一流だったが臆病者で、「命が惜しくて惜しくてたまらない男」であったといいます。
祖父の宮部はみんなが言うように臆病者だったのでしょうか?
夫は証言①の段階でつまらなさうだったので、読むのを止めてしまったそうです。
実は私もそう思いました。
しかし、その後からミステリーを読み解くようなおもしろさが出てきました。
人の真実なんて、その人にしかわからないことです。
まわりの人は、その人の一面しか見ていないからです。
しかし、色々な人の証言を集めたら、真実の一面が見えるかもしれません。
ずっと前の職場で父親が戦死して、一度も顔を見たことがないという女性がいました。
彼女は新聞に戦争のことが書かれているとスクラップしていました。
戦友会の人とコンタクトを取り、父親と同じ部隊にいた人を探しては会いにいっていました。
一度も結婚をしたことはなく、結婚すると父親のことが調べられなくなるからと言っていました。
退職してもう10年以上経っていますが、どうしているのかと思うことがあります。
例え同僚に「給料泥棒」(こう言った人は今鬱病で仕事ができません。人のことを悪く言ってはいけませんね。何があって自分も仕事ができなくなるかわかりませんから・・・)と言われようが、困った人と思われようが、父親のことを知るということが彼女の一生の仕事になっていたのです。そのために周りの迷惑も何も考えられなかったのです。
彼女の一生は亡き父親を偲ぶことで費やされていたのです。
傍から見ていた私たちは、もっと違う風に生きればいいのにと思いました。
「私は天涯孤独なの」と言っていた彼女の淋しそうな姿が浮かびます。
『孤宿の人』の時も思ったのですが、日本社会は滅私奉公を強いる社会。
丸海藩存続のため、琴江が毒殺されたことを明らかにできませんでした。
御家存続のため、加賀殿は鬼になりました。
第二次世界大戦の時も同じ。
「ほとんどの戦場で兵と下士官たちは鉄砲の弾のように使い捨てられていた。(中略)だからこそ彼らに降伏することを禁じ、捕虜になることを禁じ、自決と玉砕を強要したのだろう。力を尽くして戦った末に敗れた者に「死ね」と命じたのだ」
「(アメリカの)「VTヒューズ」は言ってみれば防御兵器だ。敵の攻撃からいかに見方を守るかという兵器だ。日本軍にはまったくない発想だ。日本軍はいかに敵を攻撃するかばかりを考えて兵器を作っていた。その最たるものが戦闘機だ・・・」
海軍は、特攻や人間魚雷回天を考え、鉄砲弾のように兵士を使い捨てにしました。
特攻隊員の乗った戦闘機も回天も、そのほとんどが敵の艦体まで届くことがなかったということです。
ここから私の考えが飛びます。
フクシマのことを考えると、日本のこの体質は変わっていないのではないかと思うのです。
住民は使い捨て。子供が死ぬといっても全員ではない。
日本の繁栄のために少しの犠牲は許される。
文句を言うな。
考え過ぎでしょうか?
宮部少尉のように生きることは難しいです。
彼のように「わたくしはわたくしの戦いをするだけです」と言えるようになりたいです。
しかし、へたれの私にはそういう勇気も信念もありません。
それでも、大事な時に声をあげられる人になれるように頑張っていきたいと思っていますが。
20代でアメリカ旅行をした時に行ったスタジアムに、その土地で戦死した人の名前が彫られたプレートがありました。
そのプレートの横にあった説明文を読んだ時、日本との違いを感じました。
彼らは「freedom」のために闘った。
日本なら「お国」ですか。
ゼロ戦のことなど詳しく書かれていますので、戦闘機ファンにもおもしろい本ですし(あ、もう知っていることばかりかも・・・)、もちろん戦争のことを知らない世代が読んでもおもしろい本です。ミステリーを読むように読んでみてください。
PREMIUM HIGHBALL 竹鶴 ― 2011/11/20
コンビニ限定『ニッカ竹鶴プレミアムハイボール』をアサヒビールさんからプレゼントされました。
ウィスキーの黄金色の缶が高級感を醸し出していますね。
ウィスキーの黄金色の缶が高級感を醸し出していますね。

相棒は酒好きで、毎日缶ビールなどを飲んでいますので、どういう風に感想を言うのか楽しみにしていたのですが・・・。
「甘くなくて美味しい」
ハァ~、「甘くない」?もっと違った感想はないんかいと突っ込みを入れると、
こういうものはたいてい甘いので嫌なのだそうです。
アルコールに弱い私もツマミにカマンベールチーズと酒肴をつけたインカの目覚めを用意していただいてみました。(ウィスキーにはどんなツマミがいいんでしょうか?)

炭酸の口当たりが心地よく、安いウィスキーやお酒を飲んだ時の独特の酒臭さがなく、とっても飲みやすいです。
ビールは苦くてそんなに飲めない私ですが、これはいいかも。
年齢がわかるのですが、私の大学生の時のコンパというと、ウィスキーの水割りでした。カティサークやサントリーオールドを飲んでいました。今から考えると、水割りってお酒の量をごまかせるから、飲めなくてもよかったんです。
今はビールで乾杯ですものね。
相棒曰く。「これ高そう」
コンビニでおいくらで売られているんでしょう?
今までは私用に「ほろよい」を買っていたのですが、甘くてね・・・。
これ、いいかも。
近くのコンビニで売っていたら、私用に買わせますわ。
と言っても、相棒に飲まれてしまうかもしれませんが。
「竹鶴」は前にも書きましたが、ニッカウヰスキーの創業者の名字。
竹鶴さんはニッカウヰスキーを創業する前にサントリーのウィスキー工場長をやっていたんです。
彼はスコットランドの気候に近い余市に移り住み、理想のモルトを作ろうとしたとか。
ウィスキーは製造から出荷までに時間がかかるので、最初はリンゴジュースを作り、会社の名前を大日本果汁株式会社としたそうです。
そう、大日本果汁を縮め、日果(ニッカ)。
なんでニッカウヰスキーというのかという疑問が解けました。
ちなみに創業者竹鶴政孝さんの奥様はスコットランド人だそうです。周りの反対にも負けずに結婚を貫き通したそうです。
一冊の本が書けますね。
ニッカウヰスキーは今やアサヒビールの子会社。
色々とあるんですねぇ。
ビールは苦くてそんなに飲めない私ですが、これはいいかも。
年齢がわかるのですが、私の大学生の時のコンパというと、ウィスキーの水割りでした。カティサークやサントリーオールドを飲んでいました。今から考えると、水割りってお酒の量をごまかせるから、飲めなくてもよかったんです。
今はビールで乾杯ですものね。
相棒曰く。「これ高そう」
コンビニでおいくらで売られているんでしょう?
今までは私用に「ほろよい」を買っていたのですが、甘くてね・・・。
これ、いいかも。
近くのコンビニで売っていたら、私用に買わせますわ。
と言っても、相棒に飲まれてしまうかもしれませんが。
「竹鶴」は前にも書きましたが、ニッカウヰスキーの創業者の名字。
竹鶴さんはニッカウヰスキーを創業する前にサントリーのウィスキー工場長をやっていたんです。
彼はスコットランドの気候に近い余市に移り住み、理想のモルトを作ろうとしたとか。
ウィスキーは製造から出荷までに時間がかかるので、最初はリンゴジュースを作り、会社の名前を大日本果汁株式会社としたそうです。
そう、大日本果汁を縮め、日果(ニッカ)。
なんでニッカウヰスキーというのかという疑問が解けました。
ちなみに創業者竹鶴政孝さんの奥様はスコットランド人だそうです。周りの反対にも負けずに結婚を貫き通したそうです。
一冊の本が書けますね。
ニッカウヰスキーは今やアサヒビールの子会社。
色々とあるんですねぇ。
帚木蓬生 『風花病棟』 ― 2011/11/22
冬になったので、景気づけに(特に意味はないですが・・・)花を買いました。
まず、冬の花と言えば、そう、シクラメン。
まず、冬の花と言えば、そう、シクラメン。

このシクラメン、しばらくしたら元気がなくなりました。
三年前に買ったシクラメンの一つは未だに元気で、年明けごろに花が咲きそうです。
花屋のには成長ホルモンを与えているといいますから、すぐに枯れるのでしょうか?
水は下に入れるところがあるので、家の環境が悪かったのでしょうか?
三年前に買ったシクラメンの一つは未だに元気で、年明けごろに花が咲きそうです。
花屋のには成長ホルモンを与えているといいますから、すぐに枯れるのでしょうか?
水は下に入れるところがあるので、家の環境が悪かったのでしょうか?

このミニバラは玄関の外に置いてあります。次々に花を咲かせてくれます。

クリスマスが近いので、ポインセチアも買いました。
花屋さんによると最高級のポインセチアだそうです。
昨年買った某有名花屋のポインセチアはしばらく経つと枯れてしまいました。
これは上手く育てると三月ぐらいまで持つらしいです。
ポインセチアはクリスマスの頃に買いますが、実はこの花の原産地はメキシコで、熱帯の花なんです。寒さに弱いとは、知らなかった・・・。
育つと高さが3mにもなるそうで、花というよりも木ですね。庭があったら植えるんですが・・・。
もらった育て方のメモをを見てびっくりしました。
水やりは「15℃から18℃くらいの温かい水」を与えるんですって。
や~、世の中知らないことが色々とありますね。

久しぶりの帚木さんの本です。
白血病になって治療をなさっているのですが、どうなったのか心配です。
彼の歴史小説が結構よかったので、また書いてくれないかしら。
今回のは短編小説で10人の医師の姿が書かれいます。
帯には「10人の良医たち」とのこと。
病気にならない人はいないので、誰でも色々な医師に診察してもらった経験があることと思います。
私の感じとして、内科医は優しい人が多いです。
最悪なのが整形外科医でした。
選ぶ科によって医師の性格って変わるのでしょうか。
「百日紅」には主人公以外にある老医師が出てきます。
彼は聴診器を使い、打診をし、入念な聴診をしただけで、検査結果を見ずに患者の様態を説明できたのです。
今の若い医師は患者に触りません。この老医師が「素手で患者から所見を得られる最後の世代に属する」と書いてありました。
そういえば、渋谷区に住んでいた時の内科医はおばあさん医師で、お腹を触る時はきっちりと心を込めて、両手で触ってくれました。不思議と彼女の出す薬は効きました。
笑っちゃったのは、いつも「チョコレートは胃に悪いので、食べないように」と言われたことです。私別にチョコレート食べてませんのに。
たまに夫と彼女のことを話すことがあります。
手当ともいいますから、医師に触られることにより患者が安心するのです。
千葉県に住んでいた時の歯医者は初めて安心して治療を頼める人でした。彼があごのあたりを撫でてくれた時、緊張が解けました。私は歯医者が大嫌いなので、いつも緊張しているのですが、彼は安心感を与えてくれた初めての歯科医でした。
本の中の医師は患者としっかり向き合っているようです。
「チチジマ」には『永遠のO』でも書いてあった出来事が書かれていました。有名な話なのでしょうね。
感染症国際学会で<臍の垢による破傷風三例>という演題で発表をした私は、戦時中にチチジマにいたというアメリカ人医師のマイケルと出会います。
私もその時、チチジマの陸軍病院にいたのでした。
話してみると、チチジマで私が偶然に見たパイロットは、マイケルだったことがわかりました。
チチジマでマイケルは二時間海に浸かっていました。というのも、マイケルが乗っていたP-51ムスタングが故障し火を噴いたので、落下傘で二見湾に着水したからです。
彼の救出のためにアメリカ軍の編隊が次々と急降下してきて、日本軍の陣地に銃弾をあびせかけました。日本軍からの反撃がないと分かると、飛行艇がやってきて彼を助けました。
マイケルはただの少尉。それなのにアメリカ軍は彼を救うために大がかりな救出作戦を組んだのです。
そういう場合、日本軍はどうしたでしょうか。
「パイロットは所詮は使い捨てだったのではないか。敵地に不時着したあと、苦心惨憺して帰隊した戦闘機の搭乗員が歓迎されたという話は聞かない。命が惜しかったのだろうと、陰口を叩かれ、はては再び過酷な戦地送りになるのが通り相場だったのではなかったか。ましてただの二等兵なら完全に無視だ。日本では、国民ひとりひとりがかけがえのない存在ではなく、その他大勢の中のひとりでしかない。それはまだ続いている」
こういうのを読むと、悲しくなりますね。
日本では命が軽く扱われていたということですから。
これからの指針にしたいのが、「終診」に出てくる言葉です。
「逃げんで、踏みとどまり、見届ける」
医師だけではなく、普通の生活にも必要なことだと思います。
10人十色。
それぞれに感慨深いものがありました。
善福寺川緑地を歩く ― 2011/11/23
今日は善福寺川に行ってきました。
川沿いに遊歩道があります。そこをずっと三時間ほど歩きました。
グラウンドやテニスコート、交通公園などがあるので、秋の休日をのんびり過ごしている人たちがたくさんいます。
野球少年たちを写していると、自分たちを撮られていると勘違いしたサッカー少年たちがポーズを取っていたようですが、私は全然気づきませんでした。後で相棒に言われて、ポーズを取っている子たちが撮れずに残念でした。
気づかずにごめんね。
川沿いに遊歩道があります。そこをずっと三時間ほど歩きました。
グラウンドやテニスコート、交通公園などがあるので、秋の休日をのんびり過ごしている人たちがたくさんいます。
野球少年たちを写していると、自分たちを撮られていると勘違いしたサッカー少年たちがポーズを取っていたようですが、私は全然気づきませんでした。後で相棒に言われて、ポーズを取っている子たちが撮れずに残念でした。
気づかずにごめんね。


イチョウはまだまだ色づいていません。
なんという木の葉っぱかわかりませんが、枯れた感じがきれいです。
なんという木の葉っぱかわかりませんが、枯れた感じがきれいです。

紅葉も赤くなっていませんが、日の当たりが悪いせいなのか、赤くなっているのも少しですがありました。



秋は花が少ないのですが、葉っぱの色がきれいなので歩いていても気持ちがいいです。
この色は人間には作れませんね。

途中にあったお寺の柱を見てびっくり。
雨樋の下の雨ためっていうんですか。妙に大きくて、井戸みたいです。

善福寺川はきれいだからなのか、鴨(だよね)がたくさんいます。
写真に撮った鴨は潜るのが好きらしく、かわいらしいお尻を出して、何回も頭を水の中に入れていました。

三時間も歩いたのに、体重計で体脂肪やらなんやらを見てみると、全然変わっていません。歩いても脂肪は減らないということですね。
遊歩道を走っていた人を見習って走らないといけないですか・・・。
宮部みゆき「霊験お初捕物控」 ― 2011/11/26

日本橋通町の一膳飯屋「姉妹屋」の看板娘、お初には不思議な力がありました。
今でいう超能力です。この能力は初潮が来てから強くなりました。
お初は三歳の時に火事で親を亡くし、岡っ引きをしている六蔵とおよし夫婦に引き取られ、彼らの妹として暮らしていました。
彼女の不思議な能力が六蔵の仕事に役立つために、今では南町奉行根岸肥前さまに直につき従って、公にならないところの働きをしています。
彼女の能力とは、私的にはあまりあってほしくないものです。
すれ違った人の着物に血が付いているのが見えたり、殺人の場面が見えたり・・・。
いつ見えるかはわからないのです。
いいこと、例えば昔住んでいた人がお金を埋めている場面が見えたりしないというのが残念ですね。
事件が起こった場所に行くと見えることが多いので、六蔵に頼まれて現場に行きます。
16歳の娘が殺人現場を見るなんて、相当タフでなければできませんわ。
色々と事件が起こるのですが、私が気に入ったのは二冊目の『天狗風』です。
あの・・・たいした内容ではないです。ただ猫が出てくるんです。
この猫、鉄って言うんですが、お地蔵様の生まれ変わりかなにか知りませんが、狸のように化けるんです。
化けるにも見本が必要で、化けた物が笑っちゃいます。巨大な将棋の駒とかタヌキの置物とか・・・。
ちょっとオマヌケです。
そうそう、お初の不思議な能力の中に動物の言葉がわかるというのが入りました。何故か鉄の話が話していることがわかるんです。
本に書かれている事件が、女の怨念っていうのがなんだかね。
この頃の女性の置かれている立場を考えると仕方ないんでしょうが。
このシリーズ、最初は短編でした。
まず、短編集『かまいたち』の「迷い鳩」と「騒ぐ刀」を読み、『震える岩 霊験お初捕物控』、『天狗風 霊験お初捕物控(二)』と読んでください。
私は最後に『かまいたち』を読みました。いつもながら、出版された順番をよく調べずに読む人なんです(恥)。
宮部みゆきの江戸物シリーズを三つ読みましたが、その中で一番好きなのは、やっぱり井筒平四郎シリーズです。
二番目が三島屋シリーズ。このお初シリーズは奇想天外なところがあっておもしろいのですが、人情話が好きな私としては物足りなく感じるので三番目となります。
どのシリーズもおもしろいので、人情物が好きなら平四郎、ちょっと影のある女性が好きならおちかの三島屋、そして物の怪や超能力が好きならお初ですかね。(どういう分け方か自分でもよくわかっていませんが)
どのシリーズも続編が楽しみです。
紅葉ライトアップ@大田黒公園 ― 2011/11/27
大田黒公園でライトアップが始まりました。
来週までなので、今週はそんなに人が来ていないだろうと思って行ってみました。
近所で買い物帰りに寄ったという女性や家族連れなどが来ています。
カメラ小僧はいませんが、カメラおじいさんが一人、三脚にカメラで写真を撮っていました。
紅葉はまだまだ本番には遠いようです。
入り口のイチョウはまだ緑です。
来週までなので、今週はそんなに人が来ていないだろうと思って行ってみました。
近所で買い物帰りに寄ったという女性や家族連れなどが来ています。
カメラ小僧はいませんが、カメラおじいさんが一人、三脚にカメラで写真を撮っていました。
紅葉はまだまだ本番には遠いようです。
入り口のイチョウはまだ緑です。

門から入ってしばらく歩くと突き当たる引き戸の上の木が赤く紅葉しています。

池にライトアップした木が反射しています。



茶室も電気をつけてくれているので、中の様子がよくわかりました。

結構大きな茶室です。
紅葉は来週末辺りがいいような感じです。
来週にまた来ようかしら。人が多そうですが。
百田尚樹 『風の中のマリア』 ― 2011/11/29

『永遠のO』が面白かったし、元同僚も勧めてくれたので読んでみました。
でも『永遠のO』とは全く違ったものでした。
題名からしてちょっととは思ったのですが、違う意味で騙されました。
マリアとはなんとオオスズメバチの働き蜂の名前なのです。
私はハチには興味がありません。
前に読んだ『ハチはなぜ大量死したのか』は面白く読めましたが、この本は小説としてどうでしょうか・・・。
生物に興味のある人には面白いかもしれません。
ようするにハチを擬人化した物語です。
ハチが話せたら、たぶんこういう風に考えるんだろうなぁと作家が想像して書いたものです。もちろん学術的に正確なものだと思います。
私の知らないことがたくさんでてきました。
例えば、ハチはどんな種類でも花の蜜を吸って生きているんだと思ったのですが、違うんです。
オオスズメバチの幼虫や蛹は蜜なんて食べないんです。肉食なんです。
チョウやコガネムシ、イモムシ、クモ、ハナバチなどの肉団子を食べるんです。
働き蜂は獲物を捕えて殺し、顎で砕いて肉団子にして幼虫たちにあげるんです。
意外と残酷なんですね。
一方、成虫たちは樹液や花蜜、幼虫の出す唾液を食べます。
秋になり餌が足りなくなると、オオスズメバチたちは他のハチの巣を集団襲撃します。
十頭のオオスズメバチが三万を超えるミツバチを虐殺なんてこともあるそうです。
恐ろしい。
ニホンミツバチはオオスズメバチに勝つために蜂球などというものを作ります。
集団でオオスズメバチのまわりに集まり、球のようになり、そこにいる全員が翅をふるわせ蜂球の中を摂氏四十八度にして、中にいるオオスズメバチを熱死させるのだとか。
すごいですね。
ちなみにオオスズメバチってこんなハチです。

ハチってしっかり見たことがないので、遭遇したことがあるかどうか何とも言えません。ハチの違いがよくわかりませんわ。
人間とは違い、本能のままで生きているオオスズメバチの生きざまに感動できるかどうかによって評価がわかれるでしょうね。
最近のコメント