朝井まかて 『先生のお庭番』&『花競べ』 ― 2014/07/01
朝井まかてさんの本は『すかたん』を読んでいたので、江戸物を書く人ということでインプットされていました。
色々と読むのでブログに書くのを忘れていたようですが。
今回は二作品を読んでみました。
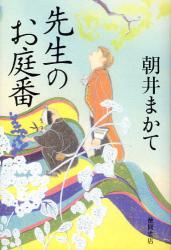
先生とはシーボルト。
出島に薬草園を作りたいという依頼を受けた長崎の植木商「京屋」でしたが、職人たちが怖気ずき、誰も行きたいといいません。
そんなわけで15歳の庭師修行中の熊吉が行くことになります。
失敗しながらも、シーボルトのために一生懸命働く熊吉は、いつのまにか一人前の植木職人へと成長していくのでした。
日本の草花に魅入られていたシーボルトですが、彼の中にある西洋精神は日本の自然と共に生きるという生き方を理解できなかったようです。
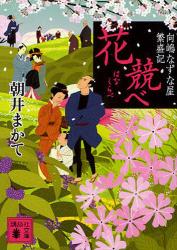
向島の種苗屋「なずな屋」は新次とおりんの若夫婦が営んでいました。
新次は腕はいいのですが、口下手。
おりんは明るく物知りで、元手習い師匠。
おりんの書いた草花の育て方が評判になり、商売も上手くいっていました。
そんな折に、ひいきにしてくれている上総屋六兵衛に懇願され、三年に一度開催される「花競べ」に出品することになります。
日本人は昔から草花と共に暮らしていたのですね。
そのことがよくわかる作品です。
波津彬子 『雨柳堂夢咄』 ― 2014/07/03

私的に、はまる漫画です。
雨柳堂の店主の孫、蓮はものの想いを聞くことのできる不思議な力を持っており、骨董品の目利きでもあります。
雨柳堂に持ってこられるものが引き起こす不思議な出来事。
ものの想いを蓮が受けとめ、解決していきます。
今のものに溢れた生活をしていると、ものを大事にするという気持ちが薄れていきます。
昔の人はものを大事にして使っていたため、ものに想いが残ることが多いのでしょうね。
付喪神などもその一種でしょう。
ものを大事にしない私はついついiPhone5をiPhone5sに替えてしまいました。
使い方は変わりありません。
指紋認証などという機能があってさっそく使ってみました。
夫が帰ってきたら彼の指紋でも使えないか試してみようと思います。
カメラも新しくなったというので、明日にでも何か撮ってみようと思います。
それほど使いこなせないでしょうがね。
そろそろiPhone6が発売されそうですが、後2年はこれで我慢しますわ。

我が家のわんこはやっと暑さに慣れてきたのか、この頃餌を完食しています。
前足上げは相変わらずやっています。
食べたらソファの上にのせて動けないようにしているので吐くこともありません。
公園まで歩いていくと道路の暑さで疲れるようなので、公園まで抱いて行って野原で遊ばしています。
抱いているとわんこの熱で人間の方が疲れます。
今頃、自転車の前籠に犬を入れている人が多いのに気づきました。
そんなわけで自転車を買いました。
これで暑い思いをしないで、わんこを公園まで連れて行けます。
夫は心配性で、誰でも入れる自転車置き場なので、盗まれたり、いたずらされないかと心配しています。
安い自転車なので、そんな心配はないと思いますけど、笑。
デボラ・クーンツ 『規格外ホテル』 ― 2014/07/04

いかにもアメリカのラスベガス。
ハチャメチャなお客と引き起こされるトラブル。
そのトラブルの数々を解決していくのが、二人の部下を持つ、ホテル<バビロン>の顧客関連係主任のラッキー・オトゥールです。
まだ三十代(だと思う)の女性で悩みも多い。
母親モナは売春宿の経営者で、近ごろ判明した父親は<バビロン>のオーナーのビッグボスことアルバート。
モナとビッグボスは関係を復活したのだけれど、モナのとんでもない行動にビッグボスもたじだじ。
ラッキーも振り回されます。
ボクシングの試合が<バビロン>で行われることになり、それでなくても忙しいのに、ミツバチが大通りを飛び回り、ホテルの廊下には全裸の男、そして、極めつけはサメの水槽に浮かんでいた女性の死体。
容疑者として部下のミス・パターソンの恋人でラッキーの友人の私立探偵ジェレミーが逮捕されます。
ミス・パターソンに頼まれ、ジェレミーの汚名を晴らすために行動を起こすラッキーでした。
彼女は頼りになる姉御という感じですね。
そんな彼女にも悩みがありました。
恋人のテディが歌手デビューできそうなのですが、二人の関係がどうなるのか心配なのです。
ラスベガスには行ったことがないですが、この本を読んでいるとラスベガスの煌びやかさとその裏にある猥雑さ、胡散臭さなどがわかります。
ショウが素敵だというので、見に行きたい気もしますが、賭けはやりませんわ。
ハマりそうですから。
元気なヒロインが好きな人にお勧めです。
森晶麿 『黒猫の接吻あるいは最終講義』 ― 2014/07/05

気持ちよさそうに居眠りする犬は、見ているだけでなごみます。

今回の黒猫シリーズは楽しめました。
美学講義はちょっと私の能力を超えていますが、前回と違って今回のモチーフはバレエの『ジゼル』です。
黒猫に誘われバレエ『ジゼル』を見に行った付き人は、黒猫の大学時代の友人でガラスアーティストの塔馬に会い、五年前に黒猫は天才プリマと同棲していたと教えられます。
第一幕の終わり、ジゼルが心臓発作で亡くなろうとしている時に、アブレヒト役の男性が転倒するというアクシデントが起こります。
プリマは上演中にもかかわらず、舞台から退場してしまいます。
その時、塔馬は「復活した・・・」とつぶやきます。
五年前、同じホールの『ジゼル』公演中に、黒猫の元恋人で塔馬の婚約者のプリマが自殺したそうです。
本当に自殺だったのかと疑問を持つ付き人。
黒猫はプライベートな事件だから首をつっこむなと言います。
付き人は自分一人で五年前の出来事を調べることにします。
『ジゼル』の解釈がおもしろいですね。
「バレエにおいてはありきたりなメロドラマが一瞬にして崇高な芸術に変わる瞬間が訪れる」
もう一度『ジゼル』を見たくなりました。
残念ながら今年日本に来るバレエ団は『ジゼル』を踊りません。
ボリショイは「ラ・バヤデール」を見たかったのですが、犬の餌やりがあるので行けません。
休日は「白鳥」と「ドン・キホーテ」だし・・・。
小説に出てくる「モンロー・グラス」、かわいいです。
モンローの足ペンもあるそうです。
どこに売っているのかしら?
黒猫シリーズはまだまだ続きます。
黒猫と付き人の関係に変化があるような・・・?
森晶麿 『黒猫の刹那あるいは卒論指導』 ― 2014/07/06

相変わらずかわいい表紙です。
この本は付き人が付き人ではなかった頃のお話です。
二人は大学四年生。
学長のゼミに急に現れた黒猫はある事件の目撃者にしたてあげられようとします。
彼は危険に気づき、この頃から揉め事に関わる体質のあった付き人を助けます。
詳しくは書きませんが、この時から二人の腐れ縁が始まることとなります。
どうも付き人さんは自分のことを客観的に見られない人のようです。
いつもTシャツにジーパンのような恰好をして外見に無頓着ですが、スカートを着たり着物を着たりすると、メチャかわいいようです。
もったいないですね。
外見は無頓着でも内面、特に黒猫に対する自分の気持ちはわかっているようです。
自分でも恋愛に奥手であることを自覚しています。
森さんはインタビューで、「恋愛は目的に到達するかしないかのぎりぎりの部分が一番美しいと考えて」いると言っていますので、二人の関係はずっとこんな調子なんでしょうね。
作者さんも美意識が厳しいんですね。
美学に関する薀蓄は『黒猫の遊歩』ほどではありませんが、ポー好きにはうれしい内容になっています。
ポーは全部読んでいないので読んでみようかとkindleで英語の全集を買いました。
読めるかな・・・。
たぶんダメでしょう。
二作目あたりから、やっとこのシリーズに慣れてきました。
『黒猫の薔薇あるいは時間飛行』が単行本で出ているようです。
早く文庫本にしてくださいませ。
そうそう、二人の関係はホームズとワトソンかと思っていたのですが、違いました。
お姫様とお姫様を助ける白馬の騎士が妥当かと思います。
奥多摩でランチ ― 2014/07/07
たまたま夫が奥多摩で食事をしたことを思い出し、その店に行ってみようということになりました。
ボーナスもでましたし、今、美味しいものに飢えている(?)私たちなので、さっそく予約をして出かけていきました。
沢井駅から急な坂道を下り、川の方へ行きます。
ちょっと予約時間に早かったので、吊り橋を渡ってみます。

吊り橋を渡ったところに寒山寺の鐘があり、誰でも好きに鳴らすことができます。
たまたま中学生ぐらいの女の子が4人ぐらい続けて鳴らしていました。
鐘の音は余韻を楽しみたいものです・・・。

赤い屋根が鐘つき堂で、上にある建物が寒山寺です。

向こう岸に「ままごとや」、その向かい側に澤乃井園があります。
澤乃井園の入り口のうさぎさんです。

川の見える庭には椅子やテーブルがありチケットを買うと、そこでおそばや豆腐、お酒が飲めるようになっています。
さて、お料理です。

紫蘇ジュースと滝川豆腐、猪口っとおぼろ。
滝川豆腐はソーメンみたいになっていました。

四種類のお酒を飲んでみました。
下戸の私はさわ音が飲みやすかったです。
夫は純米辛口が一番で、2番は本醸大吟醸ですって。
この後に涼し酒を飲みましたが、私でもするっと飲めます。

魚が何かとか説明してくれなかったので、わかりません。
鮎?
お酒の肴にびったりですね。

左の銀むつ大吟醸粕漬は普通のとは違い、食べるとぷーんと酒粕の匂いが匂いたちました。
これ以外に湯葉の含め煮やてんぷら、お造りがありました。
〆はうなぎおこわ。

これはこれでいいのですが、やっぱり鰻はいつものが好きです。
可もなく不可もない豆腐料理でした。
お値段が内容をかんがみてちょっと高いかな・・・?
多摩川はゴムボートやカヤックでにぎわっています。

大学時代、一度だけゴムボートで多摩川を下ったことがあります。
おもしろかったです。
今は商売になっているんですね。

涼しいかと思ったら、意外と暑いです。
やっぱり山の上に行かないと涼めないようですね。
向日葵とわんこ ― 2014/07/08
犬を公園に連れて行くのに、おんぶバッグを買いました。
スリングに入れようとすると、両足を踏ん張って抵抗するのですが、おんぶバッグは気に入っているらしく、抵抗しません。
こんな風に黙っています。

抱っこするよりも暑くなくていいのですが、これを見た人はびっくりですよね。

散歩途中の畑の向日葵が満開になりました。

わんこと一緒に写真を撮ろうとしても、無視されてしまいました(笑)。
柚月裕子 『最後の証人』 ― 2014/07/09
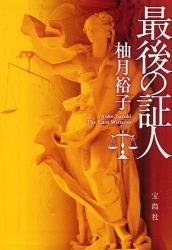
元検察官で刑事事件専門の弁護士の佐方貞人は、愛情のもつれから起こったらしいホテルでの殺人事件を担当することになります。
検察官は彼の元上司だった筒井の部下の庄司真生で、彼女のことを筒井は佐方と同じぐらい優秀だと評価しています。
状況証拠も物的証拠も被告人の有罪を指し示すものでしたが、佐方は事件に潜む真実に気づき、それを明らかにしていきます。
途中で自分の思い込みを覆され「エッ」と思い、最後に佐方の「裁判の目的は事件の真相をあきらかにすることだ。裁判は検察官や弁護士のためにあるんじゃない。被告人と被害者のためにあるんだ。罪がまっとうに裁かれれば、それでいいだろう」「法を犯すのは人間だ。検察官を続けるつもりなら、法よりも人間を見ろ」という信条になるほどと思いました。
『このミス』大賞受賞作家の中で、一押しの作品です。
西條奈加 『いつもが消えた日―お蔦さんの神楽坂日記』 ― 2014/07/10

『無花果の実のなるころに』の続編がでました。
またお蔦さんの粋な振る舞いが読めると楽しみにしていました。
ところが、この本、「あたたかな情緒あふれる」短編集ではありませんでした。
桜寺学園の元クラスメートの森彰彦と彼とサッカー部の後輩の金森有斗、近所の薬局の息子の洋平が望の作った夕食をたいらげた日に、有斗の家族がいなくなりました。
家は血だらけで誰もいないのです。
お蔦さんはそんな有斗を家族が見つかるまで自分の家に引き取ることにします。
神楽坂商店街の人たちの協力の仕方は半端ではありません。
古き良き時代のお隣さんという感じです。
日常の謎を解く殺人の起こらないミステリーと思っていたら、違いました。
お蔦さんという古い日本を体現するような人と現代の社会問題というギャップがおもしろいのかもしれませんね。
望君のお料理が楽しみなシリーズです。
望君のような息子求む!(笑)
「オルセー美術館展 印象派の誕生―描くことの自由」@国立新美術館 ― 2014/07/11
いつもは終わる頃に行くことが多いのですが、購入した1874チケットが期間限定だったので急いで行ってきました。
期間限定って買ってから友人が気づいたのです。
私ってよく説明を読まずに買って、後から気づくことが多いです。
気をつけなければ・・・(恥)。

左がプリントアウトした1874チケット。二人分で1874円でした。
バッグの中に入れておいたので、シワシワになっています。
右が 出品作品リストです。白い紙にそっけなく印刷してあるだけのリストが多い中、今回はかわいい冊子になっています。
今までの展覧会に比べて空いていて、ゆっくり見ることができました。
しかし、いいことばかりではなかったのです。
何故かクーラーがききすぎていて、「7章 肖像画」ぐらいから寒くて寒くて。
会場を出た人がみんな「寒い、寒い」と言っていました。
これはあまり会場にいすわられたら困る、いいえ、混まないようにという新美術館の心遣いでしょうか(笑)。
今回の展覧会はマネに重点を置いているようで、最初と最後がマネでした。
ポスターになっている「笛を吹く少年」と、どこがいいか私にはわからなかった「ウナギとヒメジ」や「シャクヤクと剪定ばさみ」、そして、晩年の「ロシュフォールの逃亡」で〆。
彼って人以外は下手な画家なのでしょうか?
私が一番気に入ったのは、ベタですが、ミレーの「晩鐘」です。

この絵の周りだけ神々しいほどの静けさに支配されていた気がします。
雪景色はとても描きにくいものだと思います。
白い雪ってどう表現したらいいのか。ただの白では質感がでないし・・・。
そう思っていたら、モネがお手本のような絵を描いていました。

クロード・モネ 「かささぎ」
白でも色々な白があります。
この画面ではわかりませんので、是非会場で確かめてくださいませ。
マネ展に行った時に印象に残った女性がいます。
ベルト・モリゾです。
彼女の描いた絵が一点ありました。
女性が画家になるのが難しい時代でした。
彼女の姉も画家を志していたのですが、結婚して画家の道をあきらめたそうです。
その姉と子を描いた作品が「ゆりかご」です。

モリゾも結婚後、絵を描いていないそうです。
色々なことを語っている絵です。
うれしかったのは、モネの「死の床のカミーユ」が見られたことです。
この絵があると思っていなかったので、なんで人がいるのかしらと思って見てみるとびっくり。

実物はもっと淡い色でした。
背景をしらないと見過ごしそうな絵でした。
久しぶりにのんびり見ることのできた展覧会でした。
遅く行くと、また混みそうですので、見たい方は早くいくといいでしょう。
ランチはちょっと遅くなったのですが、三階の「ブラッスリー・ポール・ポキューズミュゼ」で食べることにしました。
今まで食べた時はお客さんは数えるほどだったのに、この日はめずらしく満員でした。でも、それほど待ちませんでした。
ランチ+前菜のMENU ROUGEにしました。

前菜は野菜を使ったあっさりしたもので、メインはチキン。

前に食べた時は結構胃にズシッときましたが、今回はそれほどこってりしていなくてよかったです。
デザートはクレームブリュレ。
次回、国立新美術館に来た時は六本木ランチにしようと思います。
最近のコメント