五木寛之 『海外版インド② 百寺巡礼』 ― 2011/07/04
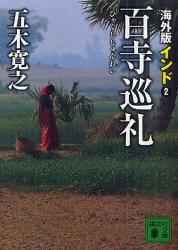
インドのブッダ最後の旅のルートの後半が書かれています。
その旅よりも印象的だったのが、二人の人です。
この2人はインドのカースト制度による差別をなくすために闘った、そして今も闘っている人です。
カースト制度はヒンドゥー教にまつわる身分制度で、4つのカーストに分かれています。上のカーストから書くと、バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ、そしてカースト制の枠外としてのアンタッチャブルと言われれている不可触民という風になっています。現在もカースト制度は続いており、IT産業がいかに栄えていても、インドの農村に行くと未だ電気のきていないところは存在しますし、不可触民に対する差別はひどいものです。
その一例として、インド農民(不可触民)の自殺が多いそうです。1998年から2003年の6年間に10万人にもなるそうです。農業をするために井戸掘りや肥料などの資金を借金し、返済できずに自殺するのだそうです。
『女盗賊ブーラン』という本を読んだことがあります。この本の中には目を覆うような悲惨な不可触民の女性の生活が書かれています。今もこの状態が続いているのです。
アメリカのキング牧師やインドのガンジーについて知っていても、インドのアンベードカル博士については全く知りませんでした。
アンベードカル博士は不可触民として生を受け、後にアメリカで経済博士号を取得し、イギリスで弁護士資格を取り、インドの法務大臣になり、インド憲法を起草した人です。
彼は「こころの改革によらなければ差別はなくならないと考え、ヒンドゥー教徒であることを捨て、仏教徒として改宗宣言」をし、不可触民の差別解消のために闘かいました。
もともと仏教は平和的なものですが、社会を変革するためには闘わなければならないというのがアンベードカル博士の考えでした。
アンベードカル博士はガンジーと同じ時を生きた人です。初めて知ったのですが、ガンジーはカースト制度を擁護する立場だったのです。アンベードカル博士が不可触民階層にも分離独立選挙を認めるようにガンジーに迫った時、ガンジーは”死の断食”に入り、博士はガンジーに屈したそうです。
残念ながらアンベードカル博士は志半ばで亡くなりました。
法務大臣までしたのに、彼の遺体はムンバイの一般市民用の火葬場では受け入れられなかったそうです。それほどカースト制度は堅固なのです。
このアンベードカル博士の意思を継いだのが、日本人の佐々井師です。
彼らの考える仏教とは「利他一利」。
「自らのいのちは捨てても他者のいのちを救う。何の見返りは求めない。つまり自利を捨てた一利のみ」
彼らの仏教は「戦う仏教」とも言われています。それ故に批判もあるようです。
彼らについてもっと調べてみようと思っています。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://coco.asablo.jp/blog/2011/07/04/5943784/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。