望月麻衣 『京都寺町三条のホームズ15 劇中劇の悲劇』 ― 2020/08/11
暑い日が続いていますね。
今年の夏はどこにも行かず、家でのんびりしています。
ここ数年、夏になると軽井沢に犬連れで行っていたのですけど。
ツルヤでお買い物ができなくて残念です。
今朝、犬たちは6時頃に散歩に行きましたが、暑くてすぐに帰ってきました。
やっぱりしばらくはお散歩は無理そうです。

兄犬はこんな風に「僕、つまんない」をしています。

すぐに読める、簡単な読み物をということで、ホームズ・シリーズの新刊を読んでみました。
読み始めてすぐに後悔するはめになりますが、仕方なく最後まで読みました。
物語は2つあります。
1つ目。
元贋作師の円生に、上海で描いた絵が日本に戻ってくるのを機に、家頭邸で円生作品の展覧会をしようと持ちかけます。
しかし、円生は自分はもう絵を辞めようと思っていると言って断ります。
ホント、面倒なおっさん。
この他に人の恋路を助けたり、結構世話焼きな、葵とホームズの二人でした。
二つ目。
『蔵』に、前に吉田山荘の新古館で朗読会を開いた相笠くりすがやって来て、ホームズに彼をモデルにした作品を書かせてくれと頼みます。
作品はすでに書き上がっており、ホームズにその作品を読んでから判断して欲しいと言うのです。
というわけで、この本の7割は相笠が書いたという作品です。
望月さんが後書きで、「京都ホームズで海外の名作ミステリーのパスティーシュにチャレンジ」したそうです。
「パスティーシュ」とは「他の作家の作品から借用されたイメージやモティーフを使って作り上げられた作品」だそうです。
彼女が取り上げたのが、エラリー・クイーンの『Yの悲劇』。
この作品は何十年も前に読んだはず。
まったく忘れていて、どういう風にパスティーシュしたのか、私にはわかりませんでした。
日本の昭和初期、大富豪の一家に起こった難解な事件にホームズが挑むという内容です。
パスティーシュ作品に興味がある方は読んでみてもいいかも・・・?
本格的ミステリーを好む方にはお勧めしません。
このシリーズはもう読まないと思います。
畠中恵 『いちねんかん』 ― 2020/08/13

しゃばけ・シリーズの19弾目。
今回は、驚くことが起こります。
というのも、若だんなの両親が店からいなくなり、若だんながお店の主となったのです。
いなくなったと言っても、おきのという祖母のおぎんの遠縁から文が来て、九州の別府の温泉にいるから湯治に来ないかと言われ、夫婦共々出かけることにしたのです。
それも一年間の長きに渡って。
若だんなは病気がちで、すぐに熱を出し寝付いてしまいますから、一年間も無事にすませることができるかどうか、店の者たちも妖たちも、みんな心配でした。
佐助と仁吉が忙しい時の若だんな付きとして妖の屏風のぞきと金次を店表で使うことにします。
一年間ですから、色々なことが起こります。
五十両の持ち逃げ、貴重な紅餅(紅花の花弁を集めて作られた紅花染や口紅の原料)の盗難、疫病の流行、婿選びの手伝い、賊との戦い・・・。
今まで以上に妖たちが頑張ってくれます。
若だんなは寝付きながらも、なんとか主として一年間を過ごしていきます。
安定した面白さのシリーズです。
そういえば若だんなが考えた旅用の薬袋の話はどうなったのかしら?
8歳になった兄犬はこの頃よく寝ています。
今日もママのベッドの上で、ゴロンと横になって寝ています。

この前、ペットクリニックで体重を量ったら、3.9㎏。
見事にお太りになりました。中年太りというもんでしょう。

犬部屋で掃除機をかける時に、犬はクレートに入れておきます。
そうしないと掃除機が怖いらしく、部屋の中を駆けずり回って邪魔です。
写真を撮っても、兄犬は無視して寝ているのに、弟犬はカメラ目線です。
M.C.Beaton 『Agatha Raisin and a Spoonful of Poison』 ― 2020/08/14

オーディオブックの表紙が可愛らしいので、載せてみました。
アガサのシリーズも19作目。後、11冊で終わりです。長いわぁ~。
アガサの探偵事務所は繁栄していて、浮気調査、行方不明の子供や犬猫探し、企業のスパイ調査などで大忙しです。
しかし、アガサは満たされていません。なぜなら愛する人がいないから。
もうこれはどうにもなりませんね。
そんな頃、ミセス・ブロクスビーがある依頼の話をしに来ます。
Comfrey Magnaに住んでいるアーサー・チャンスというSaint Odo The Severe教会の牧師が、年に一回の村祭を開催するので、アガサにPR担当になってもらいたいと言っているというのです。
もちろんチャリティですから一銭もでません。
断りに二人でわざわざComfrey Magnaまで行ったのですが、アガサですから、またまたバカなことをやってしまいます。
ホルモンのせいですか?私にはないホルモンですねぇ。
イギリスの50代の女性、もしくは肉食人種の女性はみんな持っているのかしら?
たまたま牧師と一緒にいたイケメンの教区民で建築家のジョージ・セルビーにポッとなってしまい、彼と一緒にお仕事ができるならと、引き受けちゃうんです。
みなさん、おわかりですね。アガサが関わるんですからお約束通り、このお祭りでとんでもないことが起こってしまいます。
18歳の若い探偵・トニがアガサに、ジャムのテントがおかしい。
若者達が随分並んでおり、彼らがテントからハイになって出て来ているというのです。
調べようと思った時に、ハイになった一人の女性が、「スーパーマンのように飛べるわ」と言いながら教会の塔から飛び降りてしまいました。
一体ジャムの中に何が入っていたのでしょうか?
アガサはミスター・チャンスから依頼を受け、調査を始めます。
その中で、イケメン・ジョージの妻が事故で死んでいることがわかりますが、それが殺人だと言う人が現れます。
アガサはホルモンの関係(笑)からジョージの妻の事件にも興味を持ち、今度の事件と同様に調べることにします。
今回、チャールズはアガサに恨まれましたが、ナイスな意地悪をします。
彼は相変わらず気まぐれないい加減な人ですが、アガサの男の選び方には批判的です。
トニは最初の恋愛でしくじった経験から、なかなか一歩を踏み出せずにいます。
18歳のイギリスの女の子なのにまだバージンらしいです。
アガサの友人で刑事のビルと親しかったのですが、友人以上の関係にはなれないし、元探偵でケンブリッジに行っているハリーとも合わないようです。
アガサにしてみれば、若くて可愛いというだけで嫉妬の対象なのにね。
この嫉妬心からアガサは後にとんでもないことをやります。
まあトニにしてみれば、アガサの探偵事務所のような老人ばかりいる所(50代1人、60代3人、70代1人)よりも、若い人と接したいみたいだから、良かったのかもしれませんがね。
最後に爆弾を持ってくるのが、ビートンさんのやり方。
元亭主のジェームズがやってくれました。
ジェームズの話は次回に続くようです。
今週の通販は北海道の六花亭の「おやつ屋さん」です。

今回はシーフォームケーキが3つ入っています。
一番好きなマルセイバターサンドは5個入っていて、嬉しいです。
あ、これに水ようかんなどが2缶入っています。冷蔵庫に入れちゃったけど。
24個入りで3000円です。
綾瀬まる 『まだ温かい鍋を抱いておやすみ』 ― 2020/08/15
兄犬がトリミングに行ってきました。
ペットクリニックにトリマーさんが来てやっています。
いつもトリミングをしてくれていたトリマーさんがお店を辞めたので、この際、年なので何かあった時のことを考えて、ペットクリニック内でやってもらうことにしました。

耳がいつもより短くなっています。

これぞ折り紙で折る犬、みたいな形の顔ですね。
幼く見えますが、8歳(人間で50歳)のおっさんです(笑)。

6篇の物語。
コミュ障の鳥を体に抱く女。
ウザい家族のいる、初恋の彼の枝豆パンを食べ続ける女。
子育てと家事、仕事でいっぱいいっぱいな平凡な女たち。
夫が鬱で休職中の、浮気をする女。
友人が難病で死にそうな、人の心に鈍感な男。
子を亡くし、生きる気力を失った女。
どの人も知ってか知らずか、心が苦しくてもがいています。
食べることは生きること。
誰かが作ってくれる食べ物が体に心に働きかけて、少しずつ人を癒やしていきます。
それがちんけなラブホのピザであろうが、夫に作らせるパンであろうが、料理人が作る料理であろうが・・・。
「苦しい時間を耐えていく人の食卓に豊かさを作りたい」
そんな気持ちで毎日のご飯を作っていけたらいいですね。
毎日、毎日作り続けていると、献立を考えるのが嫌になります。
せっかく作ったのに、美味しくなさそうに食べられるとね。
私も誰かに作ってもらいたいんですけど(笑)。
南杏子 『ブラックウェルに憧れて』 ― 2020/08/16
某医科大学入試で、女子学生が何年にも渡って差別的取り扱いをされていたというニュースがあったのはいつだったでしょう?
それまでは大学入試は純粋に点数で合否が決まっているんだと思っていましたし、命を扱う医科大学でということにショックを受けました。
あれから入試は是正されたのでしょうか?

題名の「ブラックウェル」とは、アメリカで初めて医学校を卒業した女性です。
エリザベス・ブラックウェル(1821-1919)はイギリスのブリストルに生まれ、11歳の時にアメリカに移住します。
ブラックウェル家は熱心なクエーカー教徒で、男女の差別を嫌い、奴隷制に反対だったそうです。
教師として家族の生活を支えるために働いていた24歳の時に、子宮癌の友人が彼女にこう言いました。
「女性のお医者さんがいたら、恥ずかしい思いをしなくてすんだかもしれない」
「なぜ、あなたは医学を勉強しないの?」
この言葉を聞き、ブラックウェルは医師になることを決意します。
12の医学校に手紙を出しますが、ことごとく入学を拒否されますが、ただ1校、ニューヨーク州のジェネルヴァ医学校だけが彼女を受け入れてくれました。
しかし、入学してからも男女差別の壁が立ちはだかります。
1849年に首席で学位をえて卒業しますが、アメリカの病院は彼女を採用してくれませんでした。
仕方なくパリの産院で修行しますが、眼病で右目を失明し、外科医の道はたたれます。
それでもブラックウェルは諦めませんでした。
NYで診療所を開き、女性だけで運営する病院を開院し、女性医師養成学校を設立していきます。
(詳しくはこちらを参考にしてください)
ブラックウェルの意思は受け継がれ、沢山の女性医師が誕生しています。
彼女が受けた男女差別はもはや昔のことでしょうか?
2018年8月、中央医科大学の解剖学教室の教授・城之内泰子の元に『月刊証言者』の記者・原口久和がやってきます。
彼は「長年に渡る女性差別が露見した中で、医学部に入学し、卒業して医師となった女学生たちが、どのようなキャリアプランを掲げ、どのような思いで医療の道に踏み出し、それぞれに闘っているのか」を書きたいので、城之内自身のキャリアに関する話を取材したい。そして卒業生も紹介して欲しいというのです。
城之内は教授になって初めて解剖学実習を受け持った、4人の卒業生を紹介します。
解剖実習の班編制は成績順に決められますが、女性が班に2人になると、男性3人に女性1人となるように操作されていました。
城之内はそういう操作を行わないことにし、その結果として女性だけ4人の班ができました。
女性だけの班を止めるようにと言う圧力がかかりましたが、城之内は自分の辞任をかけて、突っぱねます。
そこには彼女の深い後悔の念があったのです。
長谷川仁美は眼科医になりました。
白内障の手術なら外科手術班の誰にも負けないという自信があります。
次の白内障オペチームのリーダーに自分が選ばれると思っていました。
しかし、思ってもみなかった人が選ばれます。
そしてその後、陰湿ないじめが起こり、彼女は自分のキャリアの変更まで考え始めます。
仁美の話を読んでいるとあまりにも辛くて、途中で読むのを止めて、一息ついてからまた読み始めました。
女性であるというだけでコミュニティーから外され、生理休暇を取るから、少しぐらいオペが上手くても、一回やらせれば手技を教えてもらえるし、いい加減、嫁にいけば・・・。
こういう言葉が心に刺さってきます。
南さんは医師ですから、こういうことを男性医師が実際に言う様々な場面に出会ってきたのでしょうね。
知性と品性は比例しないんですね。
板東早紀は検診医。
かつて母校の病院で循環器内科医として働いてきました。
学生だった頃に出産し、シングルマザーとして父の助けを借り、なんとか働いてきましたが、無理だと悟り、キャリアを捨てました。
市中病院の勤務医をした後、認知症の父の介護のためにアルバイトの検診医となったのです。
父の症状は進み、徘徊、妄想、失禁・・・と大変な毎日です。
椎名涼子は救急救命医でしたが、仕事中に倒れ、閑職に追いやられていました。
そんな彼女に持ちかけられたのが、エスコートドクター。
外務省医務官だった父親の都合で、海外滞在経験があったからです。
私生活では麻酔科医の夫は家を出ていき、離婚届を送ってきました。
まだ夫に未練があります。
エスコートドクターとして関わった人に言われた言葉に救われます。
安蘭恵子はNICU(新生児集中治療室)で働く小児科医。
限られた人数で24時間ケアをしており、ナースもドクターも限界の状態です。
彼女には夫と一人娘がいます。夫は脱サラし、自然派農場経営に手を出しますが、上手くいっていません。
そんな時に、体に異変が起こります。
医師になろうと思う人には真面目な人が多いと思います。
地道に勉強し続けるというのは真面目さが必要ですもの。
おまけに女性医師は仕事の過酷さの他に、職場や家庭での女性差別にも対処していかなければならないのですもの。
女性医師には優秀な人が多いと思っていましたが、艱難辛苦を乗り越える力があるからでしょうか。
まだまだ女性差別のなくならない日本社会ですが、働いている女性たちの一人一人がブラックウェルのようにあきらめずに、次の世代のために働き続けていってもらいたいです。
本の中で城之内教授が言っています。
「人間の脳には、男性脳も女性脳もないというのが解剖学の最新の知見」だと。
脳には性差がない、あるのは個人差だけ。
そう思うと、男はとか女はとか言うのが馬鹿らしくなりますね。
思い込みやステレオタイプの偏見を捨て、人間として生き易い社会を作っていくことができればと思います。
「もし社会が女性の自由な成長を認めないなら、社会の方が変わるべきなのです」
ブラックウェルのこの言葉を噛みしめながら、共に歩んでいきましょう。
木宮条太郎 『水族館ガール7』 ― 2020/08/17

前巻でイルカのルンが出産をしました。
水族館では出産後も気を抜かず、「緊迫の三日、警戒の七日、魔の十日」といい、この間は赤ちゃんを二十四時間ウオッチをするようです。
そろそろ十日が過ぎようという時に、ルンが病気になってしまいます。
そのためルンと赤ちゃんは別々のプールに入れられ、離ればなれになってしまいます。
由香は人工のイルカミルクを与える係になりますが、結構大変です。
自分たちでイルカミルクを作らなければならないし、授乳の間隔が短く、気を抜く暇はありません。
ルンに赤ちゃんを託されたと思った由香は、赤ちゃんのために不眠不休で頑張ろうとしますが、チーフに諭されます。
由香の仕事はイルカ担当として全体を統轄すること、感情に溺れず、冷静かつ客観的に周りを見ろと。
離されたルンと赤ちゃんんは淋しそうです。
なんとかして2匹を対面させるために、由香はあることを思いつきます。
今回も色々と学ばせてもらいました。
私が知らないだけかもしれませんけど、イルカは共同哺育をすることがあり、保母イルカって珍しくないこと。
イルカも人も、母性は自動的にできあがるものではなく、時間をかけて、作り上げていくものだということ。
赤潮や漂流ゴミのことなど、他にもありますが、とにかく生き物に関わると色々なことが見えてくるのですね。
由香と梶も幸せになりそうです。
こういう本だから恋愛模様も描かなければならないのかもしれませんが、私にしたらどうでもよくて、かわいいイルカたちと会えればいいわ。
ニッコリーには心配させられましたけど。
表紙に惑わされず、読んでみると面白いシリーズです。
次回、イルカビーチがどうなるのか、早く読みたいです。
馳星周 『ソウルメイト』&『陽だまりの天使たち ソウルメイト2』 ― 2020/08/18
馳さんが犬を描いた作品があるということで、読んでみました。
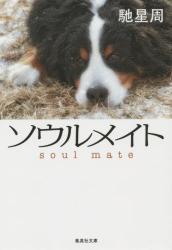
2冊ともに短編集です。
母の飼っていた柴犬を探すために一年間求職し、ボランティアとして被災地福島へ行く息子。
飼い主に殴られ、引越の時に捨てられたウェルシュ・コーギー・ペンブローク。
骨肉腫で断脚され三本脚になったフラットコーテッド・レトリーバー。
イリオモテヤマネコの子を育てる犬と老人。
愛犬の最期を看取った男と安楽死させた男。
愛犬が死に、ペットロスに陥っている男。
様々な犬と人間の絆が描かれています。
男性の飼い主の方が多いのは馳さんが男だからでしょうか?
犬を愛するのは男性の方が多いのでしょうか?
「犬は、人間のようにあれこれと思い悩んだりはしないのだ。その時その時を賢明に行き、過去の出来事やまだ起きてもいない未来に惑わされたりはしない」
このような生き方は人間も真似した方がいいようです。
「出会った瞬間から、ぼくたちは魂の伴侶なんだよ」
猫は気ままで、家に居着くと言います。
その反対に犬は飼い主に。
だから犬を特別に思うのかもしれませんね。
私は犬も猫もどちらも好きです。
犬をソウルメイトと思えるかしら?
もちろんかわいとは思いますが、どうもそこまで思えないです。

幸せそうに寝る兄犬です。
中山七里 『帝都地下迷宮』 ― 2020/08/19
中山七里デビュー10周年記念12ヶ月連続新作企画で2月に出版された作品です。
1月と4月、5月、6月のは読んだので、5冊目です。
図書館に予約して読んでいるので、結構いいペースで読めています。
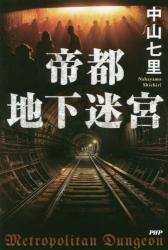
この作品はシリーズ物ではありません。
題名だけ見ると、東京が帝都と呼ばれていた時代の話かと思いますが、違います。
現代のお話です。
小日向巧は公務員。
東京都の区役所で生活支援課相談・保護係をやっています。
ようするに生活保護申請に来る区民の相手です。
彼は26歳。まだ若いので理想に燃えていて、相談に来る人のことを考えて、いえ、考えすぎてしまい、課長の山形にいつも限られた予算を考えて判断せよと指導されています。
ようするに相談に来ても親身になって相手する必要はないということですね。
こういう公務員ばかりではないと思いたいですが、区役所に行くことが滅多にないので、私にはわかりません。
こんな彼の趣味が変わっています。
鉄道オタク、といっても色々とジャンルが分かれていて、彼以外には見かけたことのない廃駅鉄なのです。
ある夜、小日向はオタクとしてはあるまじき犯罪行為に手を出してしまいます。
廃駅である銀座線万世橋駅に入りこんだのです。
万世橋駅から神田駅まで可能な限り線路を辿るというのが目的でした。
ところが、誰もいないはずの廃駅で、彼は女の子と出会いました。
バカみたいに身分証明書を見せてしまうところが、小日向の生真面目さというか世間知らずなところです。
何故か女の子に拉致されてしまい、地下住民のリーダーらしい久ジイという老人に引き合わされます。
久ジイは、わしたちと一緒に廃駅に住んで共犯者になれ、もしわしたちのことを外部に漏らしたら、彼が「夜な夜な立入禁止区域に出没し怪しい行動を繰り返していると区役所に通報する」と脅すのです。
結局小日向は特別市民ということに落ち付きます。
好奇心は猫をも殺すとはよく言ったもので、よせばいいのに小日向はこの地下都市にすむ住人たちのことを調べてしまいます。
そして深みにはまり、少しでも役立ちたいと地下でも生活保護申請の相談を受けることにします。
そうこうするうちに、小日向によく絡んできた輝美という飲んだくれ女性が殺されているのが見つかります。
持っていた身分証明書から彼女が公安の刑事であることがわかります。
何故公安が彼らのことを探っているのか?
疑問を持ちつつ小日向は死体遺棄まで手伝っちゃいます。
どうしようもないおバカさんですね。
公安や捜査一課、果ては国家権力まで敵に回した、小日向たちの運命は・・・。
廃駅鉄なんて、本当にいるんでしょうか?
出てくる博物館動物園駅は前を通ったことがあり、中がどうなっているのか見たいと思いました。
2018年から19年まで一般公開、今年2月に「京成リアルミュージアム」が開催されていたようですが、知っていたら行ったのに。
コロナ後にまた開催してくださいね。
あらすじを知らずに読んだので、楽しめました。
でもちょっとこれはありえないなとかいう所も結構ありました。
まあ、廃駅に住むということが荒唐無稽な話ですからねぇ。
最後に良い意味でのドンデン返しがありますが、手のこんだミステリーではありませんので、ミステリーを読もうという方は気をつけてくださいね。
<今日のわんこ>
いつも楽しませてくれる兄犬。
何故か前足を前に出して寝て(?)いました。
苦しくないのかしら?

濱野ちひろ 『聖なるズー』 ― 2020/08/21
本屋大賞にノンフィクション本大賞があるのを知っていますか。
2018年に新しく作られた賞です。
その中で面白そうな本を図書館などで借りて読むようにしています。
プレイディみかこさんは昨年『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で大賞を取りました。
前に紹介した『ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち』は今年の候補作品です。
今回の本も候補作品のひとつです。

表紙を見ると、題名に「ズー」があるので動物園か犬の写真ですから犬に関するノンフィクションかと思いますよね。
そう思って読み始めると、最初から違和感に囚われます。
プロローグから著者の赤裸々な性暴力の開示なのです。
これは一体何?と戸惑い、この本は私の考えたような、心温まる動物たちの本ではないことに気づきました。
この本は濱野さんが京都大学の大学院で専攻している、文化人類学におけるセクシュアリティ研究に関する論文の副産物です。
テーマは「動物性愛」。
本によると現在「動物性愛とは、人間が動物に対して感情的な愛着を持ち、ときに性的な欲望を抱く性愛のあり方を指す。動物性愛は性的倒錯だとする精神医学的見地と、動物性愛は同性愛と同じように性的指向のひとつだとする性科学・心理学的見地」とに分かれているそうです。
私は動物に性的欲望を抱く人がいることにびっくりしました。
小説で人形や女性の足などに欲望を感じるフェティズムを描く作品を読んだことはありますが、実際に動物に欲望を感じる人たちが存在するとは考えてもみませんでした。
全世界で唯一、ドイツに動物性愛の団体「ZETA/ゼータ(寛容と啓発を促す動物性愛者団体)」があるそうです。
ゼータは2009年に発足し、メンバーは30人程度でほぼ全員がドイツ在住のドイツ人で男性が圧倒的に多く、主な活動目的は、動物性愛への理解促進、動物虐待防止への取組みなどです。
彼らは自らを「ズー」と称します。
濱野さんはこの団体のメンバーと連絡を取り、「動物性愛者は、どんなふうに自分のセックスと向き合っている」のかを知り、自分の愛とセックスの問題を捉え直そうと考えたのです。
濱野さんは最初はメールで問い合わせ、その後、ビデオ通話、そしてドイツへと赴き、ズーたちと会い、何日か彼らの家に泊まり込み、生活を共にしていきます。
その中で彼らから話を聞いていきます。
勇気がありますね。こういう話は懐に飛び込んでいかないと、なかなか聞けませんものね。
彼らのパートナーは犬(大型)が多いようです。犬は一番身近な動物ですから。
彼らのことをアブノーマルだと切り捨てることは簡単です。
でも立ち止まって考えてみるのも必要だと思います。
ズーの動物への接し方を濱野さんは新しい愛し方のひとつと捉え、ズーであることとは、「動物の生を、性の側面も含めてまるごと受け止めること」であるそうです。
「動物」を「人間」にしてもいいですね。
人は異性を愛の対象と考えることが多いけど、同性の場合もあるし、動物の場合もあるし、ロボットだっていいし、別に人を愛さなくても・・・。
それでいいんじゃないと思える、そういう柔らかな感性がこれから必要かもしれませんね。
そういう世の中になると、生き易くなるでしょうね。

どう考えても、パートナーにはなり得ない2匹です。

永遠の3歳ですもの。
犬の去勢についても問題提起されています。去勢はあくまでも人間側の都合ですよね。
私自身、馳さんの本の後に読んだ後だったので、ちょっと落ち着きが悪く、戸惑っています。
犬をソウルメイトと思えるということは、少なからず犬をパートナーと認めているということですが、性的なことは絶対にないとは言えないですよねぇ。
気づいていないだけってこともあるかも・・・。
こういうことに強い拒絶反応を起こす方は、くれぐれも気をつけてお読みください。
追伸:論文はこちら。
佐々涼子 『エンド・オブ・ライフ』 ― 2020/08/22
この本も本屋大賞・ノンフィクション本大賞の候補作です。

この本では訪問看護師・森山文則に2018年8月にすい臓がんを原発とする肺転移が見つかってから亡くなるまでの話をメインとし、著者自身の経験と森山が務めていた京都の訪問医療を行う渡辺西賀茂診療所で2013年からの7年間に最期を迎えた人たちの話が描かれています。
病院ではなく家で最期を迎えたいと誰もが願うのではないでしょうか。
しかし様々な制約があり、たいていの人は諦めて病院で最期を迎えることが多いように思います。
私の親もそうでした。
父親は多発性骨髄腫で8年間入退院を繰り返し、最期は病院で亡くなりました。
まだ意識があった時に、「なんでこんなになっちゃったんだろう」と嘆いていました。
多発性骨髄腫は進むと骨が脆くなる病気なので、在宅で看るといっても難しいのではないかと思います。
母親は急性心筋梗塞でしたので、寝込まず、あっという間もなく亡くなってしまいました。
父の場合は亡くなった時にそれほどショックは受けませんでした。
闘病生活が長かったので、別れる時の準備が整っていたからです。
母の場合は本当に亡くなったの、という感じで、離れて暮らしていたので、尚更、まだ生きているような気がしています。
人には死を受容するための時間が必要ですね。
佐々さんのおじいさんやお母様の話を読むと、羨ましいなぁと思いました。
お母様はお父様に愛され、幸せでしたね。
お父様は難病にかかり、ロックイン症候群になってしまったお母様を最期まで介護していたそうです。それも完璧に。
私なんか性格が悪いですから、お父様のエゴのために生かされ続けていたんじゃないのと思ってしまいます。
私だったら、ロックイン症候群になるくらいなら死にたいと思うと思います。
佐々さんのお母様はそう思ったとしても、お父様のために生き続ける道を選んだでしょうね。
渡辺西賀茂診療所で働く人たちは訪問医療のモデルになるような方々です。
彼らは余命少ない患者のためだけを考え、時間とかお金とか責任とかは考えずに行動に移してくれます。
患者が最期にどうしてもやりたいこと、例えば、家族とディズニーランドに行くとか、潮干狩りに行くとか、をやらせてくれるのです。
こんなことをしてくれる診療所など、どこを探してもほぼないと思います。
この本に出てきた人たちのような最期を在宅で迎えるにはどうしたらいいのでしょうか。
「いい医者に出会うか、出会わないかが、患者の幸福を左右しますね」
「主治医がどれだけ人間的であるかが、患者の運命を変えてしまうんですよ」
「いい死に方をするには、きちんとした医療知識を身につけた、いい医師に巡りあうことですね」
これらは渡辺西賀茂診療所で働く医師たちが言った言葉です。
在宅医療は医師の裁量が大きいそうです。
自分の望むような在宅医療をおこなってくれる、いい医師を探すのは難しいんではないでしょうか。
第一我々患者に医師が「きちんとした医療知識」を持っているかどうか、わかりませんものね。
「出会う、出会わないも、縁のもの」
こう思って達観してしまうしかないのでしょうね。
どうしても納得した死に方をしたかったら、渡辺西賀茂診療所がある京都に住んじゃうという手がありますが(笑)。
佐々さんの書く物に興味を持ったので、しばらく読み進んでいこうと思います。
最近のコメント