帚木蓬生 『聖灰の暗号』 ― 2010/02/01

帚木(ははきぎ)さんの書くものは、社会問題と関係のあるものが多いのですが、今回はキリスト教の迫害についての話です。
彼はどれだけ本を読んで調べているのだろうと思うほど、いろいろなことを題材に本を書いています。
その取材力には感心しているのですが、作家としては今ひとつというところがあります。
何と言っても最後が甘いのです。
今度の本は今までの本のように最後はガッカリとはならなかったのですが、内容が内容だけに、なんかミステリーとして片付けるのも・・・という感じです。
フランスに留学している歴史学者、須貝彰は十三世紀から十四世紀にローマ教会から迫害を受けていたカタリ派について調べていました。
カタリ派を代々擁護してきた伯爵の居城のある、南仏のトゥルーズの私立図書館で古文書を見ていると、偶然、<地図>の棚にカタリ派の弾圧に関する資料を見つけます。
その古文書は二枚、四ページしかないもので、絵地図と詩のようなものが書かれていました。
須貝は絵地図の場所に、残りの手稿が隠されていると思い、再度トゥルーズを訪れ、パリのペール・ラシェーズ墓地で出会った女医、クリスチーヌ・サンドルと、川で砂金採りをしていたエリックの力を借り、残りの手稿を探し出そうとします。しかし、トゥルーズの図書館長を初めに次々と奇怪な殺人事件が起こります。
キリスト教徒の迫害というと、本の中にも出てきますが、日本の五島列島の隠れキリシタンのことを思い出します。
何故、寛容を唱える宗教が不寛容な行動を取るのでしょうか?
手稿の形を取っていますが、書かれているカタリ派の信ずるものは、あるべき宗教の姿のように思えます。
その古文書は二枚、四ページしかないもので、絵地図と詩のようなものが書かれていました。
須貝は絵地図の場所に、残りの手稿が隠されていると思い、再度トゥルーズを訪れ、パリのペール・ラシェーズ墓地で出会った女医、クリスチーヌ・サンドルと、川で砂金採りをしていたエリックの力を借り、残りの手稿を探し出そうとします。しかし、トゥルーズの図書館長を初めに次々と奇怪な殺人事件が起こります。
キリスト教徒の迫害というと、本の中にも出てきますが、日本の五島列島の隠れキリシタンのことを思い出します。
何故、寛容を唱える宗教が不寛容な行動を取るのでしょうか?
手稿の形を取っていますが、書かれているカタリ派の信ずるものは、あるべき宗教の姿のように思えます。
J.D.ロヴ 『この邪悪な町にも夜明けが』 ― 2010/02/02
イヴ&ローク・シリーズの新作です。
このシリーズは翻訳が速いですね。もう22巻が出てしまいました。
なんか表紙がロマンス物みたいです。

この巻を読みながら、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を思い出しました。
そう、イヴ&ロークでもクローンが扱われているのです。
有名な美容整形外科医が、彼のオフィスで心臓を一突きにされ殺されていました。彼はミスター・パーフェクトというほど、たたいても埃の出てこない聖人君子のような人でしたが、イヴは胡散臭さを感じます。
殺される前、彼は若い美しい女性の患者と会っていました。
そうして突き止めたのが、彼が若い女の子を集めて、なにやら実験をしているらしいということ。
そして、ノーベル賞を取った遺伝学博士、ウィルソンとも親しく、知り合いの幼くして孤児になった女の子を引き取り、その子をウィルソンが創立した女子の教育機関に通わせ、息子の嫁にしていたということです。
遺伝学者、再建形成外科医、私立女子寄宿学校。
この3つから何が出てくるのか・・・。
イヴとロークの私生活では、なんとロークが感謝祭にアイルランドにいる親戚をニューヨークに招きます。
たくさんいる親戚に戸惑うイヴとローク。
彼らが普通の人と同じになっちゃ、つまんないですね。
遺伝学者、再建形成外科医、私立女子寄宿学校。
この3つから何が出てくるのか・・・。
イヴとロークの私生活では、なんとロークが感謝祭にアイルランドにいる親戚をニューヨークに招きます。
たくさんいる親戚に戸惑うイヴとローク。
彼らが普通の人と同じになっちゃ、つまんないですね。
長く続くと、マンネリ化してしまうのは、仕方ないですが。
イヴとロークがいつまでも、野性味を忘れないでくれるといいのですが。
Susan Boyle のCD ― 2010/02/06
朝、外を見ると空模様が変です。
富士山には雪が降っていて、他の部分には黒い雲が。今日は寒いので、ひょっとして地方では雪が降っているのかしら?

本を読む代わりに、CDを聞いています。
スーザンは昨年の紅白歌合戦に出演しましたが、彼女がデビューするきっかけは、2009年4月のイギリスオーデション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」です。
スーザンは昨年の紅白歌合戦に出演しましたが、彼女がデビューするきっかけは、2009年4月のイギリスオーデション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」です。
彼女を見た観客や審査員は、彼女がプロの歌手になりたいと言った時、失笑したものでした。
しかし、彼女が歌い始めると、顔色が変わりました。(Youtubeでこの場面が見られますので、是非見てみてください。)
彼女はパッとしない容姿にに関わらず、歌がすごく上手かったのです。
その彼女が、出したCDが「I Dreamed A Dream」です。

なんともさえないおばさんだったのですが、今や見られるようになっています。
すごいですね。やっぱり美の専門家はどんな人も変身させられるのですね。
私も変身できるかしら?
このCDの中で気に入った歌のひとつは、ローリングストーンズの作った「Wild Horses」です。ストーンズとは全然違う歌かと思うアレンジですが、人生に疲れ果てた人の悲哀にジーンとくるものがあります。
もちろん「I Dreamed A Dream」は彼女の十八番。何回聞いてもいいですね。
「Cry Me A River」を聞いて、ジャズ系も結構いいなと思いました。
もちろん「I Dreamed A Dream」は彼女の十八番。何回聞いてもいいですね。
「Cry Me A River」を聞いて、ジャズ系も結構いいなと思いました。
これから、彼女がどういう風になっていくのかわかりませんが、悪い人に騙されずに、好きな歌を歌い続けていって欲しいと思います。
彼女の声は神様から与えられた「贈り物」なのですから。
「レンズの向こうの人生」&「靖国」を観る ― 2010/02/08
2つのドキュメンタリー映画を観ました。
「レンズの向こうの人生」は写真家のアニー・リーボヴィッツについての映画です。彼女の写真は誰でも一度ならず見たことがあるはずです。

カメラを持っている女性がアニー。
妊娠したデミー・ムーアや、暗殺される数時間前に写されたジョン・レノンとオノ・ヨーコの写真は特に有名です。
ベッド・ミドラーが『ローズ』の宣伝用に撮ったという写真(左下)は、ベッドが何千本のバラの花の上に寝ていますが、このバラの棘をアニー自ら取ったそうです。何本あるのかしら?
アニーはもともと美術の教師にでもなろうと思っていたのですが、ひょんなことからローリング・ストーン誌の写真を撮ることになり、その後、ローリング・ストーンズのツアー撮影まで手がけ、一躍有名になったそうです。
しかし、ツアーに同行するうちに麻薬に手を出してしまい、麻薬と手を切るためにリハビリ施設に入り、ローリングストーン誌は辞め、ヴァニティ・フェア誌で働くことになります。
しかし、ツアーに同行するうちに麻薬に手を出してしまい、麻薬と手を切るためにリハビリ施設に入り、ローリングストーン誌は辞め、ヴァニティ・フェア誌で働くことになります。
この頃からセレヴを撮ることが多くなったようです。
今やアニーに撮られること=セレヴの証明とまで言われるようになっています。
アメリカの作家スーザン・ソンタグは師でもありパートナーでもあったそうです。下の写真はアニーが撮ったスーザンとアニーの子供です。
アニーは五十歳過ぎに子供を出産したそうです。

彼女の写真のすごさが、映画の中でこう述べられています。
「彼女の写真から一行の文章を読み取ることができる」
「その人の何かを写真に反映できる」
「物語る写真」
写真にすべてを捧げているアニーですが、いい写真を撮るためにお金に糸目もつけないからか、破産宣告をされたと報道されていましたが、その後どうなったのでしょうか?
もうひとつのドキュメンタリー映画は「靖国」です。
「彼女の写真から一行の文章を読み取ることができる」
「その人の何かを写真に反映できる」
「物語る写真」
写真にすべてを捧げているアニーですが、いい写真を撮るためにお金に糸目もつけないからか、破産宣告をされたと報道されていましたが、その後どうなったのでしょうか?
もうひとつのドキュメンタリー映画は「靖国」です。
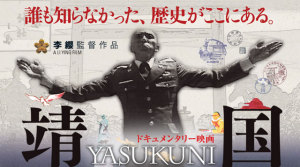
色々とマスコミで取り上げられていたようですが、この中で印象に残った場面を紹介しておきましょう。
それはあるお寺の住職の話です。彼の父親が第二次世界大戦で戦地に行き、亡くなっています。
仏間にある遺影写真は、父親が兵隊の姿のものです。
それについて、彼はこのようなことを言っています。
「僧侶が戦争に出向いたということを忘れてはいけない。宗教者は人間の命の尊厳を言い続けていくものである。自らが他国民を殺し、自らも殺される戦闘員としていくことは、聖職者として破綻せしめるものである。戦争の過酷さをきちんと刻んでおこうといいう思いで(この写真を)かけている」
立場による「戦争」と言うものの受け取り方の違いを見せてくれた映画でした。
「僧侶が戦争に出向いたということを忘れてはいけない。宗教者は人間の命の尊厳を言い続けていくものである。自らが他国民を殺し、自らも殺される戦闘員としていくことは、聖職者として破綻せしめるものである。戦争の過酷さをきちんと刻んでおこうといいう思いで(この写真を)かけている」
立場による「戦争」と言うものの受け取り方の違いを見せてくれた映画でした。
梁 石日『闇の子供たち』 ― 2010/02/10
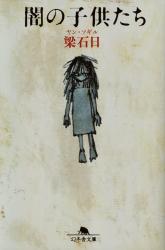
何週間か前のニュースを聞いてびっくりしました。
20代の母親が自分の子供(4歳)のヌード写真を売った上に、男に何をされるか知っているのに、娘を男に会わせたというのです。
よく読んでいるミステリーの影響もあり、アメリカなどは幼児ポルノの大国というイメージがあります。
よく読んでいるミステリーの影響もあり、アメリカなどは幼児ポルノの大国というイメージがあります。
日本はそれほどでもないと思っていたのですが、そこら辺にいる母親がこういうことをして、それを買う男がいたということは、幼児ポルノの市場が日本に確実に存在し、身近になっているということですよね。
なんともおぞましいことです。ここまで来たんですね、日本も。
『闇の子供たち』はちょうどそのニュースを聞いた頃に読みました。
タイの貧しい山岳地帯や難民キャンプで育った子供たちが売られたり、誘拐されたりした、その先に待っていることは・・・。
タイの貧しい山岳地帯や難民キャンプで育った子供たちが売られたり、誘拐されたりした、その先に待っていることは・・・。
そして、それをどうにかしようとして闘うNPOの人たち。
8歳で売春宿に売られた子供が、このようなことをされているとは・・・。
フィクションとはいいながら、作者の想像力だけで書けるものじゃないと思います。
人の命の尊さなんて、この現実をつきつけられると、空しい世迷言に思えます。
臓器移植も出てきます。自分の子が心臓移植をしなければ死ぬという現実をつきつけられ、他国の子の心臓を買おうという親を非難することは簡単です。
親たちの気持ちを否定することはできないなとは思うのですが、何か是とはできません。
日本にいると、こういうことに疎くなります。
でも、知った後に何ができるのか・・・。
アレグザンダー・マコール・スミス 『友だち、恋人、チョコレート』 ― 2010/02/11
古都エジンバラに住む、<応用倫理学レビュー>誌、編集者のイザベルのシリーズ第二弾です。
まあ、普通のミステリーとは違い、どっちかというと日常の些細なことに哲学的思考が入る内容で、一作目はあまりおもしろいとは思わなかったのですが、二作目はイザベルの哲学的思考にも慣れたのか、楽しく読めました。

姪のキャットが友達の結婚式に出席するので、彼女の店を手伝っていたイザベルは、元心理学者の男性に出会います。
彼は心臓移移植を受けていました。
彼は心臓移移植を受けていました。
不思議なことに移植を受けた後から、ある男の顔のイメージが現れるようになります。
その話を聞いたイザベルは、持ち前の好奇心から、心臓の持ち主を探し始めます。
イザベルのいい相談相手でもある、片思いの相手、ジェイミーとの関係も微妙になります。
私はアイルランドでは年上の女性と年下の男性が付き合ったって、問題ないんだと思っていましたが、そうじゃないんですね。
アイルランドにも年上女性と付き合うことに偏見があるんですね。
意外と家政婦のグレースがこの本のアクセントになったりしています。
頭でっかちの学者なんかより、ずっと労働者の方がまっとうな考え方をするのです。
バレンタイン・デーも近いので、チョコレートに関する哲学的思考を挙げておきましょう。
「考えれば考えるほど、チョコレートに関する哲学的思考範囲は広がるばかり。まず、アクラシア、すなわち意志薄弱が第一の思考対象として浮かび上がる。チョコレートはよくないと知っているとすれば(ある意味でチョコレートは実際わたしたちにとってよくないのだ。たとえば体重が増えるし)、なぜ人はそれを食べすぎるのか?意志薄弱のせいではないかと疑っていいのだろう。でも、それでもチョコレートを食べるのなら、そうするのがもっとも関心のあることだからということになる。わたしたちの意志は、好きとわかっていることをするようにそそのかす。ということはわたしたちの意志は薄弱ではないということになる。それどころかけっこう強いことになる。そしてわたしたちに本当にしたいこと(つまりチョコレートを食べること)をするようにしむけるのだ。チョコレートって単純じゃない。」
こんなことゴチャゴチャ考えずに、おいしいんだから食べりゃあいいじゃん。
「考えれば考えるほど、チョコレートに関する哲学的思考範囲は広がるばかり。まず、アクラシア、すなわち意志薄弱が第一の思考対象として浮かび上がる。チョコレートはよくないと知っているとすれば(ある意味でチョコレートは実際わたしたちにとってよくないのだ。たとえば体重が増えるし)、なぜ人はそれを食べすぎるのか?意志薄弱のせいではないかと疑っていいのだろう。でも、それでもチョコレートを食べるのなら、そうするのがもっとも関心のあることだからということになる。わたしたちの意志は、好きとわかっていることをするようにそそのかす。ということはわたしたちの意志は薄弱ではないということになる。それどころかけっこう強いことになる。そしてわたしたちに本当にしたいこと(つまりチョコレートを食べること)をするようにしむけるのだ。チョコレートって単純じゃない。」
こんなことゴチャゴチャ考えずに、おいしいんだから食べりゃあいいじゃん。
そう私なんか思っちゃいますが、哲学的思考って面倒なんですね。
イザベルにかかっちゃうと、食べ物にも倫理問題があり、論文まで書けちゃうんです。
イザベルにかかっちゃうと、食べ物にも倫理問題があり、論文まで書けちゃうんです。
小川糸 『食堂かたつむり』 ― 2010/02/13
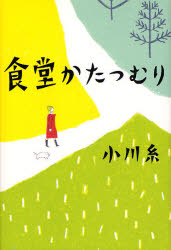
映画化されているので、いつもは読まないものを読んでみました。
なんと言っても美味しいもの大好きな、食いしん坊ですから。
同棲していたインド人に、部屋の中のもの、ぬか床以外すべて、へそくりまでも盗られてしまった倫子は、驚きのあまり声がでなくなってしまいます。
10年以上も戻っていなかったふるさとに帰ろう。
そう思い立ちふるさとに戻ると、歓迎してくれたのは豚、おかんのペットのエルメスでした。
同棲していたインド人に、部屋の中のもの、ぬか床以外すべて、へそくりまでも盗られてしまった倫子は、驚きのあまり声がでなくなってしまいます。
10年以上も戻っていなかったふるさとに帰ろう。
そう思い立ちふるさとに戻ると、歓迎してくれたのは豚、おかんのペットのエルメスでした。

おかんとはなんとなく気心が知れず、お互いに距離をとっていました。
なにもかもなくした倫子は、自分にできる唯一のことをして、ふるさとでくらしていくことにします。
倫子の得意なモノは、料理でした。
一日一組のお客を相手に、好みなどを聞き取り、その人に合った料理を出すというものです。
いつしか倫子の料理を食べた人は幸せになるという噂が広まります。
そうするうちに、母に病気が見つかります。
と、なんとなくよくある話になっていきます。
一日一組のお客を相手に、好みなどを聞き取り、その人に合った料理を出すというものです。
いつしか倫子の料理を食べた人は幸せになるという噂が広まります。
そうするうちに、母に病気が見つかります。
と、なんとなくよくある話になっていきます。
もう最後はバレバレ。大人用の童話として読むと腹も立たないでしょう。
それよりも、美味しそうな料理が楽しみです。
それよりも、美味しそうな料理が楽しみです。

たとえば、フルーツサンドイッチとラプサンスーチョン。
①レーズン食パンの表面に湯煎したチョコレートを薄く塗る。
②生クリームとヨーグルトのクリームにはちみつをたらしたものを塗る。
③洋ナシを薄く切ってのせる。
簡単ですね。一度作ってみましょうか。
ラプサンスーチョンはちょっとスパイシーな紅茶です。
ザクロカレー。
ざくろを使ったカレーで、詳しい作り方は書かれていませんが、どうもたまねぎと牛肉を使うようです。美味しいんでしょうか?一度食べてみたいですね。
ジュテームスープ。
季節の野菜を使い、組み合わせる野菜や量は毎回違い、コトコト煮こんだスープ。スープはあまり好きではありませんが、美味しそうです。
最後には、豚のエルメスが食べられちゃいますが、豚も美味しく食べていただければ、本望ですかね?
祖母が倫子に言った言葉は深いものがあります。
「イライラしたり悲しい気持ちで作ったお料理は、必ず味や盛り付けに現れますからね。食事を作る時は、必ずいいことを想像して、明るく穏やかな気持ちで台所に立つのですよ。」
簡単ですね。一度作ってみましょうか。
ラプサンスーチョンはちょっとスパイシーな紅茶です。
ザクロカレー。
ざくろを使ったカレーで、詳しい作り方は書かれていませんが、どうもたまねぎと牛肉を使うようです。美味しいんでしょうか?一度食べてみたいですね。
ジュテームスープ。
季節の野菜を使い、組み合わせる野菜や量は毎回違い、コトコト煮こんだスープ。スープはあまり好きではありませんが、美味しそうです。
最後には、豚のエルメスが食べられちゃいますが、豚も美味しく食べていただければ、本望ですかね?
祖母が倫子に言った言葉は深いものがあります。
「イライラしたり悲しい気持ちで作ったお料理は、必ず味や盛り付けに現れますからね。食事を作る時は、必ずいいことを想像して、明るく穏やかな気持ちで台所に立つのですよ。」
もっと食べることを大事にしなければと、思いました。
あ、それだけで読んだかいがあったかも。
映画はDVDになった時に見るかどうか考えますわ。
映画はDVDになった時に見るかどうか考えますわ。
谷根千でヴァレンタイン ― 2010/02/14
ヴァレンタインデーなので、いつもとは違った道を通り、「ショコラティエ イナムラショウゾウ」へ行ってみました。
昨年は並んでチョコレートを買いました。
昨年は並んでチョコレートを買いました。
今年も7~8人並んでいます。テーブル席が空いていたので、並ぶのを止めてケーキを食べることにしました。
ケーキは7種類売っていました。
ケーキは7種類売っていました。
「ドームショコラ」や「涙のしずく」、「ショコラドゥショコラ」は食べているので、違うものを頼みんでみました。

中が洋酒でしっとりしていて、軽い感じで食べられます。
オペラロールと言うらしいです。

こっちは甘すぎず、大人の味です。
どちらもチョコレートはちょっと・・・という人にはお勧めです。
チョコレートのこってりしたのが好きという人は私が前に食べた三種類を食べてみてください。
「ショコラティエ イナムラショウゾウ」から細い道を歩いていると、屋根に何やら色っぽい女性が。
「ショコラティエ イナムラショウゾウ」から細い道を歩いていると、屋根に何やら色っぽい女性が。

一体これは何でしょう?どういうお宅?
石屋のウルトラマン(HP参照)同様、不思議な光景です。
いつも通り根津神社でお参りをして、谷中せんべいの堅焼きを買い、駅前の「竹隆庵 岡埜」で桜餅を買って帰ってきました。
食べるものばっかり買ってますね。
散歩が主だったのですが、これでは痩せませんね。
駅から谷根千一周して約八千歩でした。
レスリー・メイヤー 『バレンタインは雪あそび』 ― 2010/02/16
バレンタインにはちょっと遅いのですが、主婦探偵シリーズの五作目を紹介します。

第一作では妊婦だったのに、その頃おなかにいたゾーイはもう4歳。
コンピューターを扱えるほどになりました。
ルーシーは図書館の理事になったばかりです。はりきって第一回目の理事会へ行ってみると、司書のピッツィが作業室で殺されていました。幸先の悪いこと。
州警察のホロビィッツ警部補には探偵のまねごとをしないようにと釘をさされます。
しかし、それで負けるルーシーではありません。またまた犯人探しを始めます。
バレンタインも日本とは違います。
州警察のホロビィッツ警部補には探偵のまねごとをしないようにと釘をさされます。
しかし、それで負けるルーシーではありません。またまた犯人探しを始めます。
バレンタインも日本とは違います。
ルーシーたち夫婦は、着飾って、ディナーに出かけるようです。うらやましい。
結局は大雪で行けなかったのですが、夫のビルはハート形の巨大な箱に入っているチョコレートと花束を買ってきて、ルーシーに渡します。
結局は大雪で行けなかったのですが、夫のビルはハート形の巨大な箱に入っているチョコレートと花束を買ってきて、ルーシーに渡します。
日本と違って夫が妻にプレゼントを渡すのですね。
日本人にも真似してほしかったわ。
日本人にも真似してほしかったわ。
フェイ・ケラーマン 『蛇の歯』 ― 2010/02/18
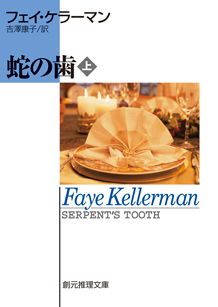
ロサンゼルス市警警部補のデッカーとユダヤ教徒のリナ夫婦の話です。
毎回二人の熱々さにはあてられっぱなしです。今回も仲がいいですよ。
高級レストランで銃の乱射がありました。
死者13名、負傷者30名以上という大惨事です。
犯人はこのレストランの元バーテンダーで、事件を起こした後、自殺しました。
銃の発射され方向を調べてみると、犯人はどうも一人ではなさそうです。
デッカーは亡くなった家族に会いに行き、話を聞いていきます。
しばらくして、亡くなった金持ち夫婦の娘、ジーニーという女が、デッカーをセクシャルハラスメントで訴えました。
しばらくして、亡くなった金持ち夫婦の娘、ジーニーという女が、デッカーをセクシャルハラスメントで訴えました。
デッカーは彼女が何を狙ってこのような訴えを起こしたのかと不思議に思い、彼女の身辺を調べます。
デッカーの家族とはいうと、リナの亡くなった夫の友達の死をきっかけに、リナとデッカーの間に微妙な空気が。
そんな時ですが、リナは夫のセクシャルハラスメントの訴えをはらすために、警察内務部の質疑の場に出席することにします。
リナのような若い、美しい妻を持っていると、セクシャルハラスメントをするはずがないというアピールになるんですって。男の側の論理ですね。
こういう場でもリナは完璧な答えをします。
その上、デッカーの助けになるのならと、ベトナムで一緒に戦った彼の友人に、捜査に役立ちそうなことを頼みに行きます。
デッカーの家族とはいうと、リナの亡くなった夫の友達の死をきっかけに、リナとデッカーの間に微妙な空気が。
そんな時ですが、リナは夫のセクシャルハラスメントの訴えをはらすために、警察内務部の質疑の場に出席することにします。
リナのような若い、美しい妻を持っていると、セクシャルハラスメントをするはずがないというアピールになるんですって。男の側の論理ですね。
こういう場でもリナは完璧な答えをします。
その上、デッカーの助けになるのならと、ベトナムで一緒に戦った彼の友人に、捜査に役立ちそうなことを頼みに行きます。
ちょっと疑問に思ったのは、デッカーは事件についてリナにベラベラと話しているのですよ。これは職業上の倫理観に触れないのでしょうか?
デッカーが事件のことを家庭で話したために、リナを初めとして、先妻との子でデッカーの反対を押し切って警官になることにした娘、シンディまで、事件に協力することになるのですから。
家庭的には恵まれているデッカーですが、デッカーが幸せすぎても、なんかね・・・。
デッカーが事件のことを家庭で話したために、リナを初めとして、先妻との子でデッカーの反対を押し切って警官になることにした娘、シンディまで、事件に協力することになるのですから。
家庭的には恵まれているデッカーですが、デッカーが幸せすぎても、なんかね・・・。
最近のコメント